本格的な梅雨入り前に強い高気圧が関東一帯を通り過ぎた夕刻、都心では猛烈な南風が吹き荒れた。
丸の内のオフィス街では、スカートの裾を押さえるOLどころか、ビルの玄関を出た途端、体ごとドアへ押し戻されるビジネスマンたちが続出している。エントランスに立つ警備員たちも、必死の形相で彼らを守っていた。
ポンバル太郎の通りでは街路樹の枝が大きく軋み、店へ逃げ込んだグループ客は強風で髪の毛が逆立ち、席に座るなり、顔を見合わせて大笑いした。その賑やかなテーブル席に、カウンターに並ぶ平 仁兵衛と右近龍二が目を細めている。ただ、隅に座る黒革のジャンパー姿の男はサングラスの上の眉間に皺を寄せたまま、土佐の本醸造を飲んでいた。
手元に置く蛇革製らしき長財布が、男のこわもてを引き立てた。
それと同じ銘酒をなめる右近龍二が、ゴオッと唸る外の風に口を開いた。
「梅雨入り前の黒南風(くろはえ)だな……懐かしい土佐の言葉を、思い出しちゃいましたよ」
聞き慣れない黒南風に、隣の平 仁兵衛がぬる燗の盃を口元へ止めた。
「黒南風? 梅雨明けの白南風(しらはえ)なら知っていますけどねぇ?」
「平先生、黒南風って、関西から南の土地が主に使うんですよ。僕の故郷の土佐や九州に多いです。黒南風は、真っ黒な入道雲を運んでくる南風のこと。一方の白南風は、白い真夏の入道雲を運ぶ風。だから、黒南風は南国のスコール雲ですよ」
答えた龍二の顔に嫌っ気はなく、むしろお国自慢をしているかのようだった。
また、強い風が玄関の扉を揺らせ、枡の鳴子の音へ平は迷惑げにつぶやいた。
「嵐を呼ぶ風ですか。じゃあ、土佐の漁師泣かせですねぇ」
龍二が「まったく」と相槌を打った時、カウンターの隅から渋い声が響いた。
「いいや、そうでもないき。黒南風が吹かなんだら、うまいウツボが食えんぜよ。土佐の漁師は夏バテせんように、梅雨前に干したウツボを食らうがよ。ウツボは脂ののる冬が旬じゃ言うが、わしゃ、今頃がええ。この店、よう分かっちょるぜ」
サングラスの下で笑う男の陽焼けした頬は、冷蔵ケースの端にあるまだら模様の切り身に向いている。
テーブル席の客は男のサングラスに眉をしかめたが、龍二は土佐弁に喜色満面で同調した。
「そう! そうじゃき! 黒南風の吹く頃になると、この一夜干しのウツボが美味しくなるんです。お客さん、土佐からいらしたんですか?……このお店、初めてだと思いますが、カウンター席じゃサングラスは御法度です。独酌の客同士、顔を見合わせて飲むのがポンバル太郎のマナーですき」
土佐訛りになった龍二に店内の客たちが驚くと、太郎が厨房から現れた。
「申し訳ないですが、私が決めたルールです……お客さんのその財布、ひょっとしてウツボの皮ですか?」
確かに、男の財布の模様は、冷蔵ケースのウツボの一夜干しとソックリだった。
男は不敵な笑みを浮かべると、サングラスを外して肉厚なウツボの身を見つめた。左目の下に走っている切り傷の痕が、龍二だけでなく店内の客たちの背筋をゾッとさせた。それでも、太郎は動じていない。
「ウツボの皮は硬いき、財布だけやなし、昔は鮫皮みたいに刀の柄にも使うちょったぜよ……そいが、今は若い者も、あんまりウツボを食わんようになっちょる……ああ、おんしらに言うちょくが、わしぁ、ヤクザやないぜよ。名前は、岡田市蔵。元は、ウツボ漁が専門じゃったき。けんど、干しウツボと辛口の土佐の酒が最近は飲まれんいうがは、まっこと悲しいぜよ」
岡田の下まぶたの傷痕は、酒の酔いでほの赤く染まっていた。えぐれた傷は、鈎で引っ掻いたように痛々しかった。
「その傷、もしかするとウツボに噛まれた跡ですか?」
「ああ、メスの獰猛な奴に、岩穴の近くでガブリとやられた。もうちくっとで、目ん玉、いかれるとこじゃった。この財布は、その時のウツボの革で拵えた物やき。ウツボは酒の肴だけとちごうて、昔から嫁の産後の体力回復、母乳を出すのにも最適な魚じゃ。わしの女房も、こいつの世話になったがやき……12年ほど前じゃったが、東京から与和瀬ハル子ちゅう女性が、わしのおる須崎の漁港へやって来た。土佐の酒蔵を回っとるちゅう、変わった若い女じゃった。その時、わしゃ、ハル子さんに子どもがでけたら毎日食べて、ええ乳を出しやと干しウツボを土産に渡した。ハル子さんは『近い内に、ポンバル太郎って居酒屋をこの場所に出します』とメモをくれた。それから、ずっとなしのつぶてじゃった。けんど、ようやく東京へ来る機会がでけてのう。ここを探したちゅうわけじゃ」
不釣り合いに開く岡田の両目が、店の神棚に飾られたハル子の写真を見上げた。
訥々と語って辛口の本醸造飲み干した岡田に、店内が水を打ったように静まった。驚き顔を見合わせる龍二と平の前で、太郎が口を開いた。
「やはり、そうでしたか。ハル子が言ってたんですよ。『ウツボの皮って分厚くて硬いから、財布にもなるのよ』と……あれは、岡田さんの財布を目にしたからですね」
「ああ、そうがやき。ハル子さん、ビックリしちょった……けんど、残念じゃのう。あげな愛嬌のある、ハチキンなおなごは、そうおらんぜよ」
岡田の褒めそやす“ハチキン”にテーブル席の若い客が「ハチキンって、何だよ?」と囁き合った時、玄関の鳴子が大きく響いた。
「玉が八つもありそうなぐらい、男勝りな土佐の女のことでぇ。太郎さんの亡くなった奥さんは、それぐれえ、肝の据わった女傑だったってことだ」
現れた火野銀平が岡田の隣へ座り込み、独酌するお銚子に手を伸ばした。いきなりの登場だったが、岡田は銀平が何者かを火野屋のTシャツに察したようだった
「初めまして、火野銀平です。いつも、取引きをありがとうごぜえやす。岡田さんとハルちゃんのおかげで、うちは干しウツボを扱うようになったんでさぁ……そして、ハルちゃんの乳を飲んで育ったのが、あいつです」
ほころぶ銀平の視線の先に、二階から手伝いに降りて来た剣が割烹前掛けをしていた。
「こりゃ、まっこと嬉しいぜよ。ハル子さんに、よう似ちゅうのう」
店内の話が聞こえていたのか、剣は岡田へ丁寧にお辞儀をすると、岡田の長財布を見つめた。何事か言いかける剣を太郎は差し止めようとしたが、平が首を横に振って、それを制した。
「あのう……その財布、触ってもいいですか。どんな感触なのか、知りたいんです……母ちゃんは、どう思ったのか」
剣の声に、岡田はためらいなく財布を渡した。受け取る剣の指先が、かすかに震えていた。
「きめ細かくて、柔らかいんですね。思ったほど、男性的じゃないんだ」
ハル子を追憶する面々に、カウンター席がしんみりとした。それを察した岡田が、声を高くした。
「そうぜよ。ウツボは両性具有。子どもの頃はオスだったのに、成長してメスに変わったり、その反対もある。いわば、生命力の強い魚じゃき、しぶとい。だから、精もつくわけぜよ」
岡田がせわしなく剣の頭を撫でた時、またもや、玄関が鳴った。
「あ~あ、もうスゴイ風! ここまで歩くのに、疲れちゃったわ。太郎さん、元気の出るお酒と料理、お願いしま~す!」
飛び込んで来た高野あすかの口調に
「あっ……ポンバル太郎のハチキンがやって来た」
と剣がつぶやいた。
「剣君、ハチキンって誰のことよ? その意味、私が知らないとでも思ってるの?」
カウンター席へ詰め寄るあすかに、岡田が目を丸くした。
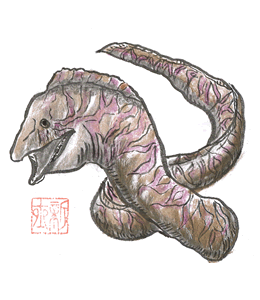
「や、ヤバイ! 銀平さん、バトンタッチ! 仲良く、あすかさんと干しウツボを食べてね」
剣が銀平にタッチして、奥のテーブル席へ注文取りに逃げた。
「お、おい、おい! まったくよう。両性具有は、ウツボだけで充分だからな」
「ちょっと! 銀平さん、もう一度言ってみなさいよ! 誰が両性具有なのよ!」
毎度のように始まったあすかと銀平のすったもんだに、店内は一気に賑やかになった。
「何もそこまで、ハル子に似なくてもいいのにな」
龍二と苦笑いする太郎に、干しウツボを注文した平が続けた。
「う~む、今夜のあすかさんはウツボじゃなくて、ヤブ蛇ですねえ」
土佐の本醸造を飲み干した岡田の笑い声が、ポンバル太郎へ響き渡った。
