渋谷スクランブル交差点のネオンボードが都心の気温6℃を示した夜、新潟の南魚沼では、初雪がたった一日で1メートル以上積もったとテレビニュースは報じた。前代未聞の事態に除雪車の手配が間に合わず、地元の交通網はマヒしているとキャスターが叫んでいた。
晩秋を愛でる余裕もなく、一気に冬へ突入してしまう近頃の気候に、東京のオシャレ好きな女性はうんざりしている。ポンバル太郎の通りをトレンチコートの肩をすくめて歩く高野あすかも、しかめっ面だった。
だが、扉を開けた途端、憂鬱な気分を消し去るような、いい匂いが漂った。
「う~ん、お味噌のいい匂い! それだけじゃないわ……このダシの香り、何かしら」
あすかが、高くて筋の通った鼻梁をひくつかせると、たいていはテーブル席の男たちが見惚れるのだが、今夜はレンゲと小鉢を手にして何かを待ち構えている。卓上には、富山の純米酒が四合瓶で出されていた。
「おっ、呼びもしねえのに、やっぱり鼻が利きやがる。まぁ、脂がたっぷりのった真鱈の上物だから、口の肥えたあすかだって黙るほどうめえぜ」
冷酒グラスを手にする火野銀平は隣の右近龍二へ聞かせながらも、赤い目元であすかをカウンター席へ誘っている。ほろ酔いの銀平と龍二だけでなく、手招きしている平 仁兵衛の前にも小鍋用の七輪コンロが置かれていた。
「分かった! 鱈鍋ね! 私、それ大好きなんです、太郎さん!」
小躍りしながら厨房へ声を投げたあすかへ返されたのは、しゃがれた太い声だった。
「太郎ちゃんは、ちょっと出かけてるでぇ。わしの忘れ物を、ホテルへ取りに行ってくれてんねん。今夜の寒さで膝が痛むよって、歩くのが難儀やろうと気を使うてくれてなぁ」
厨房からぬうと上半身を突き出した中之島哲男は、豆しぼりの鉢巻き姿に出刃包丁を握っている。白い割烹前掛けには、魚をさばいたらしき血糊が染みていた。
堂に入った料理支度の中之島へあすかが見入っていると、満面の笑みを見せる平は期待して声を高めた。
「富山沖の真鱈が数年ぶりに豊漁だそうで、銀平さんが大物の差し入れをしたんですよ。だから太郎さんは、今週、お客さんに鱈鍋をふるまうことにしたそうです。その話を中之島の師匠にしたら、『よっしゃ! わしに任せとけ』と大阪からすっ飛んで来たわけです」
そうなら、一流料理人の中之島が腕によりをかける鱈鍋だけに、取材しない手はない。カウンター席に座ったあすかは、レシピを訊き出そうと手帳を取り出し、スマホをカメラモードに切り替えた。
「さすが酒食ジャーナリスト。抜け目ないや」
冷酒グラスを飲み干した龍二があすかに感心した時、カウンターの端っこから
「私は結構ですわ、いりまへんで。鱈鍋なんて、見たくもないし」
とあからさまな断りが飛んで来た。
声の主は、七三分けに光る頭に紺色のスーツが似合う、三十歳頃のビジネスマンだった。
小一時間前にやって来た男は、大阪の地酒としめ鯖をつまんでいる。
太郎へしめ鯖を頼む際、「きずし、ありますのん?」と大阪弁で訊ねた男に中之島はニンマリとして一瞥を送ったが、きっぱりと鱈鍋を断られたのには顔を曇らせた。
案の定、いつもの癇癖で男にからみそうな銀平を龍二とあすかが諫めると、平が口を開いた。
「お客さんは関西の方ですか? 鱈は大阪ではめったに召し上がらないと思いますが、それを敢えて、大阪の料理人である中之島さんが仕立てるのですよ。どんな鱈鍋になるのか、食べてみたくはありませんか?」
平の気遣いにも、中之島はカウンターに背を向けて再び厨房へ入ると、出刃包丁で鱈をぶつ切りした。その音は不機嫌さを感じさせたが、男はにべもなく言った。
「興味ないですわ。鱈鍋は、大嫌いな父親の好物やったから。私は大阪の船場育ちやけど、幼少期までは富山の朝日町におりました。そこが、親父の故郷ですわ……もともと、越中富山の置き薬屋だったんですが、家業が傾いて、私が小学校に入る頃、大阪の船場にある製薬会社に転職しましてん。でも、田舎者の父は大阪の商売になじめず、結局、私と母を船場に置いたまま、その会社の富山支社へ単身赴任。最期は、過労から朝日町の実家で倒れて、四十五歳で死にました」
男の口元が徐々にゆがんでいくと、大阪弁に聞き耳を立てるテーブルの客たちは他人事と思えない顔つきで押し黙った。どうやら、東京へ単身赴任中の男たちのようである。
銀平とあすかが、男の話に鱈鍋は富山の名物と知った時、厨房の出刃包丁の音が止まった。
カウンター越しに鼻先の老眼鏡を押し上げる中之島が、まじまじと男を見つめた。
「あんさん、滝さんっちゅう名前とちゃうか? お父さんは、滝 正一郎はんやないか?」
中之島は手についた鱈の血を拭こうともせず、男に顔を近づけた。
「えっ! ……そうです」
男も中之島から漂う魚臭さを忘れたかのように、唖然とした顔で答えた。
なんと偶然の出逢いかと、テーブル席の客がざわつくのを銀平の声が制した。
「そう言やぁ、中之島師匠の割烹は大阪の船場近くじゃねえですかい! 以前、俺たちが関西へ旅した時に行きやした、あの大阪きっての薬の町でしょう。てぇこたあ、滝さんの親父さんは師匠の店に通ったお客さんだったてぇわけか」
銀平お得意の早合点ながら、今回は正解のようで中之島が静かに頷いた。気を取り直したあすかは、二人の会話をメモろうとしている。
その場のなりゆきを酒のつまみにしようと、テーブル席の客たちは聞き耳を立てた。
「正一郎はんは、いつも富山の本醸造と肴を注文した。春はホタルイカや白海老、夏から秋にはスルメイカ、そして、冬は鱈鍋や。しかも、朝日町ならではの特別な鱈鍋をわしに教えてくれたんや。今夜は、それを作りに来てんけど、まさか息子さんと出逢うとは、びっくらぽんやがな!」
雰囲気を和らげようと、今どき言葉でおどける中之島にも滝は硬い表情で答えた。
「よしてください。あんな男、親父やないですわ。おふくろや私をほったらかして、好き勝手に生きてた奴や。そやから、あんたの割烹に通ってたなんて一切聞いてないし、今の話かて信じられませんわ……親父は亡くなった時、石ころを握りしめてた奴や。ヒスイっちゅう朝日町の海岸で採れる宝石の一種らしいですわ。いっこも家族を大事にせんと、そんなしょうもない物を死ぬまで大事にしてた男ですねん」
誰もが固唾を飲んで滝を見つめる中、銀平の声がした。
「石ころが形見ってのも、辛ぇよなぁ」
無神経につぶやいた銀平の脇腹へ、あすかが「もう!」と肘鉄を入れた。
「いっ、痛てぇじゃねえか、何しやがる」
小競り合いする銀平とあすかに、滝は気が高ぶったのかカウンターを両手でドンと叩いた。その音にまた客席が静まった時、開いた扉の鳴子とともに太郎の声がした。
「そりゃ、ちがいますよ、滝 雄太郎さん。あなたのお父さんは、とっても家族を愛していたと思いますよ」
「ど、どうして、私の名前を……あんた、誰なんや?」
名前を言い当てられて目を丸める滝に、あすかが「この店のご主人、太郎さんです」と答えれば、太郎は手のひらほどの青緑色をした石ころを差し出した。石には二つに割った跡があり、表面には「雄太郎へ 成人祝いは、鱈のヒスイ鍋で乾杯しよう」と刻んだ文字が薄く覗いていた。それが、太郎が中之島の泊まるホテルへ取りに行った忘れ物である。
声を失くしている雄太郎へ、中之島が続けた。
「そのヒスイは、あんたの親父さんがうちの割烹で食べる鱈鍋に使うてたんや。鍋の中にヒスイを入れると運が良くなって、幸せになれるっちゅうてなぁ。それを富山支社へ行く前に、わしの店に置いて行ったんや。『雄太郎が成人する頃には大阪へ戻って、ここでヒスイを入れた鱈鍋を食いたい。だから、それまで預かっておいてくれ』と頼まれた。そして、富山で単身赴任するにも必要やからと、石を半分にして持って行った……その片割れを正一郎はんは最期に握ってたんやろう」
静まり返った店内に、厨房で鱈鍋の煮える音がしみ込んでいる。
顔がみるみる紅潮する雄太郎に、中之島は正一郎が富山支社へ赴任した理由を打ち明けた。当時、製薬会社の社長は、越中富山の置き薬を扱う支社を立ち上げた。将来はその道に詳しい正一郎を取締役にすると口説かれ、彼は妻や雄太郎のためにもと単身旅立ったと伝えた。
「……そうやったんか。親父、ごめん。ごめんなさい」
震える唇を噛みしめながら、雄太郎が嗚咽を洩らした。
緊張の糸を噴きこぼれる鱈鍋の音が切ると、中之島は無言で厨房へ戻った。
太郎はゆっくりと、ヒスイを雄太郎の前に置いた。
「お父さんとの約束の鱈鍋、今夜、召し上がりませんか。このヒスイを使って」
客の誰もが相槌を打つと、湯気の立ち昇る鱈鍋を中之島が手にしていた。
「それほど嫌いやった正一郎はんやけど、最期まで持ってたヒスイを、雄太郎君は捨ててないんやろう?」
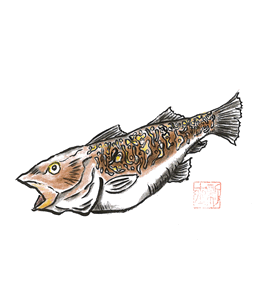 「……お見通しですね。でも、捨てなくて良かった。おかげで、こんなええ日がめぐって来ました」
「……お見通しですね。でも、捨てなくて良かった。おかげで、こんなええ日がめぐって来ました」
目の前に置かれた鱈鍋に、ハンカチで両目を拭った雄太郎がヒスイを入れると、あすかや龍二、平が立ち上がって拍手した。すると、テーブル席の客は、富山の純米酒を差し出した。
「粋な、はからいだねぇ! じゃあ、二杯目は俺の奢りだぜ」
嬉しそうに銀平が雄太郎の肩を叩くと
「皆さん、おおきに。ほんま、おおきに」と大阪弁で泣き笑いした。
鱈鍋を小鉢によそう中之島も、目尻を光らせて言った。
「その“おおきに”、うちの店に来てた頃の正一郎はんにそっくりやで」
鍋ダシの中で、青緑色のヒスイが心地よさげに揺れていた。
