クリスマスイブ前夜が金曜日とあって、原宿や渋谷は、そのまま朝まで弾けようという若者でごった返していた。繁華街では、どの居酒屋も混雑し、シャンパンタイプのスパークリング大吟醸を抜く音が響いた。
ふだんカップルの少ないポンバル太郎は、クリスマス向けのメニューや酒を置いてない。それでも、今夜のテーブル席には高野あすかの紹介で、自らが参加している「姫の会」と称する女子会の予約が入り、日本酒に合うカマンヴェールなどチーズの盛り合わせを太郎は特別に用意した。
独り者の揃った日本酒派の女子会はチーズ談議に盛り上がるはずと、高野あすかが太郎へ提案したのである。ちなみに、日本酒は「愛らしい姫の会だから」と愛媛県の酒をあれこれ推薦していた。
カウンター席の平 仁兵衛が、チーズナイフを片づける太郎に興味津々で訊ねた。
「珍しいチーズばかりですねぇ。私は、チーズにはワインとばかり思ってましたが、日本酒との相性もいいです。特に、燗をつけた純米酒は冷酒とちがって、お腹の中でチーズを固めないので、消化にもいいですねぇ」
平の言葉に女性客の一人が「そのウンチク、もらいま~す」と笑って、パルメジャーノレッジャーノの酢漬けとぬる燗した山廃純米酒を口にした。
色や形がとりどりのチーズへはしゃぐ女性たちに、カウンターに座る八百甚の誠司は落ち着かない。火野銀平は、その隣で眉をしかめている。
「平 先生まで、あすかのチーズ好きにかぶれちまったんですかい? 俺なら、あんな日本酒好きなおネエちゃんたちには、この時期、天然物のウニやツブ貝をオススメしやすがねぇ」
いつもながらに銀平があすかの手柄を腐すと、幹事の三井と名乗る女性が口を開いた。
「うちの女子会には、チーズが付き物なんです。とっておきのチーズを手に入れてくれるあすかさんには、いつも感謝してますよ……それからマスター。冷酒グラスと取り皿を、もう一組頂けませんか?」
6人がけのテーブルは1席空いたままだが、女性は鞄から小さな写真立てを取り出して、そこへ置いた。遠目にも目鼻立ちのハッキリとした女性と判り、太郎が「美人だね」とつぶやくと、見つめる誠司は前のめりになって生唾を飲んだ。
5人の女性たちは全員、無言で頷いた。冷酒グラスに愛媛の純米大吟醸が注がれる中、平は場の空気が重くなったのを察しながらも訊ねた。
「それは、陰膳ですか?」
平の言葉に、店内の数人の年配客が振り向いた。
誠司はキョトンとして「陰膳って、何すか?」と洩らし、銀平に「てめえ、それでも江戸っ子か!」と頭を一発張られた。
「陰膳てなぁ、旅に出た友人や、離れて暮らす家族が飢えないよう、膳に供える食事だ。昔は、日本全国どこでもあった習慣でえ。家族と同じ食い物や、本人の好物を供えてよう。茶碗や椀の蓋に露がついてりゃ本人は無事、なけりゃ不吉だと占ったりしたんでえ」
思いがけない銀平のウンチクに太郎と平が顔を見合わせると、客席から「へぇ、陰膳って吉凶も観るのか」と感心する声が聞こえた。
テーブル席の女性たちも占い方までは知らなかったらしく、グラスの結露としたたる水滴にお互いが胸を撫でおろした。
平が嬉しそうに、目尻をほころばせた。
「その写真のお友だちを、皆さん、案じてるんですね。美しい方ですから、モデルさんか何か、ファッション関係で外国にいらっしゃるのでしょうかねぇ」
お世辞抜きに平が褒めると、三井が苦笑して、女性たちは揃ってため息を吐いた。
「それがですねぇ、まったく畑ちがいな水産研究所の技術者なんです。松山さんって名前なんですが、新種のホタテ貝の開発にマレーシアまで行って、もう3年も戻ってません。絶対、日本酒に合う新しいホタテ貝を開発するって意気込んでいました」
飽きれ顔の三井は、松山はとんでもない秘境の島にいるらしく、携帯電話やメールはおろか、手紙も届いているのかどうか不明だとぼやいた。しかし彼女は、仕事に生きているシングルな仲間のヒロインだとも語った。
「それじゃ、クリスマスどころじゃありませんねぇ。でも、日本の女性力を、世界へアピールするお話ですねぇ……できれば、松山さんの開発してるホタテ貝を、日本酒と楽しんでみたいものです」
三井と平のやり取りを聞いていた銀平が、太郎へ小首をかしげた。
「しかし、ホタテ貝は、水温が低い所じゃねえと難しいだろ? マレーシアなんて、南洋じゃねえか」
「確かに……国産の稚貝を持って行っても、水が合わねえからダメな気がするな。身の締まりが悪い大味なホタテじゃ、美味くねえしな」
その時、太郎が思い描く新種のホタテ貝を、玄関の鳴子の音が掻き消した。現れた高野あすかに女子会メンバーから歓声が上がると、銀平は渋い顔で舌打ちした。
あすかがテーブルに置いた透明なビニール袋に、彼女たちはいっそう声を高くした。太郎や平だけでなく店内の客たちが、まばたきもせず袋の中身を見つめていた。
「うひゃ! こりゃ、スゲエや! 虹色のホタテ貝だ!」
誠司が素っ頓狂な声を上げると、女子会の歓声に背を向けていた銀平も振り返った。
赤、橙、紫、黄色など鮮やかな色のホタテ貝が、袋の中に透けていた。しかし、通常のホタテ貝よりも小ぶりなサイズで、女性たちが「カワイイ!」とはしゃぐのも頷けた。
「あっ! ヒオウギ貝かよ」
銀平の声に、あすかが片目をつぶって答えた。
「さすがに、そこは銀平さんね。松山さんが、マレーシアへ持って行ったのは、この“ヒオウギ貝”なの。漢字では、緋扇貝。ホタテ貝に似てるけど、元々は、真珠養殖のアコヤ貝の系統よ。貝柱が美味しくて、関西以西の暖かい海で養殖されてる。その一番の産地が、偶然にも愛媛県の宇和島なの」
「なるほど! まさしく、この女子会“姫の会”にピッタリの、“媛の貝”ってわけですね。シャレてますね! そこに、愛媛の地酒とくりゃ、最高だ!」
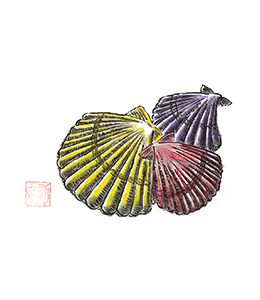 興奮している誠司が、銀平の答えるタイミングを奪った。横取りされた銀平は
興奮している誠司が、銀平の答えるタイミングを奪った。横取りされた銀平は
「この野郎、てめえは兄貴分への義理てえものを、欠いてんだよ!」
と誠司の口を捻り上げた。
「いてて! そんなぁ、俺ゃ、いつだって兄貴を想って、陰膳だってやりますよう」
「ふ、ふざけんな! 俺に、どこか旅に出て、遠くへ行っちまえってえのか!」
犬も食わない悶着に客席がアングリするのをよそに、あすかは鮮やかなヒオウギ貝のビニール袋を太郎へ手渡した。
「チーズを使った、ヒオウギ貝柱のグラタンがいいな! ねえ、みんな。そのレシピ、愛媛の日本酒と一緒に松山さんへ送ってみない!」
誘ったあすかに、女子会の全員が冷酒グラスを掲げた。それに応えるかのように、太郎の手にした虹色のヒオウギ貝がパックリと口を開いた。
