大寒の冷え込みをよそに東京湾の水温は下がらず、漁船の網には見たこともない南洋の魚が掛かっていると山手線内のトレインチャンネルにトピックスされていた。さらに、築地のセリはここ数日荒れもようで、大間産のマグロだけでなく、氷見の寒ブリも不漁。冬場の高級魚市場は高騰している。
それは、足取り重くポンバル太郎へやって来た火野銀平から察することもできた。舎弟である八百甚の誠司を従えていないのは、ご機嫌ななめな証拠である。
江戸前とはいえ小魚ばかりが目立つ冷蔵ケースに、今夜の客たちも浮かない顔だった。
「ええい! こんちくしょうめ。移転はハッキリしねえし、相場は落ち着かねえし、年明けからロクなこたぁねえ。太郎さん、ゲン直しに灘の新酒を封切ってくんねえか」
昔ながら築地の江戸っ子が愛した上方酒で縁起を担ごうとする銀平に、カウンター席でおでんをつまんでいる平 仁兵衛も「いいですねぇ、それ、ノリます」と空いた徳利を掲げた。
厨房でイワシのつみれを丸めている太郎が
「あいよっ、生もと純米酒の上燗でいいのかよ?」
と銀平へ念を押した。
「ああ、もちろん。だけど、問題は肴だぜぇ。灘の生もと純米に合う本マグロのヅケも、戻りガツオのたたきも、今夜はねえしよう」
イワシのつみれを一瞥した銀平は疲れが溜まった首筋を揉みながら、平の隣へ座った。心なしか、顔色もすぐれなかった。
火野屋は3月の決算を前にして追い込みをかける時期だけに、顔見知りの客たちは愛想笑いを浮かべながらも銀平の気持ちを斟酌していた。
すると、重たい空気を蹴飛ばすように鳴子が響いて、しゃがれた声が聞こえた。
「なんじゃい、銀平ちゃん。サバが腐ったような目ぇしてからに。マグロやカツオがなかったかて、灘の酒に合う絶品の旬の肴はあるでぇ! お誂え向きに、わしが大阪から持って来たこいつが、そうや!」
ふいに現れた中之島哲男は、京友禅の縹色の羽織と袷を重ねていた。いかにも上方らしい恰好の右手が掲げる袋には、何やら、長細い影が覗える。
「……サンマ? かな」「いや、それにしちゃ、細いよ」
口走るテーブル席の男たちに、中之島は群青色の魚を袋から取り出した。
青と銀色に光るサヨリに
「えっと、ほら、何て名前の魚だっけ?」
と、客席の男たちはもどかしげに顔を見合わせた。
「サヨリは今どきの東京人が忘れかけとる、お江戸の頃の大衆魚。東京の下町では、こいつを春先に干物で食うた。今の厳冬期、火野屋でも、サヨリは雑魚みたいなもんやろ。けどなぁ、関西では、サヨリの旬は真冬や。この時期、サヨリの白身が引き締まって、上品な味わいなんや。東京では春のサヨリを酢で締めるけど、大阪は冬のサヨリを刺身で食う。いわば、寒サヨリやな。この締まった身を兵庫県の竜野醤油で食うのが、辛口の灘酒には一番やでぇ」
中之島が25㎝前後の型のいいサヨリを袋ごと渡すと、銀平は「あ、ありがてえすよ」と礼を返しながらも、口惜しそうな表情を浮かべた。築地の春のサヨリだって、上方に負けちゃいねえ! そう言いたげに銀平が口元をグッと結ぶのを、平だけでなく、太郎も目に止めた。
その時、玄関の鳴子がゆっくりと鳴った。落ち着いた音に客たちが振り返ると、また一人、江戸小紋の袷に羽織を纏った老爺が立っていた。
「ちょいと待ちねえ。その言い分。はい、そうですかとは呑めねえよ、中之島の。江戸っ子にだってぇ、極上の寒サヨリがあるんでぇ」
葵屋の伝兵衛の登場に、客席がどよめいた。築地の移転延期について、近頃、ニュース番組で頻繁にインタビューされている伝兵衛の顔は都民に広く知られている。築地魚河岸の元締めの言葉だけに、客たちは“江戸の寒サヨリ”に聞き耳を立てた。
「いやぁ伝兵衛はん、ご無沙汰しとります。そらぁ、わしも知りまへんでしたわ。江戸の寒サヨリ、教えておくんなはれ」
助け舟を出された銀平だが、伝兵衛と中之島という巨匠同士のぶつかり合いに、気が気ではない。しかし太郎は、伝兵衛の機嫌をそこねないよう下手に出る中之島に、さすがの大阪人気質を感じた。
中之島の気遣いを汲み取った伝兵衛は、右手に提げるビニール袋を見せながらカウンター席へ誘った。その中身は、中之島のとは比べ物にならない太くて長いサヨリだった。
「東京湾のサヨリは、春先に産卵期で岸に近づいて来るんでぇ。だがよ、小せえサヨリは卵を持つと、脂と旨味が落ちる。だからよう、干物にしちまうんでぇ。ところが、昔の江戸っ子が欲しがったのは、すこぶるつきに脂ののった、産卵前のでっけえサヨリだった。こいつは、東京湾の根について育った35㎝を超える大物でよ。今でも、“カンヌキ”って呼んでらぁ。真っ直ぐに伸びた長さと太さが、屋敷の門の内側に掛ける真一文字のカンヌキに似ているからだよ」
伝兵衛が言うには、冬の盛りになると東京湾や相模湾にサヨリの二年生のカンヌキが現れる。一本釣り、刺し網、流し網漁で獲り、脂ののった身は分厚く、鮨のネタにもなる。
だが、青魚ゆえに時間が経つとはらわたの臭みがキツく、江戸の料理人は、灘の酒を使って、さばいたカンヌキを丁寧に洗った。こうすると匂いが消えて、白身の旨味をもっと引き出すと解説した。
無言だった客席からため息が洩れると、中之島が納得したように頷いた。
「しかも、当時の灘の酒は杉樽で運ばれてまっから、ええ匂いがしとった。吉野杉のテルペンの匂いがはらわたの臭いをキレイに取って、カンヌキの刺身の風味も良うなったはずでんなぁ」
「察しの通りでぇ。さすが中之島の。舌が肥えた、なにわの匠だぜ」
中之島を持ち上げる伝兵衛に、銀平が恥ずかしげに頭を掻いた。
「め、面目ねぇ。あっしもカンヌキは知ってやしたが、そんな支度があったとは……しかし、カンヌキみてぇにでっけえサヨリは、築地の売れ筋じゃねえ。もったいねえ話だがよう」
独りごちる銀平の横顔に、魚匠らしい悔しさがにじみ出ていた。
笑顔で頷き合った中之島と伝兵衛が、席から立ち上がった。伝兵衛は平に小さく会釈をすると、銀平を挟んで座った。そして、中之島は太郎に厨房を借りると、大小揃った寒サヨリをさばき始めた。
太郎が燗をつけた灘の生もと純米酒を、銀平へ差し出して言った。
「サヨリってよ、どうして江戸っ子が食わなくなっちまったか、知ってるか?」
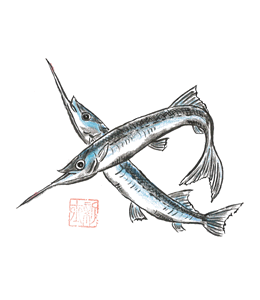 「い、いや、それも知らねえ。あ~あ、まったくよう……近頃はツイてねえ」
「い、いや、それも知らねえ。あ~あ、まったくよう……近頃はツイてねえ」
ふて腐るよりも、移転のことも含めて真剣に落ち込む銀平へ太郎が教えた。
「あのよぅ、サヨリって、白身は透き通るぐれえキレイなのに、はらわたが黒くて臭ぇからよ、“見掛けによらず、腹黒い奴”って言われたんだと。旨いサヨリにとっちゃ、迷惑な話だぜ。……銀平、築地の移転が揉めたのは腹の黒い悪党のせいだが、お前みてえな真面目に商売してる者の気持ちは、みんな、承知してるぜ」
盃を止めて長いため息を吐く銀平の背中に、店内の客たちが頷いた。
平が生もと純米酒の上燗を口にしながら、銀平の背中をさすっている伝兵衛に目尻をほころばせた。
「ポンバル太郎の客には、腹黒い江戸っ子は、一人もいませんからねぇ」
