東大寺の御水取りを準備する修二会(しゅにえ)が始まったと、銀座のLEDボードが伝えていた。いつもより文字がまばゆいのは、2℃近くまで冷え込んだ夜気のせいである。
だが、御水取りの意味を知らないのか、若いカップルはボードを見上げながら「お水取りって、何?」と小首を傾げていた。
ポンバル太郎では、カウンター席の平 仁兵衛の隣で、久しぶりに仁科美江を伴った中之島哲男が御水取りについて講釈をたれていた。中之島が気に入っている伏見の大吟醸を蔵元が醸すのは、修二会の時期と重なっている。
御水取りに興味なさげな男性客の視線は、冷酒で酔い始めた中之島のウンチクよりも、総絞りの着物をまとった京美人の美江に注がれている。
「御水取りの由来は、実は、若狭の国にあんねん。つまり、美江さんの祇園の店“若狭”と同じや。神話の時代、魚釣りをしとって東大寺の集まりに遅れた若狭の国の明神さんが、お詫びに二月堂のほとりで清らかな井戸水を掘り出したちゅうわけや。その水は“御香水(ごこうすい)”と呼ばれて、今も二月堂の中へ運ばれてるんや」
聞えよがしな声を、中之島は聞き入る平だけでなく、厨房で寒サバを酢で〆ている太郎にも向けた。脂ののった関西の冬の“きずし”は、中之島の好物である。
「あら! 御香水と言わはったら、伏見には御香水神社がありますえ」
美江がしなを作って冷酒のデキャンタを中之島へ傾けると、こっちにも注いで欲しいとばかりに客席の男たちは羨ましがった。
「そうや。つまり御香水は、二月堂の水と同じように、神聖な水っちゅうわけや。伏見の酒を仕込む軟水や」
中之島は美江が酌した伏見の大吟醸をひと口含むと、あらためて舌鼓を打った。自慢げな口ぶりに惹かれた平が「私も、同じ酒を」と太郎へ大吟醸を注文する中、玄関の鳴子とともに若い声が聞こえた。
「だけど中之島の師匠、水が合わねぇって、よく言うじゃねえですか。東京の水道水は上等じゃねえでしょうけど、代々、深川で暮らしてきた俺にゃ飲みなれてるし。伏見の軟水ったって、江戸っ子には、よく分からねえや」
現れるやいなや、中之島に突っかかったのは八百甚の誠司だった。中之島だけでなく、平も、黒いスーツ姿でいささか酔っている誠司に眉をしかめた。ほのかな焼香の匂いが、客たちの鼻先をくすぐった。
「誠司君、お悔やみ事の帰りですか?……ヤケ酒なら、やめておいた方がいいですよ。仏様も心配します」
平が誠司に忠告すると、太郎もふらつく誠司へ「今夜は帰れ」と厨房から首を突き出した。だが、誠司は聞こえないふりで、カウンター席にドッカリ座った。
珍しく周りへ媚びない誠司に、中之島がひと呼吸置いて、飲み干した大吟醸のグラスを手渡した。
「……わしは、かめへんで。ところで誠司君。その内ポケットの物は、わけありか? お葬式帰りに、けったいな物を持ってるやないか」
眉を八の字にする中之島が眼鏡をずらすと、平は誠司の礼服の懐を覗いて不思議そうにつぶやいた。
「紅い房の十手? それを、葬儀へ持って行ったの?……よほど、故人にゆかりの物ですか?」
誠司が胸ポケットに右手を入れて取り出すと、それはカウンターを照らすダウンライトに鈍い光を浮かべた。浅草の仲見世で売っている安っぽい土産物の十手とはちがい、太い鉄棒にカギ型の刃が施してある。
「ほう! 実戦向きの十手やな。昔、捕り物番組の名俳優が使うてたのと、同じや。ちゅうことは、亡くなった方は相当な時代劇ファンかいな?」
感心する中之島の言葉とは裏腹に、テーブル席の若い男性客は「ダセえの」と鼻白んだ。
誠司は、長いため息の後で肩を落とした。握り締めている十手の紅い房は使い込んだらしく、手垢で幾分くすんでいた。
「……うちの祖父ちゃんの形見っす。映画俳優だったんすよ」
途端に、テーブル席の客は「えっ!?」と洩らして、バツが悪そうにうつむいた。
中之島と平が驚いた顔を見合わせると、太郎の包丁の音も止まった。
つかの間、無言で十手を見つめていた美江が口を開いた。
「それ、中川辰三はんの十手とちゃいますやろか。辰三はんは、うちの店へ太秦映画村や京都撮影所の帰りに、ちょくちょく来てくれましたんえ……そうどしたか。あんさんが辰三はんのお孫さんとは、これも御縁どすなぁ」
中川辰三は、かつて捕り物番組のヒーロにも抜擢された昭和の時代劇俳優だった。晩年は、人情ドラマの脇役として登場することが多く、いぶし銀の演技を高く評価された。
平と中之島は、記憶に残っている若かりし頃の中川辰三の面影を誠司に重ねていた。辰三とよく似た誠司の額に、皺が寄った。
「えっ!? そんなはず、ねえすよ。辰三祖父ちゃんは、五十歳から酒は止めちまったんでさぁ……ちょいと、マズい事件を起こしちまって」
「ええ。お酒は、一滴も口にしなかったわ。伏見の大吟醸が飲めなくなった代わりに、伏見の水を飲ませてくれって頼まれて、あては、いつも御香水を汲みに行ってました」
当時、若狭を始めたばかりだった美江は、初めて来店して気に入ってくれた辰三のために足繁く伏見へ通い、御香水を持ち帰っては、体を冷やさないように白湯にして出した。その白湯と美江のおばんざいのおかげで、京都での十日間の撮影生活を乗り越えれると辰三は喜んでいた。
撮影の最終日、美江は辰三に酒を飲まない理由をおそるおそる訊ねてみた。
辰三は寂しさを隠すように、ふっと鼻息を洩らした。
二十年前に酔った勢いで、つまらない口喧嘩から、撮影現場の若いスタッフについ手が出てしまった。そのせいで、捕り物のヒーロー役は降板。トレードマークだった十手を、二度と持てなくなった。つくづく自分は、バカ野郎だと吐き下した。
「その時、辰三はんが口惜しそうに鞄から取り出したのが、その十手どした。辛いけど、決して忘れたらあかん戒めやと言わはって、いつも持ち歩いてやしたわ……けど、未練もあったんどっしゃろねぇ」
しんみりと余韻を引く美江の京言葉に、もう誰も十手を茶化しはしなかった。
厨房から出て来た太郎は、誠司の好きなカツオの酒盗と上燗の本醸造をカウンター席に置いた。一盃やってけと、目顔で誘った。
誠司が小さく頭を下げて、口を開いた。
「美江さんのおっしゃる通りでさぁ……ガキの頃、辰三祖父ちゃんの家へ遊びに行くと、十手を誇らしげに俺へ持たせてくれやした。それが、あの日から突然、隠しちまった。祖父ちゃんは、最期まで、捕り物のヒーローに返り咲けなかったのが心残りだったにちげえねえ。俺、この十手を通夜と葬式に供えたんでさぁ。だけど、金属だから棺桶に入れらんねえ。それで、俺が形見にもらうことにしやした」
燗酒の湯気が、誠司を慰めるように立ち昇った。
中之島がお銚子を手にすると、平が誠司の隣に盃を置いた。
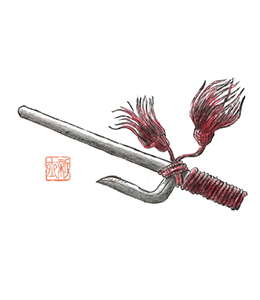 「辰三さんが辛抱していたお酒を、心置きなく飲ませてあげませんか。おつかれさまのご褒美酒ですよ」
「辰三さんが辛抱していたお酒を、心置きなく飲ませてあげませんか。おつかれさまのご褒美酒ですよ」
誠司は顔を紅潮させて、酒を受けながら目尻を潤ませた。
すると、誠司の隣へ席を移した美江が、十手に両手を合わせながら言った。
「実は、辰三はんが最期にうちへいらしたのは、去年の春どした。誠司君は知りはらへんと思うけど、今年の捕り物映画に出演が決まってたの。古参の年老いた岡っ引きの役でも、この十手が握れるんやったら俺は本望やって……そらぁ、もう、嬉しそうどしたえ」
一瞬、愕然とした誠司が涙をこらえると、中之島と平は頷き合って太郎へ伏見の大吟醸を注文した。
「その十手を、受け継いだんだ。おめえ、辰三さんが好きだった伏見の酒も、これからは飲まなきゃな」
太郎の置いた大吟醸のデキャンタに、十手の赤い房が映えていた。
