上野公園や隅田川の堤に吊るされたボンボリが、蕾をふくらませた桜の梢とともに、春一番の強い風に揺れている。街路樹から聞こえる鳩の声も、どこか嬉しげだった。
黄昏の六義園では名物のしだれ桜がライトアップされ、外国人観光客を魅了している。
先週まで花冷えの寒さに丸まっていたビジネスマンたちの背中は、シャンと伸びていた。彼らを誘い込む居酒屋には、全国各地の春の旬味がめじろ押しだ。
むろん、それに合う地酒も仕込みが終わる皆造の時期を迎えて、新酒需要はピークである。ポンバル太郎ではマフラーやコートを脱いだ客たちが、血色のいい顔で箸とグラスを動かしている。
「近海物の初ガツオはまだ早えが、年明けから東京湾でトラフグが揚がるようになってよう。春先のフグ鍋てぇのもオツなもんだ。どうでぇ、太郎さん。一度、うちで仕入れたトラフグを試しちゃみねえか? 中之島の師匠も、『江戸前のてっちりかいな!』ってビックリするにちげえねえよ」
すこぶる上機嫌な火野銀平が、時ならぬ東京湾のトラフグ景気に、両手を広げてサイズを自慢した。手に持つお銚子が右隣の右近龍二の鼻先をかすめるほど、銀平はすでに酔っている。トラフグは長さ60㎝、重さ5㎏の上物も築地に並び、仲卸は毎日が争奪戦だと銀平は口角から泡を飛ばした。
左隣で熱燗の盃を口にした平 仁兵衛が、銀平の手の幅に目を丸めた。
「そんなに大きいフグのヒレ酒を、ぜひ飲んでみたいものですねぇ」
アンコウ鍋を囲んでいるテーブル席の客たちも、平の声に頷いて
「東京湾のフグって、うまいのかな。一度、食ってみたいな。下関とかの本場の物より、安いんじゃないの?」
と聞えよがしな声を上げた。
だが、銀平の売り込みへ太郎は首を横に振った。
「いや、やっぱり玄界灘のトラフグじゃねえと、俺は使わねえ。米や野菜がその土地の滋養を吸っているのと同じように、逸品の魚介類は土地の海のエキスが入ってるからこそ、うめえんだ」
ガックリとうなだれる客たちに、大吟醸のグラスを手にする龍二が苦笑しながら言った。
「それに比べて、函館のイカ漁がダメらしいですね。あれって、対馬海流のせいとか、中国が東シナ海で一網打尽に獲ってるとか、まことしやかに言われてますけど、どうなってんですか? 銀平さん」
情報通の龍二だが、漁業の現場話には疎いらしい。トラフグの話題をすげかえられた銀平だが、不機嫌な表情は見せず、むしろ勢い込んで答えた。
「真偽のほどは、俺にも分からねえけどよぅ! 築地の連中も、イカ不足で頭が痛ぇんだ。北海道のスルメイカの水揚げは、ここんとこ30年ぶりの不漁でよ。価格も8割高で、キロ1,000円まで跳ね上がってんだ。平先生の家だって、晩飯にイカを見ねえんじゃねえですか?」
話を振られた平が、口惜しげに頷いた。
「我が家は、家内もイカ好きでしてねぇ。スーパーのイカが高いって、ぼやいてます。むき身の冷凍紋甲イカで、我慢していますよ……しかし、北海道の漁師さんも大変でしょうねぇ。先行き、イカ不足を補う北海道の海産物はあるんですか? 銀平さん」
「あるっちゃあ、あるんですが……値が張るわりに、人気のねぇ魚でね。ようやく回復の兆しが見えて来た、ニシンでさぁ。今年の漁期も3月25日で終わっちまうけど、去年よりも4割増しの水揚げだったそうでさぁ」
ニシンと聞いても、客席の面々はピンとこない表情だった。確かに、東京人が口にするのは、身欠きニシンをのっける熱い蕎麦ぐらいである。
ニシンに期待する声がない店内に、玄関の鳴子としゃがれた江戸言葉が響いた。
「人気がねえのはよう。今の東京人は、本当にうめえニシンを食ったことがねえからでぇ。だから、この厚田雄冬さんに、今年から葵屋は石狩湾で獲れた最高のニシンを納めてもらってんだ。太郎さん、あんたの店でも、一度使ってくんねえかい」
今は築地の元締めを引退して相談役に隠居した葵屋の伝兵衛が、褐色の頬をツヤ光らせている男を伴っていた。男は一目で雪焼けと分かるほどで、上等なダウンジャケットが似合っている。
固い表情でお辞儀する厚田に、道産子の純朴さが見え隠れしていた。
銀平は厚田の納めているニシンを知っているが、本人との対面は初めてらしく、腰を上げて丁寧にお辞儀を返した。
「伝兵衛さん。本当に美味しいニシンって、どうちがうんですか?」
厚田へ小さく会釈した龍二の問いに、伝兵衛は
「ふむ、今の若けぇ者は、本場のニシンを知らなぇだろうなぁ」
と答えると、目顔で厚田に答えを譲った。
厚田は、緊張をほぐすように一つ咳払いをして、道産子訛りで答えた。
「30㎝を超える7年物が、脂がのって一番うめえっす。そいづらは、もうずいぶん前から獲れなくなっでぇ、幻の魚になっちまってたのが、近頃、揚がるようになったんす。ピッカピカの生ニシンで、大きな白子を持ってるオスの大物が貴重なんす」
強い訛りに、テーブル席の客たちが失笑した。
「訛ったその声を聞いてると、ニシンってマズそうだな」
「ああ、やっぱ、俺たちの故郷の魚がうめえに決まってるよ」
彼らは瀬戸内産のサワラの塩焼きを肴に、愛媛県や香川県など四国の酒を飲み比べていた。
厚田は雪焼けした鼻梁を赤くして、口ごもった。真剣な面持ちで聞き入っていた銀平が、笑った客に向かって声を荒げた。
「何が、おかしいんでぇ! 漁師は板子一枚、下は地獄。しかも冬の石狩湾の漁ってなあ、危険と隣り合わせだ。港にゃ、雪がどっさりだし、氷点下の海に落っこちりゃイチコロなんでぇ!」
テーブル席の客が気まずげにうつむくと、店内は水を打ったように静まった。
張り詰めた空気の中、銀平の暴言に目で釘を刺した太郎は
「良かったら、石狩の地酒がありますよ」
と厚田をカウンター席に招きながら冷蔵ケースを開けた。
取り出した銘酒のレッテル“石狩挽歌”に、厚田の動きが止まった。
「……それ、石狩挽歌の本醸造じゃねえですか。私の好きな一本だ。元々は、ニシン漁の網元が飲んでいた晩酌酒なんすよ。東北から漁に出稼ぎに来ていたヤン衆が飲みたくても飲めなかった上等な酒だと、亡くなった曽祖父が自慢してねぇ。キレが良ぐって、すっきりとした辛口が越後の酒に似でるのは、蔵元の先祖が新潟県の出身だからだ。実は、その蔵元の先祖は、明治の頃にうちと一緒に北海道さ移民したんだ。今は小せぇ酒蔵だども、当時は大店だったそうで。今まで、頑張って営んできたのっす」
厚田の解説に、平や龍二だけでなく、北海道の地酒に興味なさげな客たちもレッテルへ目を向けた。
「確かに、北海道には10社を超える酒蔵があるけど、ほとんど本土から明治時代に移植した蔵元ですよね。石狩挽歌の杜氏や蔵人も、当然、新潟から引き連れて行ったわけだ」
得心顔の龍二に銀平が「おっ、なるほど」と相槌を打てば、隣の平が続けた。
「春になるとニシンは産卵のために、石狩湾へ大群で押し寄せました。それで一攫千金を狙った出稼ぎ漁師が江戸時代から昭和初期まで、越後や東北から陸続と乗り込み、ヤン衆と呼ばれました。彼らは網元の鰊御殿に寄宿し、番屋と呼ばれる漁師小屋でニシンの群れを待ち続けたわけです。稼いだ大金で、この石狩挽歌をお腹いっぱい飲みたかったんでしょうねぇ」
元教師の平がリアルに語ると、日本酒ツウの客たちは目の色を変えて、太郎へ石狩挽歌を注文した。
「けっ、ゲンキンなもんだぜぇ。だけど、石狩産のニシンがねえのは残念だな」
銀平が物欲しげにつぶやくと、厚田を誘ってカウンター席へ座る伝兵衛が「任しなときな」と太い腹を叩いた。言うが早いか、携帯電話で葵屋へ本場のニシンを手配する伝兵衛に、客席から歓声が上がった。
平が目尻をほころばせると、太郎は意を得たとばかりに厨房の竈へ火を点けた。
それぞれのあ・うんの呼吸を黙って目にしていた厚田は表情を和らげ、また道産子訛りを口にした。
「昔は冷蔵設備がねがったから、ヤン衆たちが獲っだニシンのほとんどは浜に揚げて、少しだげ食用の干物“身欠きニシン”にして、残りは大釜で炊いて魚油を搾り、その搾りかすを“ニシン粕”に加工したんす。ニシン粕は、日本海の北前船で西日本に運ばれ、愛媛県のミカンや徳島県の藍、香川県の綿栽培とかの高級肥料になったす。そんな上等の“干しか”てぇ肥料になるほど、美味しくて、うめえ魚なんすよ」
そして、大漁に沸いた浜辺でヤン衆たちの唄うソーラン節は干しかとともに伝わり、全国に知られる民謡に変わっていったと厚田は瞳を輝かせた。
「あっ! もしかして最近流行してる“よさこいソーラン”って、元々はニシンの干しかが全国へ普及したせいかも知れませんね。いやぁ、食の歴史って、やっぱり深くて面白いや」
龍二が嬉々として石狩挽歌を注文した時、肩越しに声が聞こえた。
「あのう……さっきは、失礼なこと言ってすみませんでした。実は俺の実家、愛媛県宇和島市の温州ミカン農家なんです。子どもの頃、祖父がニシンの干しかをミカン畑の肥料に使ってたのを、今のお話で思い出しました」
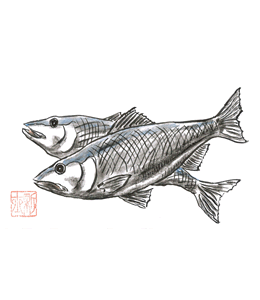
テーブル席の客の一人が厚田の後ろで、所在なさげに頭を掻いた。
照れ臭いのか、赤ら顔でほほ笑むだけの厚田の代わりに、銀平が声を発した。
「いいって、ことよう! 厚田さんのニシンは、この火野屋もじゃんじゃん納めるからよう。あんたたち、食ってくれよな! 葵の元締め、いっそのこと厚田さんのニシンとセットで、石狩挽歌の酒を築地場外で売れませんかねぇ。そうすりゃ、ヤン衆が飲んで食った当時の酒と肴のうまさを、江戸っ子に教えられるじゃねえですか!」
「銀平、乗ったぜ! 隠居した身の俺でよけりゃ、酒販免許も手を尽くしてみようじゃねえか」
その時、伝兵衛の声を追いかけるように、ニシンで満杯になった葵屋のトロ箱がポンバル太郎へ届いた。
息をすうっと吸い込んだ厚田の口から流れ出るソーラン節に、客席から拍手が沸き起こっていた。
