日比谷公園の蝉のざわめきが、ぎらつく夕陽にあおられていた。黄昏時は羽虫を追う蝙蝠の影も日増しに増え、ひと時の憧憬を都心に描いている。
ポンバル太郎の通りには打ち水がされて、暮れなずむ中、赤や青の花々が風に揺れている。
「表通りの朝顔、町の企画かよ。いい風景だな、懐かしいよ」
扉の鳴子を響かせて入って来た菱田祥一の声に、カウンター席の高野あすかが手にする酒器を嬉しそうに持ち上げた。
「えっ! まさか朝顔で酒を?」
菱田が目を擦るほど、花を型どった陶器のグラスはリアルだった。
あすかがほくそ笑むと、太郎が
「そんなわけ、ねえだろ。朝顔をデザインした冷酒の長盃だよ。あすかのお手製だとさ。平先生の指導がいいんだろうけど、なかなか上出来だろ」
太郎に褒められたあすかの顔が、赤い花びらのように火照った。
「天性の素質ですねぇ。私の工房の生徒さんも、舌を巻いてました」
ほろ酔いであすかの隣に座っている平 仁兵衛も、手放しで喜んだ。
「私、吟醸酒専用にラッパ型の陶器の盃が欲しかったの。ガラス製よりも陶器は口当たりが優しくて、お酒の芳香やキレをまろやかに感じるの」
あすかの酒食ジャーナリストらしいコメントに、テーブル席の女性たちが、
「そうなんだ! 知らなかったわ」
と物欲しげに朝顔の盃を見つめた。
そこへ、ひと足遅れで店に入って来た右近龍二が、あすかの解説をフォローした。
「全国新酒鑑評会の審査でも、鑑定官はグラスと蛇の目のきき猪口を使い分けるそうですよ。出品する蔵元さんは、その年の審査でどちらの酒器が使われるのか気にして、両方の器で味を試すそうです」
龍二は目ざとく朝顔盃を見つけると、あすかの隣に腰を下ろして
「そう言えば、今日は台東区“入谷(いりや)の朝顔市”でしょ」
と太郎から突き出しのオクラと湯葉のおろし和えを受け取った。頼んだ酒は、夏向けの生貯本醸造である。
龍二の声に、表情を変えた平がぬる燗の純米酒の盃を口に止めると、あすかは店の神棚にさりげなく目を止めた。
ハッとする菱田も、棚に置かれたハル子の遺影を見上げた。
「……そうだった。入谷の朝顔市は、ハルちゃんが好きな夏の歳時記だったよな」
それを初耳の龍二はしまったとばかりに口をつぐんだが、菱田に応えるかのように、玄関の鳴子が音を立てた。
カウンターの面々は押し黙ったまま動かないが、扉へ振り向いたテーブルの女性客から「わぁ! キレイ!」と嬌声が上がった。
彼女たちの瞳に、赤、青、紫の朝顔が咲きほころんでいた。
"入谷朝顔市"の帯を巻いた鉢植えを抱えているのは八百甚の誠司だったが、菱田の声を耳にしたのか、朝顔の向こうから気まずげに顔を覗かせた。
「すみません、太郎さん。俺ぁ、そうとは知らなかったもんで。俺のダチに、入谷の朝顔市で店を出してる花屋がいましてね。めっぽう日本酒好きな奴なんで、ポンバル太郎へ誘ったら、手土産にこの鉢を差し上げたいってんで……ちょいとマズかったなぁ」
太郎の顔色を窺う誠司の後ろで、髪を短く刈り上げた若い男が律儀なお辞儀をした。
「気にしねぇで、いいんだよ。ここん所、店の中に花っ気がなくて、殺風景だったからよ。むしろ、ありがてぇぐれえだ」
気遣い無用とばかり、太郎は龍二たちへも聞こえよがしに声を高くした。
遠慮がちにカウンター席の隅に座る誠司が
「こいつぁ、花政の咲田 薫です」
と、連れの男を紹介した。目鼻立ちのスマートな、優男風である。ジーンズの腰には、花切りハサミを差した粋な革サックをぶら下げていた。
「ほう、名前まで花屋らしいじゃないか」
「薫さんって、花の香りを思わせるし。それに、イケメンだし!」
太郎の言葉に菱田とあすかが気を取り直して、口を揃えた。ところが太郎は、さっきの態度と打って変り、咲田に目をみはった。
「花政ってえのは、深川にある老舗の花商だろ・・・・・・あんたのお祖父さんと思うんだが、彦一さんって名前じゃねえか?」
かすかに震えている太郎の口元に、あすかと龍二が顔を見合わせると、平がおもむろに口を開いた。
「驚きました。花政さんは、ハル子さんが通い詰めた店です。龍二君やあすかさんがここへ来るようになる前の話しですが、彦一さんは昔の江戸っ子気質でねぇ。老練な植木職人で、日本酒がお好きでした。花好きなハル子さんと意気投合して、花政に行くと長い時間、帰って来なかったですねぇ」
遠い目をして、平は続けた。朝顔市の顔役でもある彦一は、江戸時代の下町で朝顔が愛された理由をハル子に教えた。
中国では朝顔を"牽牛花(けんぎゅうばな)"と呼んだ。つまり七夕の祝い花で、織姫を意味する江戸っ子の色恋沙汰に持ってこいの花だった。それに朝顔の種は、江戸の医者から漢方薬に使われ、重宝したのだと自慢した。
龍二とあすかが感心すると、太郎は苦笑して朝顔盃に純米吟醸を注いだ。
「ハル子に『織姫は私で、彦星はまさに彦一さん。だから、あなたの出る幕はないわね』って腐されたよ」
ハル子を追憶する菱田も目を閉じたまま頷くと、つかの間、店内は静かになった。重たい空気を払ったのは、誠司の威勢のいい声だった。
「こりゃ、薫を連れて来たのは偶然と思えねぇや! びっくらこいちまうぜ!」
聞こえよがしな誠司の気配りを察したテーブル席の女性たちも
「朝顔が取り持つ縁って、ステキね」
と声を重ねた。
言葉の出ないあすかが、手元の朝顔盃を誠司の前の花々と見比べた。
ふと、盃に気づいた薫が大声を発して、盃に手を伸ばした。
「ああ! 彦一祖父ちゃんが描いた朝顔の盃に、ソックリだ! それ、どうしたんですか?」
「どうって、これは私が作ったの」
薫の語気にたじろぎながらも、あすかは朝顔盃を差し出した。
「そうですか・・・・・・今、思い出したもんで。彦一祖父ちゃんから、いつも来てたお馴染みの女性客から朝顔の盃の話しをされて、それを絵に描いたって聞いたんです」
薫は、その時の彦一の満面の笑みをハッキリ記憶に留めていると付け足し、朝顔盃に見入った。
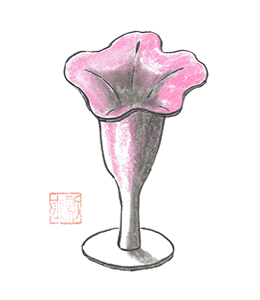 黙っているあすかと龍二に、太郎が神棚を見つめながら笑った。
黙っているあすかと龍二に、太郎が神棚を見つめながら笑った。
「あすかが朝顔盃を作った理由も、龍二の言った鑑評会の酒器のちがいも、ハル子はいつも気にしてたよ。おそらく、そんな話まで彦一さんに聞いてもらったんだろうな・・・・・・厚かましい奴だからよ」
薫が朝顔の盃を撫でながら、つぶやいた。
「あすかさんは、ハル子さんと同じ気持ちで、この盃を作られたんですね」
龍二と誠司があすかをちら見すると、恥じらうようにうつむいていた。
平が口に出さず、あすかに目顔でささやいた。
……今年の織姫は、あすかさんですねぇ。彦星は、もちろん、太郎さんですよ……
朝顔盃の酒に、あすかのほほえみが揺れていた。
