ロシアからのシベリア寒気団は日本海までせり出し、東北沿岸で鉛色の怒涛が牙をむいていると夕方の気象ニュースが伝えていた。雪をちらつかせる灰色の雲がクリスマスソングを響かせる都心を覆い、渋谷や新宿を歩くカップルは、このまま雪が続いて、イブを白一色にと期待している。
ポンバル太郎は、入社1年目の冬のボーナスで気の大きくなった若いグループ客が四合瓶のスパークリング大吟醸を3本注文し、やたらと賑やかだった。料理の頼み方も、高値の“和歌山産クエのお造り”や“福井県産ズワイガニの甲羅蒸し”など金に糸目をつけず、カウンター席に並ぶ平 甚兵衛と菱田祥一が「太郎さん、今夜はお稼ぎだね」と冷やかした。
メニューを選ぶ面々の凝った会話に、飲食系企業の社員かとテーブル席の年配客たちは顔をしかめ、定番のサバの煮つけをツマミに熱燗の盃をあおっていた。
確かに、羽振りのいい若者ばかりだが、お決まりの肴で晩酌を交わす常連オヤジ客は癪に障るだろうと、太郎も嬉しい半面、気にしている。その視線の隅で、カウンター席の端に座るロマンスグレーの頭と仕立ての良さげなスーツの男が、若いグループへ目を止めているのに気づいた。
「すみません。もう少し、静かにして頂けませんか。ほかのお客さんからの注文が、よく聞こえないんです」
ふいに、店奥の階段から飛んで来た声に、客席が振り向いた。ポンバル太郎の白文字を染め抜いた藍染めの半被を、太郎と面差しの似た剣がはおっていた。これから店の手伝いに入るところだった。背丈は、もう170㎝近くある。
少年らしからぬ落ち着いた物言いで、念を押すように目力を込める剣を、白髪の紳士は太郎の顔と見比べた。
若いグループは一瞬、声を止めたが、リーダーらしき長身の男が冷酒グラスを飲み干して答えた。
「俺たちだって、客だよ。しかも5人なんだから、かなり売り上げに貢献してんじゃん。ボクちゃんさ、ちょっとぐらいの声、大目に見ろよ。なあ、伊藤」
ほろ酔いの男がフンと鼻を鳴らせば、伊藤と呼ばれた隣の小太り男は剣の父親と読んだ太郎へ、皮肉っぽく催促した。
「ところで、さっき清水が注文した氷見の寒ブリのカマ焼きって、まだなの? この店の大将、口が達つわりには手が遅いよ。それにさ、もっと手っ取り早いB級グルメってないの? 焼きそばとか、コロッケとかさ。いくら手が込んでる肴でも、客を待たせちゃダメだよ。そこは、俺たちの会社が得意としてるところだよな」
伊藤や長身の清水のスーツの襟元には、全国展開する居酒屋チェーンの社章が光っていた。
やにさがった態度の二人に、菱田がいつになく声を荒げた。
「難癖つけやがって、エリート面しても、酔えばたちの悪い連中だな。与和瀬、早々に帰ってもらった方が、いいんじゃねえか」
菱田の苦言に、ロマンスグレーの紳士が情けなさげにうつむいた。こめかみに青筋の浮いている太郎が伊藤へ口を開きかけた時、玄関の鳴子が音を立てた。
「ほなら、わしが玉子焼きを作りまひょ!」
タータンチェックのハンチング帽を脱ぎながら、薄くなった白髪を掻き上げる中之島哲男の登場に、剣が気色ばんだ。
「マジ、いいタイミングで来るわ。神ってんじゃん、中之島の師匠!」
我に戻った太郎も、爆発しかけた怒りを制してくれた中之島の来店に胸の中で感謝した。
どっこいせとダミ声を吐き、大阪土産の“岩おこし”の紙袋を平の隣へ置き、コテコテの浪花オーラを発している中之島に、清水が立ち上がった。
「あのさぁ、玉子焼きなんて、いくら美味しいっても、見た目も形も同じだろ。上等そうに聞こえるダシ巻きにしたって、味は知れてんだよ」
清水の後ろに立った伊藤は背が低く、その分、声を張り上げた。
「俺はどうも、関西人って嫌いでさ。それなりの料理だって、大げさに、いかにも美味しいように誇張するでしょ? まるで、芸人のトークだよ。オヤジさんの玉子焼きも、そうじゃないの?」
腐す伊藤と合わせるように、清水も嘲笑した。だが、連れの何人かは「ちょっと言い過ぎだよ」とつぶやき、バツが悪そうに中之島へ小さく頭を下げた。
「いやいや! それは、あんさんが“明石の玉子焼き”を知らんからや。あの四角いダシ巻きとは、まったく別物ですわ。いわば、たこ焼きの玉子バージョン! けど、普通のたこ焼きと、焼き方も食べ方もちがう。つけるダシ取りも、ずっと難しい。う~む、上手いこと、言われへんなぁ……よっしゃ! わしが食わしたろやないか」
言うが早いか、中之島は太郎に厨房入りを頼むと、冷蔵ケースの真ダコを取り出した。そして割烹前掛けをすると、利尻昆布と本枯れ節でダシをとってくれと太郎へ頼み、タコをぶつ切りにした。平と菱田は久しぶりに中之島の玉子焼きを口にできると、肴と盃に動かす口を止めている。
中之島は数個の玉子をボールに割ると、泡立てないように掻き混ぜた。
変わらない包丁さばきと手際の良さに平や菱田が惚れ惚れした表情を見せると、ロマンスグレーの男も純米酒の盃を口元に止めて、小さく唸った。
カウンターの中へ入った剣が、中之島に、すり鉢とすりこぎ棒を差し出した。
太郎がダシを氷で冷ますと、中之島はとき玉子と合わせ、すり鉢に移し、小麦粉を少しだけ足した。
「懐かしいな。神戸支社にいた若い頃、よく食ったんだよ。上司に、説教されながらね」
中之島を関西料理の匠と知っている常連客の一人が喉を鳴らし、グラスの純米吟醸を口にした。
嬉々としてすりこぎ棒を動かす中之島に、清水のメンバーの一人が物欲しげに言った。
「玉子たっぷりのタコ焼きか。しかも、和風ダシで味がついてるなら、日本酒に合いそうだ!」
唾を呑んだメンバーが気まずげに清水の顔色を窺うと、中之島がほくそ笑んだ。
「お江戸の人は、明石の玉子焼きをあんまり知らんのやなぁ。まぁ、大阪のソースたこ焼きですら、この10年ぐらいで、ようやく都内に専門店ができたんやから、しゃあないか」
すり鉢をゴリゴリと混ぜる音の間に、ロマンスグレーの男が太い声を挟んだ。
「本場の明石の玉子焼きには、もう一つ、地元ならではの隠し味があった気がします」
「ほう! よう、ご存じで! 実は、焼く前に、ある物をタネに入れますねん」
中之島がもったいぶると、玉子焼きを知らずに恥をかいた伊藤が剣へ顎で指図した。
「もう、いいよ! 聞きたくも、食いたくもねえや。ボクちゃん、勘定をしてくれ。俺たち、もう帰るからさ」
「そうそう。うちの会社のメニューは誰が食っても満足する量と味付けだからな。隠し味なんて、安さと味で売るなら、いらないよ」
剣への悪態と中之島への無礼を腹に据えかねた太郎が言い返すよりも先に、ロマンスグレーの男はひときわ声を響かせた。
「今のが君の本心なら、その社章を外してくれないか。明日から、付けてもらわなくていい」
驚き顔を見合わせる平と菱田の前で、剣はロマンスグレーの男をまじまじと見つめた。怒り顔ではなく、落ち着き払った態度に、毅然とした怒りがこもっていた。
一瞬、声を失くしていた清水は
「お、おいおい。あんた、何、言ってんだよ? 社章、見間違えてない? うちの社長でもないのに、偉そうに言ってくれるじゃん」
と苦笑した。だが、ほかの面々はその笑いに合わすことなく、頬を引き攣らせていた。ロマンスグレーの男を凝視した伊藤が「ま、まさか……藤村会長」と洩らすと、清水の顔から血の気が引いた。
「どうやら、新入社員の方は、会長さんとお目にかかったことがあまりないのでしょうねぇ。いや、お気の毒です」
会長の藤村は、日頃は社員と顔を合わせない顧問的な存在と察した平の言葉に、ロマンスグレーの男は
「いやはや、面目ありません。私の不徳の致すところです」
と椅子から立ち上がり、カウンターへ両手を突いて太郎や中之島へ頭を下げた。ざわついていた清水たちが、水を打ったように静まった。
客席が注目する中、藤村は居酒屋チェーンを創業した当初の志を語った。
息子に社長を譲ってはいるが、近頃の商品開発は初心を忘れかけている。太郎や中之島のように、手作りへのこだわりと真心を伝えなければ、いくら安くて美味しくてもお客様には喜ばれないと、清水や伊藤へ苦言するでなく、自戒のように語った。
束の間、テーブル席のオヤジ客も藤村の話しぶりに聞き入っていた。
「まぁ、会長さん。もうそのへんで、よろしいんやおまへんか。せっかくの玉子焼きが、まずうなりまっせ……ところで、思い出しましたか? 玉子焼きの隠し味?」
張り詰めた空気が、中之島の大阪弁にほぐれた。藤村が記憶の糸をたどる間、太郎が厨房の奥から赤みがかった銅製のタコ焼き器を取り出し、コンロに乗せると、客席から「きれいな色!」「ピカピカじゃん!」と声が上がった。その穴へ、中之島はといた玉子とダシを合わせたタネを流し込んだ。
さらに、大ぶりのタコの切り身を入れようとした時、藤村が口を開いた。
「思い出した! 昔、何度か通った明石焼き屋の女将は、何かのダシを少しだけ足していた……野菜を煮込んだスープのような……ああ、思い出せない」
頭を抱える藤村の傍で、剣が「あっ! 分かった!」と叫んだが、中之島は口をつむったまま透明の計量カップに入った黄色いスープを手にした。そして清水と伊藤へ、カップをかざしながら訊いた。
「あんさんらは、分からんか? 飲食業のプロやったら、明石や淡路島あたりで美味しいスープが取れる野菜っちゅうたら、何じゃいな?」
首を捻る若者たちの目は、リーダーの清水に集まっていた。そこへ、藤村の視線も重なった。
はっとして顔を上げた清水が、伊藤の肩を叩いた。
「そうか! 淡路島の玉ネギだ。スープにすれば、甘味がたっぷり出るぜ」
「それに、玉子や和風ダシとの相性がいい!」
伊藤も自信ありげに、計量カップのスープを指さした。
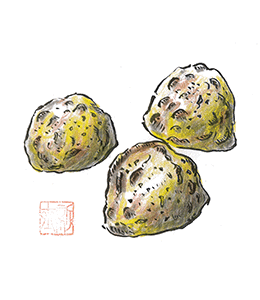 「ほう、図星です。新人さんだからって、侮っちゃいけませんねぇ」
「ほう、図星です。新人さんだからって、侮っちゃいけませんねぇ」
平が冷やかすと、清水と伊藤は藤村へ照れくさげな笑みを見せた。そこは、まだ若気の至りである。
「じゃあ、会長さんと新人さんで、仲良く、玉子焼きを焼いてみやすかい!?」
太郎の声掛けに、藤村が頷くと、尻込みしていた若いメンバーが「はい!」と素直な声を揃えた。
「何だよ、最初から、その態度と姿勢を見せりゃ、いいものをよ」
テーブル席のオヤジ客がなじると、中之島がイジッた。
「あんさんらかて、そんな生意気な頃がありましたやろ?」
「うへっ、お見通しだ!」
機嫌が良くなったオヤジたちの笑い声を、藤村と若者たちの作る玉子焼きの湯気が包んでいた。
