クリスマス直前で賑わう銀座や渋谷をよそに、アメ横は、歳末の大売り出しに向けたテント増設や目抜き通りの改修整備があわただしい。
職人たちの目が血走り始めた築地市場では、年末年始を日本で楽しもうとやって来る外国人客に、思わず「どいてくんな!」と威勢が飛んでいた。日本人は優しくて親切、安心して見学できると高をくくっていた外人たちは、縦横無尽に行き交うターレー車にひるんでいる。
場内にいる火野屋の銀平と八百甚の誠司はのっぴきならない忙しさで、この数日、ポンバル太郎には納品のみで、客として立ち寄れない。もっとも、年末の駆け込み忘年会で、店内は満席である。
太郎自身も、連夜の客の対応だけでなく、年始の“酒肴お節”の注文が殺到していた。
3年前から始めた日本酒ツウに向けたこだわりの酒の肴を3段の重箱へ詰めた商品で、“数の子の大吟醸酒粕漬け”や“鮭トバのにごり酒びたし”、“ブリのあら煮の梅酒煮こごり”など、15種類もの手の込んだ珍味を盛り込んでいる。ただし、限定20名の早い者勝ちのため、高野あすかや右近龍二など常連組が先を争って予約し、一般客の口には入りにくかった。
「大将! いつになったら、俺たちの番が回って来るんだよ?」
何人もの苦言が年末近くになると客席で聞こえ、そのたびに太郎は「申し訳ねえです」と頭を下げていた。
だが、今年は逆に、常連たちの機嫌が悪い。
客の不公平をなくそうと剣が提案したのは、一年ごとに常連客と一般客の優先を入れ替える方法だった。
「まぁ、もっともだがよう! 俺ぁ、年末ギリギリまでテンパって仕事して、唯一の正月のご褒美が、あの酒肴お節なんでぇ。誠司の野郎なんざ、今年初めて口にできるって、心底、楽しみにしてんだからよう。太郎さん、重箱1段だけでいいから、回してくんねえか」
スマホの向こうでへつらう銀平だったが、抜け駆けを拒否する剣に、太郎の口は重かった。
「ダメだ。おめえだけを目こぼしするてえのは、できねえ。あすかも龍二も、マリさんだって、渋々、我慢してんだよ」
厨房の中でスマホの声を殺す太郎に、自ら今年の注文を辞退した平 仁兵衛も、純米酒のぬる燗の盃を口元に止めて浮かない顔だった。
「……常連組のお正月は、暗澹としちゃいますねぇ。ありきたりなデパ地下のお節料理じゃ、物足りないですよ。何か、いい手はないものですかねぇ」
食材の冷蔵ケースを見つめて独りごちる平に、学校が冬休みに入って毎日手伝いをする剣が半ベソ気味に酌をした。
「僕、そんなに悪いことしたのかなぁ。銀平さんだけじゃなく、菱田さんや龍二さんにも、にらまれちゃったよ」
「まぁ、正しいのですけどねぇ。我々には、いささかショックですよ……うん? にらまれた……ですか。そうか! その手がありますねぇ。太郎さん、おからはありますか?」
平は盃を飲み干すや、太郎へ声を発した。
「おからって、豆腐のおからですか? 俺の賄い飯の残り物なら、少しありますけど」
不審げな太郎の返事に、平は冷蔵ケースの小鯛を指さして「ついでに、このチャリコもね」と珍しく出身地の石川県の方言を使った。
おからと小鯛にほころぶ平の目尻が、不思議そうな剣の表情を見つめた。
「剣君は、年賀の“にらみ鯛”って、知ってますか?」
「お正月に食べる尾頭付きの鯛のことかなぁ? 頭が付いてるから、にらんでるように見えるとかじゃないの?」
剣が曖昧な口を厨房へ投げると
「面目ねえですが、俺も、正確なことは知らねえです」
と太郎の答えもおぼつかない。すると、玄関の鳴子とともに、聞き慣れた右近龍二の声が聞こえた。とっさに、酒肴お節の件でバツが悪いのか、剣の顔色が変わった。
「四国の瀬戸内じゃ、塩釜料理にした尾頭付きが、にらみ鯛ですよ。僕の田舎の土佐じゃ、もっぱらカツオやマグロが主役ですけどね……だから、来年の正月は皿鉢料理で過ごします。太郎さんの酒肴おせちを土産にできないのは、残念だけど」
龍二のボヤキでますます落ち込みそうな剣を、平が庇うかのように答えた。
「実は、そこなんですよ。にらみ鯛も、全国にいろいろあるんですねぇ。当たり前なのは、塩焼きですが、私の故郷・石川県は「鯛のから蒸し」とも呼びます。金沢の郷土料理でして、鯛とおからを一緒に焼くのです。もともとはね、婚礼に出された料理で、嫁側が嫁入り道具と持参する祝い鯛を、婿側が調理してふるまいました」
おからには、子宝に恵まれるようギンナン、百合根、麻の実、きくらげなどをいっぱい入れ、その上にオスとメスの鯛を腹合せにして並べる。ただし、鯛をさばくのは、切腹を連想させないよう背開きにするのが、元の加賀藩の武家文化らしいところだと、平は長々と説いた。
龍二や剣だけでなく、客席からも感心する声が聞こえた。その中には「私、金沢出身です!」と手を挙げて、から蒸しを自慢する女性もいた。
厨房から出て来た太郎も、平がおからと小鯛を頼んだ理由を納得して、初耳のから蒸しについて訊いた。
「じゃあ、から蒸しって、おからに由来してるんですね? さっそく、試してみますよ」
小鯛をさばこうとする太郎に、玄関から九州弁が飛んだ。
「そうやなかよ。から蒸しは、唐の蒸し物たい。元々は、長崎に来た加賀藩のお侍しゃんが、卓袱料理の鯛のけんちん蒸しを覚えて、金沢へ帰ったとよ。それに、九州のにらみ鯛には、中華の甘酢餡かけみたいに、脂っこいのもあるたい」
カウンター席へ近づくや、太い尻を捻じ込む手越マリは、この後、自分の銀座のBARに行くと太郎へ前置きして、低アルコールの発泡純米酒を注文した。
「へぇ、中華風のにらみ鯛か。正月からコッテリしてるんだねぇ」
「だから、九州の甘い酒が合うんじゃない? マリさんの田舎の熊本赤酒なんて、味醂みたいだから、甘酢餡かけにピッタリじゃん!」
発泡酒の栓を抜く太郎と、声変わりの終わった剣が、そっくりな声音を重ねると、マリが嬉しそうにツッコミを入れた。
「これぇ! どうして、そこまで見抜けるたい? 剣ちゃん、赤酒ば、たっぷり味見したとね?」
「えっ……いやぁ、何となく、そんな気がしてさぁ」
とぼけ顔の剣をイジるマリに、テーブル席の酔った若い男が、自分の故郷は長崎で、まさに甘酢餡かけの鯛は正月に欠かさないと握手を求めた。
盛り上がる客席を剣が抑えにかかると、平が太郎へ言った。
「これで、から蒸し、塩釜焼き、甘酢餡かけです。実は、太郎さん。いろいろなにらみ鯛のお節を作ろうと思ったのです。それを、今年は常連客の酒肴にしてはどうかと、思いましてね……ただ、問題は誰が……」
と多忙な太郎へ遠慮して、口ごもりかけた時、玄関から冷えた師走の夜気がどっと入り込んだ。大きく開いた扉から、中之島哲男の大阪弁が響いた。
「そこは、わしの出番や! 平先生のたっての頼みなら、今年を締めくくる腕前をふるいまっせ! ついでに、わしの料理の介添えは、太郎さんやのうて、剣君や。来年からは、板場の手伝いも始めるそうやないか。今年の晦日は、きばって、にらみ鯛を作ってみよやないか」
いきなり助っ人を振られた剣は、呆気に取られている。中之島が料理の達人と知っている客からは、ヤンヤの拍手である。
中之島は口に指を当て、それを制した。そして、剣に大吟醸を一杯くれと頼むと、ぐっと冷酒グラスを飲み干して、しゃべり始めた。
「皆さん、それぞれの故郷に、お正月のにらみ鯛がありますな。仕上げ方も、味付けも、いろいろでっしゃろ。ほなら、にらみ鯛ちゅうのは、どこから来たのか。これを、知っておいて下さいな」
巨匠の中之島のウンチクが聞けると、常連だけでなく客席も静まった。
そもそも鯛は帝や公家といった貴人が口にした魚で、神へ捧げる贄(にえ)の下がり物だった。とりわけ、京の都は海から遠く、生魚は届かず、サバやニシンのような干物や塩漬け魚ばかり。しかし、冷え込む正月は、雪を詰めた木箱で運べば、どうにか宮中に鮮度を活かしたまま届けられた。そんな鯛を、すぐさま口にするのはもったいない。そこで、焼いて火を入れた鯛を神棚に飾り、惜しむように、にらむように数日間置いてから、うやうやしく頂く。これが古式豊かな、にらみ鯛の形だと説いた。
そこかしこからため息が洩れると、
「俺、今年はちゃんと、鯛の尾頭付きと日本酒で、お正月しよう」
「から蒸しって、美味しそう! 私、うちの家族に作ってみようかな」
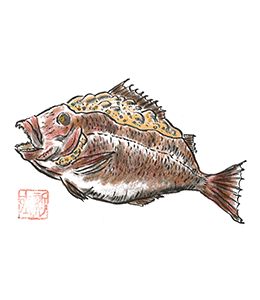 と、平のアイデアを実証するような声も聞こえた。
と、平のアイデアを実証するような声も聞こえた。
その時、玄関の鳴子が暴れて、酔った罵声が続いた。
「まったくよう! どうして、俺たち常連客が、後回しなんでぇ。ちょっとぐれえ、酒肴お節を作ってくれても、いいじゃねえかよう」
「あっしも、連れに食いに来なって自慢しちまって、引っ込みがつかねえんでさぁ。太郎さん、殺生な話ですぜ!」
最高のムードをぶち壊した火野銀平と青砥誠司に、全員の客から厳しい視線が注がれた。
「な、なんでぇ!? いきなり、にらみやがって!」
たじろぐ銀平の後ろに誠司が隠れると、剣が聞えよがしに言った。
「にらみ鯛じゃなくて、ほんと、にらみたい連中だよ」
大爆笑が巻き起こる中、太郎におからを詰められる小鯛が、賑わう師走の店内を見つめていた。
