冷やおろしの文字を揮毫したさまざまなレッテルが、ここ数日、ポンバル太郎の冷蔵ケースを占めている。
9月の半ばを過ぎ、その熟成した夏越しの酒が全国から届くようになると、太郎の店を蔵元の社員がチラホラと訪れるようになる。客たちが今年の自社の冷やおろしをどう評価するのか、どこの冷やおろしの人気が高いのかを彼らが調べて回るのは、この時期なのだ。
「うちの冷やおろし、どうですか? マスター」
二十代後半の営業マンらしき男が、短く刈り上げた頭でおもねりながら太郎に訊いた。
ぎこちなく名刺を出す手つきと作り笑いが、いかにも山出しの若者といった雰囲気だった。名刺にはある東北の蔵元名と、営業主任 横田正雄 の名があった。
だが厨房の太郎は肴の注文に追われて、生返事さえも返せない。傍では小学生の息子の剣が、テーブル席から聞いて回った注文書をまな板の脇へ黙々と貼り付けている。
そんな猫の手さえ借りたい状況なのだが、横田はあいかわらずカウンターの隅から厨房を覗き込み、一本調子で太郎に話しかけた。
空気を読めない田舎侍かとばかりに、カウンター席に座る火野銀平が横槍を入れた。
「おい、あんちゃんよ。答えの一つでも聞きたきゃ、まずは店の手伝いでもやったらどうなんでぇ。空いたグラスやお銚子ぐらい、引いて来れるだろう? この状況で、それぐらいの気配りがなきゃ、お世辞にもあんたの蔵の酒をうまいとは誰も言わねえぜ!」
たじろぐ横田は銀平とその隣に座っている平 仁兵衛の顔に視線を泳がせたが、平は素知らぬ顔で、ぬる燗にした冷やおろしを盃に注いでいた。
「あっ、は、はい……じゃあ、空いてる皿とかも見て回ります」
その時、カウンターの向こうから剣の甲高い声が飛んで来た。
「銀平さん、よけいなこと言わないでよ。勝手の解ってない人に手伝われると、かえって面倒だよ。この前だって銀平さんが運んで、グラスをいっぱい割っちゃったでしょ」
「な、な、なんでぇ、剣。ありゃお前、ちょっくら手元がすべっただけじゃねえか」
「あのさぁ、市場で魚をさばく手と、店で料理を運ぶ手は、まったく種類がちがうの!」
「こっ、この野郎! 言わせておけば……ったく、こましゃくれたガキになりやがって!」
と剣にやり込められて形無しの銀平の肩を、笑いを噛み殺している平がさすった。テーブル席の客たちも苦笑し、横田も所在なさげにつられ笑いをした。
それでも太郎は、表情ひとつ変えずに料理を作り続けている。動じない太郎に平が満足げに頷くと、またも唐突に剣の声が響いた。
「お待たせしました、横田さん。“じゃのめ”のきき猪口を持ってますか? まず、僕がいっしょに青冴えを見ます。テイスティングは、父の手が空いてから二人でやってください」
一瞬、店の中がしんと静まって、横田は鳩が豆鉄砲を食らったようにポカンとしていた。親を手伝う孝行息子で、ちょっとばかり生意気な小学生。それが酒の色を見るなど、横田は馬鹿にされているような気もした。
「ちょいと変わった家族だからなぁ……けどよ、剣の能力は本物だと思うぜ。あいつは酒の鬼だった母ちゃんの血を、しっかり引いてるからな」
冷やおろしの特別純米酒を飲みつつ問わず語る銀平に、横田がどぎまぎしながら、きき猪口を鞄から取り出した。
白い陶器の盃の底に青い線が二重に丸く描かれ、それが蛇の目に似ているので、“じゃのめ”と呼ぶが、その線の青さが冴えるかどうかで酒の良し悪しを見るのは、酒のプロの常識である。
しかし、剣は横田が手にするきき猪口に「あっ……」とつぶやいて、肩を落とした。
「あの、なにか……これ、大きさも酒匠仕様ですし、口当たりの部分も味を感じやすくするために薄くしてあるんです」
横田が自慢げにきき猪口を差し出すと、それと大きさ、色や形の変わらない猪口を剣が近づけた。
「でも、それ、ちがうんです。横田さんのきき猪口の底は、平たくなってます。“呑みきき用”だから、じゃのめの線が盛り上がってないでしょ。でも僕の“本きき猪口”は、窯で焼いてから線を1本ずつ手書きしてます。だから底の表面に凹凸ができて、線の輪郭がぼやけない。お酒の色を見るには、これが重要です」
「そ、そんな……これだって、充分でしょ」
呑みきき用と指摘されて恥をかいた横田は、これみよがしに客席へきき猪口を見せた。
すると、静かだった太郎がおもむろに口を開いた。
「そんな言いわけは、うちではやめてもらう。冷やおろしの評価や味を訊いたのは、あんたの方だろ。それに対して、プロとしてちゃんと答えるのが俺の流儀。だから横田さんも、酒のプロとしての基本を守ってくれ。悪いが日を改めて、本きき猪口を持って来なよ」
口調は毅然としていたが、太郎の目元はおだやかだった。その言葉を耳にしながら、銀平と平は言わずもがなといった顔で小さく頷いた。
唇を噛んでいた横田だったが、きき酒が中止になるや健気に店内を回っている剣を目にして「ふっ、かなわないや」とつぶやき、しだいに表情を和らげた。
そして、飲みきき猪口をしまって帰り支度をすると太郎へ振り向いた。
「あの、一つだけ、訊いてもいいですか? 剣君にきき猪口のこと、どう言って教えたのですか」
「俺からは、教えてねえよ。毎日、息子が洗い物を手伝ってるうちに、本きき猪口と呑みきき猪口の底のちがいに気づいたんだよ。そのちがいの理由を俺にしつこく訊くもんで、インターネットで調べろと教えた。それを調べた息子は、うちのお客さんに説いて楽しませるってわけだ」
太郎は、秋田県の冷やおろしの純米吟醸をテーブル席で説明している剣に、目を細めながら答えた。
客たちが剣に感心する声音が、癒されているかのように長い余韻を引いていた。
「本当に、驚いてばかりです……突拍子もないというか、常識はずれな居酒屋ですね」
ため息をつく横田に銀平がグラスを手渡し、冷やおろしを注いだ。
「まあ、一杯ぐらい飲んで帰りな……だけどよ。自分の常識に慣れすぎると、まちがったきき猪口を使っちまっても気づかない。そうだろ?」
片目をつぶる銀平に横田は笑みを浮かべて、グラスを飲み干した。
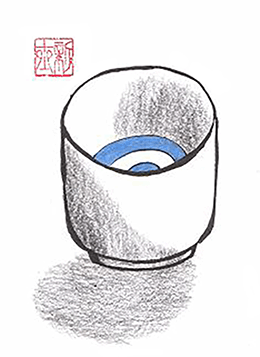
その横顔を見ながら、平が独りごちるように語った。
「仕事ってのは、いつも新しい発見や体験がなきゃ、おもしろくありませんねぇ。マンネリやルーティンは、人を成長させませんよ。日本酒も、これからはいろいろな変化や進化が必要な時代です。横田さん、大いに、常識はずれの蔵元マンになってください」
今度は、平からぬる燗の酒を勧められ、横田はカウンター席に腰を下ろした。
「それにしてもよ、今夜は、あすかがいなくって正解だぜ。あいつ、蔵元の娘だから、きき猪口どころか、横田さん、トッチメられてたぜ!」
ほろ酔いになった銀平の声に、間髪入れず、玄関先から返事が飛んで来た。
「あ~ら、ごめんあそばせ! もう、いるわよぉ」
無言に変わる銀平の傍で、剣が本きき猪口を手にしながら言った。
「銀平さん、やけに青ざめてるよ。きき猪口のじゃのめより、青いかも」
途端に、ポンバル太郎に大爆笑が巻き起こった。
