竈から藁焼きしたカツオの身が取り出され、バットの冷水をくぐらせるとジュジュンとうまそうな音がした。太郎はその身をすばやく取り出して、ステーキのようにぶ厚く切っていく。
鮮やかな赤身を真ん中に残しているカツオにカウンター席で舌なめずりしているのは右近 龍二と中之島 哲男で、その二人に火野 銀平がドヤ顔で言った。
「約束通り、最高のカツオを持って来たぜ。土佐の久礼から火野屋に直送された近海物で、ポンバル太郎と築地の料亭にしか届けてねえんだ」
それを耳にしたテーブル席のサラリーマンたちが、いっせいに厨房へ向かって目を凝らした。若い面々には限定品の産直カツオが刺激的だったようで、「食ってみたいな」とつぶやく声が聞こえた。
包丁をふるう太郎に、龍二が口を開いた。
「じゃあ太郎さん、僕が用意した物をそろそろお願いします」
「あいよ! さすが土佐っぽの龍ちゃんだ。高知じゃ、これをたたきの薬味に使うのか。しかし、仏手柑(ぶしゅかん)とはよく言ったもんだな。ほんと、仏様の手の形に似てるよなぁ」
冷蔵庫から太郎が取り出したのは、あたかも合掌している手のような形をした柑橘系の黄色い果実だった。龍二は、見た目の感じが美味しそうじゃないので仏手柑はほとんど国内に流通しておらず、高知県の一部と鹿児島県でしか作られていないと話した。
太郎は仏手柑の匂いをかぐと、細かく刻んだ。途端に、シトラスっぽい酸味のある匂いがほとばしり、もうたまらん!とばかりに、テーブル席の客たちが立ち上がって厨房を覗き込んだ。
「うん、うん、これぞ、土佐のカツオのたたきや。ほんなら、仕上げが肝心や!」
カツオのたたきに合わせる土佐の辛口本醸造を飲み始めた中之島は、手提げ袋の中から薄茶色い粉が入った小瓶を取り出した。
「わしが持って来たんは、高知県の藻塩(もじお)や。これで食う“塩たたき”が、ほんまの高知のカツオのたたきやで」
“藻塩”の言葉に銀平や龍二はニンマリとしたが、観衆の若い客たちは首をひねっている。太郎は、中之島から小瓶を受け取りながら若い客たちに言った。
「藻塩ってのは、海草のホンダワラを焼いて、その表面に浮いてくる塩なんだ。遥かな昔、すでに千年以上前から作られていた。万葉集にも書かれているよ。塩を作る技術がまだ無かった時代の原始的な塩だね」
土佐の皿鉢料理に使う大皿へ手際よく並べた厚いカツオの切り身の上に、太郎はスライスしたニンニク、細かく刻んだ浅葱と仏手柑をたっぷりとのせ、最後に藻塩を振りかけた。
そのボリューム感と食欲をそそる香りに、銀平と龍二だけでなく中之島も唾を呑み込んだ。
すると、三人の後ろから声がした。
「あの……僕たちが知ってる普通のカツオのたたきは、ポン酢で食べるじゃないですか。あれって、邪道なんですか?」
若者の一人が物欲しげな顔で、銀平が小皿に取ろうとしている塩たたきを見つめながら訊いた。
「おっ、おう。そう言われりゃ、そうだな……ええっと、龍二、どうなんだよ? お前、土佐の男だろ?」
もどかしげな口元の銀平が答えを振ると、太郎と中之島は呆れ顔で笑ったが、龍二は自信ありげに笑みをこぼした。
「カツオって青魚だから、足が速いんですよ。つまり、痛みやすい。だから時間が経って少し味が変わっても食べられるように、ポン酢や土佐酢を使うようになったんです。しかし、トレトレのカツオを食っていた土佐では、新鮮な旨味を引き出すために塩で食ったわけです」
龍二は答えながら、若者たちに塩たたきを盛った自分の皿を回して、ひと切れずつ勧めた。口に放り込んだ彼らは目を丸めて、何度も頷き、太郎に向かって親指を立てた。
そのようすに、ほろ酔いになった中之島が問わず語った。
「ええこっちゃな。今の若い子たちは、ほんまもんの日本の食文化に触れる機会が少ない。イタリアンやフレンチの料理、ワインはテレビや雑誌でいくらでも持てはやされとるが、どうも和食や日本酒は年寄りの食い物みたいに扱われてる。この塩たたきかて、どないしたら、もっと広まるやろかなぁ」
その声に太郎と銀平が無言で相槌を打った時、龍二がスッと立ち上がった。そして、店の中央に直立すると、スウッと息を吸い込んで、突然、歌い始めた。
♪ 言うたちいかんちゃ おらんくの池にゃ ♪
♪ 潮吹く魚が泳ぎより よさこい よさこい ♪
こぶしの返しが効いた、歌いこなした土佐の“よさこい節”だった。
唖然としているサラリーマン客たちと対照的に、中之島はうっとりとして聞き惚れ、銀平は「ふ~ん、やるじゃねえか」と嬉しげにつぶやいた。
「本物の塩たたきに、本場仕込みのよさこい節か。贅沢の極みだな……今夜は、俺も客になりたいよ」
太郎の言葉が終わると、店内の客席から拍手喝采が巻き起こった。数人の客たちは龍二に歩み寄って握手すると、太郎に塩たたきを注文した。
「なるほど、歌もごちそうにしてしまうかぁ……ほんまに、龍ちゃんは土佐のいごっそうやな。これでハチキンがおったら、完璧に、今夜は塩たたきの宴や」
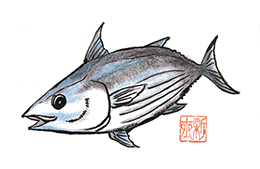
歌い終わって、テーブル席の客たちに塩たたきや土佐の酒文化を語る龍二に、中之島が目を細めながら言った。
「ハチキンって●●●●が八つある、男まさりな土佐の女のことでしょ? それはこの店じゃ難しいぜ、中之島の親父さん」
と銀平が返すと、いつの間にやって来たのか、手越マリの顔がにゅっと肩越しに現れた。
「土佐の女に負けない、肥後のハチキンがおるとよ!」
「か、勘弁してくれよ。マリさん」
塩たたきを喉に詰まらせながらマリを拝む銀平の両手が仏手柑のようで、太郎は思わず苦笑した。
