木枯らしを予感させるような冷たい風が、ポンバル太郎の玄関先で落ち葉のつむじを巻いている。その桜とイチョウの枯れ葉にふっとほほ笑む中之島 哲男は、一枚ずつ拾って羽織の袂に入れた。
「まいど~。えらい、寒うなってきよったなぁ」
かじかんだ手をすり合わせながら入って来た中之島は、カウンターの向こうにいる太郎に向かって、パッと右手を開いてから人差し指を立てた。
それは中之島が飛びきり燗のお銚子を頼む時のしぐさで、ようやくその季節が来たかと太郎は思った。
「今のサインは、なんですか。太郎さん?」
ぎこちない日本語の発音に、中之島がカウンター席の端っこへ視線を向けると、青い目と高い鼻筋を持つスーツ姿の外国人が座っていた。以前に菱田祥一が連れて来た、ニューヨークの雑誌記者をしているジョージだった。
ジョージを太郎から紹介された中之島は
「あんさんでっか。熱心に菊酒の話しを聞いて、クリサンミストとかいう名前を考えたんわ? あれは、なるほどでんなぁ。アメリカの皆さんにも、よう伝わる言葉でっしゃろ。よかったら、こっちへ来て、一緒に飲みまへんか?」
と目尻のしわをほころばせ、声をかけた。
するとジョージは中之島の大阪弁をほぼ理解できるようで、深いおじぎを返すと、隣に座ることをはばかった。
「ほう……アメリカの方やのに、今どきの日本人より礼儀を知ってはるなぁ。けど、遠慮せんでもよろしいで」
中之島がもう一度誘って手招きをすると、ジョージが答えた。
「でも、あなたのお隣の席は、おそらく常連のお客さんがいらっしゃる指定席でしょう。私は新参者ですから、端っこの席でいいです。お声をかけて頂いて、ありがとうございます」
ジョージは手にしている純米酒のグラスを置いて、中之島へていねいに手を合わせた。
感心して苦笑いを見せる中之島の背中越しに、ため息が聞こえた。いつの間にかやって来ている平 仁兵衛 が、赤いマフラーの上で嬉しげな顔を覗かせていた。
「ジョージさんですね? 日本文化を学んでいるらしいですねぇ。今夜は、楽しい酒になりそうだ・・・・・・それじゃあ中之島の師匠、私たちが席をあっちへ移しますか」
平は中之島の隣に座るのをやめて、ジョージの隣に腰を下ろしながら、簡単に自己紹介をした。
自ら歩み寄る平に、ジョージはどぎまぎとした顔つきになった。
「平さん、よろしいのですか? いつもの、お気に入りの席じゃなくても?」
「はい。今、はやりのオ・モ・テ・ナ・シをさせてもらいましょう。太郎さん、お近づきに一盃、私のオススメの生もと純米酒を、ぬる燗にしてジョージさんへお願いします」
太郎への平の注文に続いて、中之島の声がした。
「わしからは、丹波松茸の塩焼きを、天日塩だけで頼もうか」
二人に挟まれたジョージが顔を真っ赤にして照れると
「酒を飲んでも、アメリカ人にしては珍しく赤くならないジョージさんなのに……ようやくシャイな面を見せてくれましたね」
と太郎がほくそ笑んだ。
慣れた手つきで酌を受けるジョージは、平が陶芸家であることや、中之島が和食と酒の匠と知っておもむろに聞き込みを始めた。
「平さん、この酒は黄色いですね。それに、変わった匂いがある」
「ええ、それが本来の日本酒の姿です。その色や匂いが見た目に敬遠されることもあって、活性炭やマイクロフィルターを使って濾過している酒が多いのですが、最近は、本物志向で無濾過の日本酒も増えてきました。その酒の黄色を実感できるのは、器が白磁だからですよ」
「おう! これは白磁の盃ですか! 日本の小説によく出てきますね」
ジョージは、平の手造りの白磁盃をしげしげと見つめながら、いびつな形や手触りを楽しんでいた。
「気に入ってくださったなら、あなたへプレゼントします。それは、私が太郎さんに預けている物ですから」
平の言葉に興奮したジョージは、いきなり立ち上がってワンダフルを連発した。
その声の隙間から、焼き松茸の香りが漂ってきた。太郎がカウンターに置いた焼き松茸の皿には、川の流れのような天日塩と赤い葉っぱが盛りつけられていた。
「これは、もみじ狩りやなぁ」
「ええ、秋の渓流のイメージですよ」
中之島と太郎の会話に、ジョージが聞き返した。
「もみじ狩り? とは、なんですか?」
「日本人は季節ごとに、行楽へ出かける。もみじは秋を象徴するモチーフで、昔は山もみじを伐って、家へ持ち帰って楽しんだ。そやから、ハンティング=狩りっちゅうわけや」
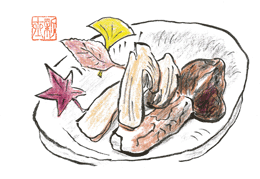
同じように春のお花見の季節には、野山の桜を盗んで売りさばく人たちが横行していた。それを「花盗人(はなぬすっと)」と呼んでいて、伝統芸能の狂言劇にもなっているのだと中之島は語った。
盃をペンに持ち替えて、せわしなくメモを取っているジョージを平の声が差し止めた。
「ジョージさん。そのような行為を、日本では“無粋(ぶすい)”と言うんです。私たちはジョージさんをもてなしているつもりですが、される側の心遣いも大切です。相手の気持ちを汲んで、ゆっくりと酒と料理とお話しを楽しむ。時を贅沢に使えば、お互いの表情が豊かになってきます。これも実は、“面成し(おもてなし)”と呼ぶのです」
「なるほど……オモテナシには、いろいろ深い意味があるのですね」
ウットリとした酔眼で白磁の盃と焼き松茸の皿を見つめるジョージの前へ、袂を探っていた中之島の指が、店先で拾った桜とイチョウの枯葉を皿の脇に乗せた。
一瞬にして、皿の彩りが鮮やかになった。
ジョージの顔に満面の笑みがこぼれると、平と中之島が嬉しげに口を合わせた。
「ようこそ、ポンバル太郎へ」
