太郎のしなやかな指先と菜箸が、半透明の切り身を古伊万里の小さな絵皿に美しく並べている。
白い身がフグの“てっさ”であることをテーブル席の客たちも察しているのか、カウンターの上に置かれる皿に目を細めて、思わず唾を飲み込んでいた。
その雰囲気を濁すかのように、荒い語気が響いた。
「日本酒は、吟醸造りでなきゃダメだ。あの香りが、三十年前に地酒ブームを作ったんだよ!」
「けっ、トウシローがうるせえんだよ。辛口の普通酒だって、戦後の日本を支えてきた功労者なんだ! それに、フグのひれ酒には欠かせねえんだよ!」
てっさの皿を前にして、二人の男がポンバル太郎のカウンター席で丁々発止を始めた。一人は剃り上げた頭から耳たぶまで赤くなっている火野銀平で、もう一人は、鼻髭を伸ばして長い髪を束ねている銀平のライバルの魚匠・勝浦昌吉(かつうら しょうきち)だった。
お互いの容姿だけでなく、Tシャツの背中の店ロゴも対照的で、それを目にする店内の客たちにも犬猿の仲と憶測できた。
昌吉が仕切っている築地の勝浦屋は火野屋としのぎを削る商売がたきで、太郎が築地市場をうろつけば、いい魚が入ったと話しを持ちかけ、新規の取引を虎視眈々と狙っていた。しかし、あからさまに売り込む商売や人気食材を独占するかのような仕入れ方が、太郎は気に入らなかった。
銀平と同い歳の昌吉は、実年齢よりも七、八歳は若く見え、その日の魚介類の優劣だけでなく、彼が築地市場の女主人たちにチヤホヤされるのも銀平にとって癪に障るのだった。
厨房から呆れ顔で出て来た太郎が、巻き舌で言った。
「おい、二人ともやめな。騒ぐなら、表に出てやってくんねえか。せっかくのフグが腐っちまわ」
「太郎さん、お言葉ですがね。火野屋のフグは腐っても、うちのは大丈夫ですよ。活きがちがいます。ところで今日のフグは、この前、ウチが推した北陸の養殖フグですね。でなきゃ、この値段では出せないでしょ?」
昌吉はカウンターの隅に立てかけられたホワイトボードのメニューを指さすと、やに下がった顔で冷酒グラスを傾けた。
その途端、激昂した銀平が椅子から腰を浮かせ、飲み干したひれ酒の入ったぐい呑みを荒っぽくカウンターに置いた。
「おう、昌吉! お互いの店や魚をとやかく言わねえってのは、俺たちの仁義じゃねえか!」
「銀平さん。そんな古臭いことを言ってるから、火野屋の客筋は減っちまうんですよ。お客さんは、いい物を求めてるんだ。天然物じゃなくても、そっくりで美味しく、しかも安い物。それが、勝浦屋のオススメ品なんだよ」
実際、“勝浦フグ”の商標を取って昌吉が販売しているそのふぐは、日本海の入り江で養殖され、近年、低価格で人気を呼んでいた。
昌吉は火照った頬に優越感を浮かべながら、てっさへ箸を伸ばした。すると柄皿が太郎の指に引っぱられ、箸先をかわした。
「昌吉さん、自信満々のところを悪いがな……このフグは火野屋が仕入れた、下関の天然物のトラフグだよ」
「えっ!? この、一人前1,200円が!? う~む、信じられないですねぇ……太郎さん、ちょっと味見だけでもさせてもらえませんか?」
目を丸めている昌吉が前のめりでてっさを覗き込むと、太郎はしばらく黙考して答えた。
「……その前に、こいつを味わってもらおうか」
太郎は冷酒グラスを二つ用意すると、冷蔵庫から二種類の瓶を取り出し、ラベルを隠しながら注いだ。いわゆるブラインドで昌吉にテイスティングをさせるつもりだと、銀平は悟った。
「どっちが、あんたの言う“吟醸造り”なのか、選んでみてくれ」
「ふっ、俺の味覚を試そうって腹ですか、いいですよ。これまで吟醸酒は、山ほど飲んでますから」
昌吉は、おしぼりで鼻髭と口まわりを拭ってから、すぼめた唇で息を吸い込むようにしてグラスを啜った。
きき酒をする軽やかな音を聴いた客たちは相当にツウの男だろうと評したが、太郎は無表情で昌吉の答えを待っていた。
いぶかしがる銀平を見下すように、昌吉が得意げに口を開いた。
「右側のグラスの酒です。理由は香りが華やかで、吟醸酒らしいカプロン系の芳香が強い。いわゆる洋梨などの果実に含まれる成分と、同じ香りですよ。おっと、これは太郎さんには、釈迦に説法でしたか」
昌吉の嫌味な言葉に、怒りをこらえる銀平が頬をひくつかせた。しかし、太郎はどこかほっとしたかのように失笑した。
「やはりな。似非は、似非しか判らないか。残念ながら、そいつは正真正銘の吟醸酒じゃねえ。ヤコマンを添加して、香りづけした吟醸もどきの酒だよ」
あっ! と顔色を変える銀平と対照的に
「ヤ、ヤコマン? って何ですか?」
と昌吉は的を得ない表情で眉をしかめた。
テーブル席の客たちも小首をかしげるようすに、太郎は銀平に視線を向け、おまえが解説しろと目で指図した。
「ヤコマンってのは、インスタントの吟醸香りみたいなもんだよ。その呼び名は、三人の開発者の姓から取っているらしい。吟醸酒が発酵中にできる芳しい香りを液体として集めて、それを別の酒に加えることで、吟醸酒らしく仕上げる方法だ」
仕上げてすぐのヤコマン入りの酒は、本物の吟醸造りと見分けがつきにくい。だが、栓を開いて数日経つと、酒の風味が変わり、香りと味のバランスがくずれる。だから吟醸もどきと呼ばれていると、銀平は右側のグラスの匂いを嗅ぎながら答えた。
それを聞きながら口元をゆがめる昌吉に、太郎が言った。
「あんたの推した養殖フグも、俺にすれば同じなんだよ。かすかに、飼料の匂いがするんだ。例えば、フグ食文化の強い大阪では、本物のトラフグは身をさばいてから一晩寝かせる。その理由は、天然物が持つ旨味がさらに熟成して美味しくなるからだ。ところが、おたくのフグは寝かせると雑味が浮いてきた。あれは、飼料のせいだろ?」
昌吉は長いため息をつくと、降参とばかりに破顔一笑した。
「つまり、このヤコマンと同じってことですね……でもね太郎さん、それを言えば、今は養殖マグロだって生まれる時代なんです。だからこそ、ヤコマンだってありなんでしょ?」
「ああ、そうだよ。俺はすべてを否定してるわけじゃない。ただ、ポンバル太郎が選ぶ品は、ちがうってことだけだ」
二人のやりとりに、銀平だけでなく店内の客たちも黙したままだった。グラスを置いたり、皿をつつく音だけが聞こえる中、昌吉がおもむろに立ち上がった。
「それじゃ私も、この店にいてはいけませんね……失礼します」
その時、銀平が声を発した。
「おっと、こいつも飲んでいってもらえねえか」
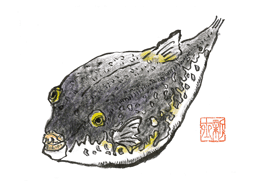
左側の本物のグラスを、銀平は昌吉に手渡した。そして、柔和な目元で言った。
「分かってんだよ……頑張ってんのはよ」
「ああ……いい経験、させてもらったさ」
昌吉は短く答え、一気にグラスを飲み干した。
勘定をして出て行く昌吉の背中を銀平が見つめていると、太郎が言った。
「ところでよ。お前も最近、勉強不足みてえだから、久々にヤコマンのきき酒してみっか? ただしハズしたら、伝票は倍づけだからな」
「ええ~、太郎さん、勘弁してよぉ」
ようやくポンバル太郎に、本物の吟醸酒の香りと酔客たちの笑い声が漂い始めた。
