上越新幹線を震わせるほどの轟音と窓を突き抜けるような閃光に、太郎だけでなくシートでうたた寝している出張帰りの客たちが飛び起きた。
「冬の稲妻や。いよいよ新潟に、本格的な冬がやって来よったで」
太郎の隣で平然と新潟のカップ地酒を傾けている中之島 哲男が、嬉しげにつぶやいた。さすがに越後の蔵元へ足しげく通っている中之島は、雪を呼ぶ大きな雷に慣れたものである。
彼のほころんだ目元は、荷物棚から爽やかな匂いを漂わせる四角い紙包みを見つめていた。それは、車両の天井につかえるほどの大きさだった。
「この匂い……都会の酒飲みには、たまらんやろうなぁ」
「ですねぇ。毎年のことながら、中之島の親っさんには感謝しかありません。お客さんも、今年はどこの酒蔵の酒林が吊るされるのか、心待ちにしてくれてます」
三日間の蔵元見学の旅に同行した太郎も爽やかな杉の香りを発しているその包みを見上げながら、明日の朝、さっそく店の神棚に新酒を供えて、ささやかな神事をしようと思っていた。
ポンバル太郎の玄関で看板代わりに吊るされている茶枯れた酒林は、12月になると真新しい緑色の玉に取り替えられる。それは毎年、中之島が肝煎りの蔵元へ依頼していた。
せっかくなら店で扱っている全国銘酒の蔵元に頼み、年ごとに変えれば、日本酒ツウの客たちは楽しいだろうと中之島が太郎に提案したのは三年前のことだった。
ポンバル太郎の店頭を飾るオブジェになってる酒林に、いったい何なのかと首を傾げる日本酒ビギナーの女性客が増え、小学生の剣から、そもそもは新酒ができたことを知らせる造り酒屋のサインと教えられ、さっそくフェイスブックやツイッターに剣とのツーショット写真を載せたりする。
そのようすを思い出す太郎が、今年は100社近くある新潟県の中で一番人気の蔵元にお願いできたことに感謝し合掌すると、前後の席に座る客たちも気持ちがいいとつぶやき、杉の香りに癒されていた。
すると、太郎と中之島の頭上から声がした。
「酒林だろ、あの包みは? おめぇさんたち、酒の関係者かね?」
今朝まで耳にしていた蔵人たちの訛りを髣髴とさせるような、やんわりとした新潟弁だった。
通路側を見上げると、白髪の男性が目じりをほころばせていた。人のよさげな笑顔にほんのり赤らんだ頬を目立たせる白い肌が、越後の親爺らしさを覗かせている。
「ええ、東京で居酒屋をやってます。この酒林は、うちの店先に吊るすんです」
太郎がその男の手を見ながら答えた時、同じ視線を重ねていた中之島がつぶやいた。
「おたくはん、麹をさわっとる手ですなぁ。お仕事は、酒の蔵人でっか?」
確かに、見たところ70歳を過ぎた高齢者ながら、手の甲の皴は少なく、ツヤツヤしていた。
「ああ、そんだ。もう、ずいぶんになるがねぇ……だども、今年の酒造りで現役はおしめえだ。俺は酒林も、いっぺえ作ったさぁ」
中之島と同じカップ地酒を手にして気分よさげに話す男が、一瞬、ふらついた。太郎は転びやしないかと、中之島の隣の空いている席を勧めた。
「いやいや、ありがとねぇ。ところでおめえさん、酒林は新酒ができた合図って言われてるだけどよ。昔は、蔵人にとっちゃ、おっかねえ物でもあったんだよ」
「ほう? ちゅうのは、なんででっか?」
中之島の濃い大阪弁に男が眉をしかめると、太郎が東京言葉でゆっくりと訳した。そのようすに、周囲のシートの客たちが笑いをもらした。
「俺は今年、80歳だ。19歳で酒造りに入ってから、昭和の頃が現役バリバリだったのさ。その頃の新潟には、もっといっぺえ酒蔵があってね。だけど設備は今みてえじゃなくて、冷蔵タンクなんてなかった。仕込みもタンクじゃなくて、杉桶を使ってたんだ。だから雑菌が多くて、酒が腐りやすかった」
男が言うには、当時は発酵や貯蔵用の冷蔵設備がなく、雪の寒さに頼る酒造りだった。しかも発酵をうながす酵母は蔵つきの野生酵母のため、品質が安定せず、気を抜けば酒が腐り、すっぱくなって売り物にならなかった。すると新酒ができず、酒林は作れない。
そうなると、数ある造り酒屋との競争に負け、一気に斜陽し、倒産の憂き目に遭う。そんな蔵元を何軒も見てきたと男は語った。
「だっけぇ、酒林を軒先に吊るせるってことは、蔵人にとっちゃ、今年もおまんまが食えるってことさ。町の居酒屋では、あの蔵元は酒林を吊るせたが、この蔵元は今年は吊るしてねえって噂が酒のツマミになったんだよ」
太郎も中之島も、すでに感心しきりの表情で聞き入っていた。周囲の乗客たちも、熱っぽい口調の男に注目し、キップの確認にやって来た車掌までも、鑑札の手を止めて男の声に耳を傾けた。
「なるほど……そう考えると、今も酒林の前で手を合わせる蔵人が多いのは、あながち儀礼的な作法じゃなくて、生活をかけたお祈りの習慣ですか」
問わず語る太郎に中之島も深く頷いて、カップ地酒を飲み干した男に、手持ちの新しい1個を手渡した。
男はお辞儀をしてそれを受け取ると、太郎に尋ねた。
「ところで、あめぇさん。きれいな緑色をした酒林が、時間が経って、だんだんと茶色くなってくっと、どうしてる?」
唐突な質問に、太郎はいかにも純朴な越後の親爺らしいと嬉しくなった。
「酒林の色が変わるたびに、季節のオススメ酒をお客さんに紹介しています。春なら少し熟した本生酒、夏には生貯蔵酒、秋は夏越しのひやおろしですね。もう、うちじゃお客さんの方が、酒林の色変わりに敏感で、うるさいですよ。特に、この人はね」
太郎が中之島を覗き込むと、いつになく真面目な顔で男に言った。
「酒林には、蔵人の魂がこもってるんやなぁ。あらためて、大事にせなあかん」
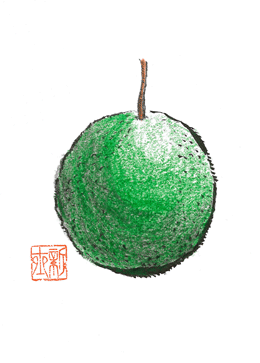
すると男は感慨深げな表情を浮かべて、席から立ち上がった。
「……そっかぁ。いや、安心した。酒林をそんたに使ってくれてるとは、ありがてぇ話だ。どうも、お邪魔したね。旦那さん、これ、ありがとねぇ」
カップ地酒を上着のポケットに入れた男は、深いお辞儀を返すと、列車の揺れに合わせてフラリフラリと自分の席へ戻って行った。
「一期一会ですね」
酒林の杉の匂いを吸い込んだ太郎が、つぶやいた。
「いや、越後一会(えちごいちえ)や」
中之島が、大阪のノリでダジャレを返した。
「うまい! この地酒もだけど!」
太郎の高い声に、静かになっていた車両の乗客たちが地酒カップを注文し始めた。
