すっかり日暮れが早まり、4時を回ったばかりの通りにネオンが瞬き始めている。その光彩の中、首をすくめて歩いて来たダウンジャケット姿の火野銀平が、ポンバル太郎の扉にかけた手を一瞬止めて小窓の中を覗き込んだ。
まだ開店前なのに、カウンター席には数人の男の背中が並んでいる。
グラスに口をつけては考え込み、言葉を交わしているのは中之島哲男と右近龍二、そして平 仁兵衛の隣にはニューヨークの雑誌記者 ジョージが座っている。
彼らの肩の隙間から数本の一升瓶が覗くと、銀平はいきなり顔を上気させ
「あっ! ちっ、ちくしょう。新酒を利いてやがる。おい、太郎さん! そりゃねえだろ。俺にも、今年の一番酒を利かせてくれよ!」
と乱暴に扉を開いた。
激しい音を立てる鳴子の木枡に、太郎がガックリと肩を落とした。と同時に、中之島が嬉しげな表情でカウンター越しに太郎の肩を数回叩いた。
「ほれ! わしの勝ちや! 太郎ちゃん、約束どおり純米大吟醸を一杯おごってんか。それにしてもさすがは銀ちゃん、思うツボにはまってくれよった」
「え……? なんだよ、思うツボってのは。ツボじゃなくて、その瓶を飲ませて欲しいんだよ!」
荒い鼻息の収まらない銀平は、赤ら顔で訴えた。
「はいはい、どうぞ。銀平さん、お好きなだけ飲めばよろしいですよ」
数本並ぶ一升瓶を勧める平の口元は、なんとなく含み笑いを浮かべている。それに気づいた龍二も、笑いをかみ殺しながら冷酒グラスを銀平に用意した。
「おっ、おう龍二。わかりゃいいんだよ、わかりゃ。どれ。この黒い瓶から飲んでみるか。おっと、どんな特定名称酒か、どんな酒造好適米を使ってるかは、まだ俺に教えるんじゃねえぞ!」
銀平はもったいぶった手つきで冷酒グラスを光にかざすと、それに黒い一升瓶を傾けた。
その瞬間、褐色の液体がグラスを色づけた。
「わっ、わわ! こりゃ、古酒じゃねえか。太郎さん、早とちりしてるよ。新酒の瓶とまちがってるぜ」
そのようすに笑いを堪えきれなくなったジョージが手を叩いて喜ぶと、太郎が長いため息を吐いて銀平に答えた。
「あのなぁ、早とちりはお前なんだよ。誰が利き酒をしてるって言った? ここにある一升瓶の中身は、全部、仕込み水なんだよ。まったく、中之島の親爺さんの罠にまんまとはまりやがって。きっとお前のことだから、新酒を利いてると思い込んでやっかむにちがいないって、酒を一杯賭けたんだよ!」
「えっ……そうなの。だ、だけどよ、こんなヒネた酒みたいな茶色い仕込み水なんて、見たことねえぞ」
銀平が思わず褐色のグラスに鼻を近づけて匂いをかぐと、わずかに鉄臭さが漂った。顔をしかめる銀平に、中之島が別のすりガラス瓶の水をグラスに注ぎながら言った。
「その茶色い水は、シングルモルトのウイスキーを仕込む井戸水や。アイルランドにあるウィスキー会社からジョージさんが知り合いを通じて、手に入れたんや。かなりの硬水やから、そんな色が付いてる。こっちの瓶の水は、フランスにいてはる平先生のお弟子さんが送ってくれた天然水や。これも少し硬水系で味がある。ほかには、メキシコのテキーラの仕込み水もあんでぇ」
銀平はようやく状況を理解できたらしく、
「なるほど……利き水か。だけど、どうしてこんなこと、やってんだよ?」
と戸惑いながら、中之島が教えたフランスの水を口に含んだ。やはりクセがあるのか、銀平は眉間にしわを寄せて飲み込んだ。
それを目にした龍二が、ようやく日本酒の仕込み水の瓶を差し出した。
「まずは硬水系をひと通り利いたら、それから日本酒の仕込み水を味見しようってわけです。つまり、日本酒を仕込む軟水の良さをあらためて勉強しようってのが今夜の主旨です。これを提案したのは、ジョージさんなんですよ。僕らは、普段から当たり前に日本の軟水を口にしていますが、アメリカはミネラル分の多い硬水のペットボトルがほとんどで、それに比べると日本の軟水はすばらしいそうです」「軟水か……なるほど、最近は海外でも日本は軟水の国だって評判らしいよな? でもジョージさんよぉ、硬水で育ったアメリカ人のあんたにとっちゃ、軟水って無味無臭で味もそっけもねえだろ? それを、どうしてすばらしいと言えるんだよ?」
銀平が質問を投げると、ジョージは一瞬口ごもったが、それをフォローするように太郎が二つの椀を銀平の前に差し出した。
太郎が両方の椀の蓋を取ると一方には脂分の浮いた金色がかったスープ、もう一方は透明のダシ汁が湯気を立ち昇らせていた。
「これが、ジョージさんの答えだ。銀平、どっちがうまいか味わってみろよ」
「ふうん、俺の舌を試そうって腹かよ。よし、いいだろう」
太郎の投げかけに、鼻先で笑う銀平が椀のダシを交互に口へ含むのを、ジョージはまばたきもせず見つめていた。
「右の椀だな。これ、利尻昆布のダシだろ。透明でまろやか。雑味のない上品な旨味と香りがいい。それに比べて、この鶏がらスープは押し味が弱い。がらの旨味が出ていなくて、薄いよ」
途端にジョージは拳を握ってガッツポーズを作ると、銀平にハイタッチを求めた。
「銀平さん、正解です! 鶏がらや牛の骨などの動物系の食材からダシを取るには、硬水がグッドです。硬水のカルシウム、マグネシウムが臭いやアクを引き出し、旨味だけを残します。 つまり硬水は、欧米の料理によく合う。だから、軟水で仕込んだそのスープは味が弱くて、美味しく感じません。しかし、昆布ダシは反対です。昆布の持っているグルタミン酸などの淡白な旨味を引き出し、これは日本料理の繊細な味つけにピッタリです。だから、そんな味と合わせる日本酒も、軟水系の仕込みが僕は好きです」
興奮して熱いヤンキーに戻っているジョージを、平が目でとがめながらカウンター席に座らせた。そして、日本酒の仕込み水を自作の瑠璃色の片口に満たして、茶道の利き茶に話しをふくらませた。
「日本の陶器も、軟水と縁が深いのです。酒器は当然ですが、茶器もそうです。かつて千利休を庇護した頃の豊臣秀吉は、全国から銘茶を集めていました。しかも、その各地の名水を沸かし、茶を点てさせた。名水のほとんどは軟水だったそうです。日本茶の繊細な味わいも、やはり軟水で仕込んでこそなのです」
含蓄のある平の話しに全員が静かにうなずいて、グラスの軟水を嬉しげに飲み干した。
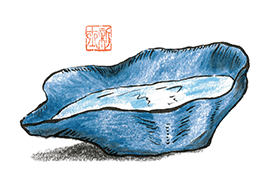
静まった店内に、龍二の声が響いた。
「思うんですが……日本人の奥ゆかしさや優しさ、細やかなもてなしの心は、ずっと軟水を飲み続けてきた民族だから引き出されたのかも知れませんね」
その言葉に、中之島や平が無言で目尻をほころばせると、銀平がつぶやいた。
「結局、美味しい所は、いつも龍二が持っていきやがる」
「はい! 根が軟弱な人間なので、旨味が出やすいのかも」
龍二が減らず口をきくと、銀平が切り返した。
「けっ、旨いってのは、甘いってことだからな! 忘れんなよ!」
カウンターを囲む男たちの笑顔が、片口の仕込み水に揺れていた。
