仕事始めとともにポンバル太郎のテーブル席は、連日、新年会の予約で埋まっていて、一見の客たちが店を覗くたび、舌打ちしてあきらめた。
カウンターで盃をあおっている右近龍二や平 仁兵衛は、ポンバル太郎の口コミが広がっていると笑顔になったが、今夜の太郎はテーブル席の皿、鉢、酒器選びに余念がない。
厨房では冬休みが終わったはずの剣も、真剣な顔つきで鍋の中をかき回している。甘い香りが漂う中、そのまなざしは太郎と瓜ふたつで、たった今カウンター席に並んだ高野あすかが感心して声をかけた。
「剣君、甘酒を造ってるね。しかもそれ、吟醸用の米麹を使ってるでしょ?」
「うん、ご名答……でもあすかさん、悪いけどちょっと黙ってて。今、一番大事なところなんだ。火を入れすぎると、まずくなっちゃうんだよ」
煮立ってきた甘酒とにらめっこしている剣に、あすかが参ったとばかりに舌を出した。その時、ふいに扉が開いて、太郎はハッと顔を上げた。人影が銀平と判かると、太郎は拍子抜けしたかのように鼻息をもらし、また視線と手先をテーブルの器へ戻した。
「な、なんでぇ、ため息とはご挨拶だな……太郎さん、やけに熱心じゃねえか? それに、何で甘酒なんか造ってんだ?」
相槌もしない太郎は、取り揃えた器を黙々と厨房へ運び始めた。すると、また扉が開いて、鳴子の木枡がカラコロと音を響かせた。甘酒の匂いは、菱田祥一の鼻先もくすぐった。
「今夜は、高校の同窓会を兼ねた新年会を俺が主催して、ここでやるんだよ。かつてのクラスメートがわんさかやって来るから、与和瀬も落ち着かないんだろ。甘酒を頼んだのは俺だけど、理由はまだ言えねえ」
菱田の思わせぶりな声に太郎が一瞬、動きを止めて、不審げに振り向いた。
「もう、教えてくれてもいいだろ? 俺が甘酒を仕込むのは、学生の頃以来だぜ」
その声と同時に玄関の鳴子の音が響き、アラフォーらしき男性や女性たちがドヤドヤと現れた。そして会話を止めた菱田がテーブル席に案内すると、クラスメイトたちは旧懐をあたため、思い出話に花を咲かせ始めた。
染めた髪の間から白い物を覗かせる女性やメタボ体型の男たちがさっそく太郎が調理する厨房の前に集まり、その手さばきやしつらいに目を丸めた。
「あのガサツだった与和瀬が料理人で、酒匠ってかよ。信じられないや。お前、学校じゃいつも早弁して、昼飯はとなりの席の女子……なんつったっけ? 思い出した、吉田だ。あいつに、弁当をもらってたじゃねえか?」
口々になじる面々に、大皿へふぐの刺身を盛り付けた太郎が苦笑いを返すと、龍二と平だけでなく、あすかも意外な顔をして太郎を見つめた。
菱田はテーブル席を一瞥して、小さく頷いた。その視線の先に、地味な海老茶色のセーターを着た小柄な女性が座っている。
「おっ? あれって、吉田喜美子じゃねえか。おーい、吉田さん。こっちへ来いよ」
クラスメイトの一人が声を発すると、太郎はどこに吉田喜美子がいるのかと店内を見回した。すると、そのセーター姿のしもぶくれた顔の女性がカウンターに近寄って来た。
「ぷっ、オタフクみてえだな」
銀平のつぶやきに、龍二も思わず噴出しそうになるのを堪えた。
「へぇ、吉田さん、ずいぶん太ったわねぇ。高校の頃は、ガリガリの痩せ子だったじゃないの」
かつてクラスで人気を集めていたらしい闊達そうな女性が喜美子に話しかけると、取り囲んでいる男たちも相槌を打った。
「ええ、おかげさまで。あの頃は、食べることにも事欠いた暮らしだったから……でも今は美味しい料理に囲まれてるから、とっても幸せよ」
喜美子は10年前に料理人と結婚し、都内で自然食の弁当屋を営んでいると答えた。普段は割烹前掛けをし、店長としてこま鼠のように走り回っていると言った。
目から鼻にかけて当時の面影を残している喜美子を前にして、太郎は追憶をたどった。
幼くして母を亡くし、父親の手一つで育った喜美子は、高校時代は父や兄弟の弁当も毎日作っていた。金をかけない弁当には大根の葉っぱや里芋のツルを使うなど無駄のない質素なおかずが入っていて、しばしば周囲の冷笑を誘った。
それでも、隣の席で腹をすかせている太郎に
「与和瀬君、これでよかったら半分食べて」
と喜美子は弁当箱のアルミの蓋によそってくれた。麦を混ぜたご飯と素朴なおかずながら、口の中に広がる滋味に太郎は驚き、遠慮するのも忘れて食べた。そのうち喜美子は太郎にドカ弁を作って来るようになり、弁当箱を洗って返そうとした太郎は母親に見つかり、こっぴどく叱られた。
社会人になった太郎は、口過ごしの乏しい痩せ細った喜美子から弁当をもらうなど、恥ずかしいどころか、人でなしに近かったと猛省した。
あれから20年あまり、後悔を引きずったままの太郎は同窓会の依頼を菱田から受けた時、喜美子と会えるなら謝ろうと決めていた。
学生時代の陰気でおとなしい喜美子からは想像もつかない変身に、同級生たちは顔を見合わせ感心すると、ふぐのてっさに舌つづみを打とうとテーブル席へ戻った。
カウンターの隅に腰かけた喜美子へ、太郎が唐突に頭を下げた。
「若気の至りだった。すまねえ! 吉田の弁当を食ったこと、心からお詫びするよ」
銀平と龍二がグラスの純米酒をゴクリと音を立てて呑み込むと、平は燗酒の盃を空けながらむせた。あすかも先付けをつまむ箸を止めて、目を丸くした。
すると喜美子はいたずらっぽい笑みを浮かべ、太郎を見つめた。
「ううん、あんなにつまらないお惣菜ばかりの弁当を残さず美味しそうに平らげてくれたこと、今も忘れていないもの。あの弁当に自信を持ったことで、自然食のお弁当屋を開けたの」
恥をしのぶ太郎から喜美子は視線を外すと、甘酒を青磁の片口に注いで客たちへ配り始めた剣に目尻をほころばせた。
「息子さんね、すぐに判ったわ。卒業する頃、お弁当のお礼にって、家に来て甘酒を造ってくれた時の与和瀬君の横顔によく似てる……今夜、甘酒が飲みたいって菱田君にお願いしたのは私なの。でも、息子さんの造ったこの甘酒は、あの時よりもぐっと美味しいね」
頬杖をついて剣を見つめる喜美子の言葉に、菱田はようやく太郎へ目で合図した。
太郎の脳裡で思い出が輪郭を帯び、セピア色に色づいた。
「そうだったな。俺、おふくろから、ひな祭りに『お弁当のお詫びに、甘酒を造ってあげなさい』と説教されて、造り方を教えてもらって吉田の家に行ったな」
喜美子も出された甘酒を口にしながら、懐かしげに答えた。
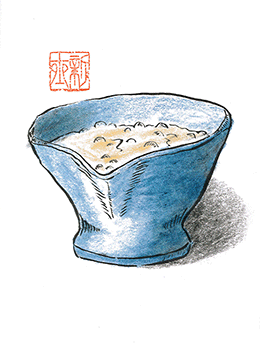 「とっても美味しかった。与和瀬君、私に詫びるような顔で『吉田の弁当、最高にうまかった!』って甘酒を注いでくれたの、忘れていないよ。あの言葉があったから、私は卒業してから弁当会社に就職し、そこで今の主人と知り合って、二人でお店を出すまでになれた」
「とっても美味しかった。与和瀬君、私に詫びるような顔で『吉田の弁当、最高にうまかった!』って甘酒を注いでくれたの、忘れていないよ。あの言葉があったから、私は卒業してから弁当会社に就職し、そこで今の主人と知り合って、二人でお店を出すまでになれた」
賑わうテーブル席と対照的に、カウンター席の面々は二人の会話に聞き入った。
「新年早々、いいお話ですねぇ。剣君、私たちにも、その甘酒をもらえますかな」
平が剣にほほ笑むと、あすかや銀平、龍二もほころんだ顔で相槌を打った。
満足げな太郎が剣にOKサインを出すと、喜美子が甘酒の盃をかざして言った。
「今度は、私が褒める番ね。剣君の甘酒、最高に美味しいわ! お父さんに負けない、ステキな酒匠になれるわよ」
照れ笑いをする剣の口元が太郎ソックリにほころぶと、店内のクラスメイトたちからも拍手が巻き起こっていた。
