昼下がりの晴れ間に舞い始めた風花が日暮れ時には灰色の雲を呼び、予想だにしない吹雪が都心を包んでいた。真っ赤な新年色にライトアップされているスカイツリーも白く霞んで、鴇色に移ろっている。
その姿を遠目にしながら駅へ向かう人波に逆らって、高野あすかはポンバル太郎の玄関に着いた。東北育ちで雪慣れた足取りのあすかの後ろには、ソフト帽に厚手のカシミアコートを着こなす老紳士がついて来ていた。
「いやぁ、たまげたなぁ。東京でも、こんなに降るもんだかぁ」
扉を開きざまにつぶやいた老紳士の東北訛りとその容姿のギャップに、カウンター席の右近龍二と平 仁兵衛が怪訝な顔を見合わせた。
厨房の太郎も包丁を持つ手を止めて、老紳士の顔を覗き込んだ。身なりは昔の映画で見た男優のような印象だったが、しわ深い頬の輪郭や高い鼻梁があすかによく似ていると思った。
「あら、皆さん。怖い顔してどうしたの? 私が初めて、年輩の男性と来たから? じゃあ、少しは私のこと、気にしてくれてるのかしら」
あすかがこれ見よがしに老紳士の肩にしなだれると、彼女のファンの剣がテーブル席を片づけながら、ふてくされた顔になった。
「これ、やめねえか……初めまして、私はあすかの父親で高野 伊衛門と申します。日頃は、娘がたいへんお世話になっているそうで。誠に、ありがとございます」
男が上等そうなグレーのソフト帽を脱ぎながら、常連客たちにおじぎをした。
「そ、そうなの!? じゃあ、相馬の蔵元さんだ!」
と龍二が声を高めると、あすかが一瞬、顔を曇らせた。
「あっ、いや。今はもう……元・蔵元です」
伊衛門の硬い表情に、太郎は彼の胸の内を思った。天災のせいとはいえ廃業した蔵元が日本酒の居酒屋に来るには、たとえ娘のいきつけの店でも恥を忍ぶ思いだろう。ましてや新酒のシーズンだけにそれを話題にしていいものかと、太郎は口から出かかった言葉を呑み込んだ。
「お名前の伊衛門は、おそらく代々、世襲されてますね。伝統のある御家柄でしょうな。まあ、まずは一献いかがですか。お父様は私と同年輩のようですから、あったかい燗でいきますか?」
湿りかけたその場の雰囲気を察した平が白磁のお銚子を手にすると、伊衛門は恐縮しながらカウンター席に座りかけた。すると、伊衛門のコートを脱がせるあすかがポケットに入っている紙包みに気づいた。
「お父さん、これは?」
「おおっ、忘れてた。もう、家にあっても宝の持ち腐れじゃから、ポンバル太郎さんに飾ってもらおうと思ってなぁ」
節くれ立った伊衛門の指先が古めかしい和紙を開くと、将棋の駒を大きくしたような木片が出てきた。そこには、今どきの揮毫ではないと判る墨字が書かれていて、脇から覗き込む剣が「酒株証文?」と迷いつつ読み上げると、つや光る木目に龍二や平も目を凝らした。
「はい、ご存じかな? 昔はこれを持ってないと、お酒を造れなかったのですよ」
「ふ~ん、じゃあ今の酒造免許みたいな物?」
「その通り! いやぁ、聞きしに勝る、賢いご子息さんじゃなぁ」
伊衛門が剣の両肩を抱きしめて喜ぶと、あすかは太郎に申し訳なさげな顔をした。そのまなざしに、太郎は相馬へ正月帰省していたあすかの変化を感じた。いつものあすかなら伊衛門の行為を盛り上げ、笑顔もふりまくはずだった。
「ちなみに、その酒株は何石分だったのですか?」
龍二が興味津々の面持ちで、伊衛門に席を勧めながら問いかけた。
「たった二百石ですよ。江戸時代の安政年間に相馬藩から頂戴した酒株ですが、うちは最期まで、それぐらいの酒造りでした。ですから、半仕舞い(はんじまい)です」
「なるほど、以前に飲ませて頂いた“蔵娘”が美味しいのは当然ですね!」
酒株をしげしげと見つめて得心する龍二の隣で、
「あの……お恥ずかしいながら、半仕舞いとは何ですかな?」
と平が白髪の頭を掻いた。
それにあすかが答えようとした時、伊衛門が手で制した。
「剣君は知ってますかな?」
伊衛門を蔵元とようやく悟った剣は、いささか緊張気味に口を開いた。
「ええっと……酒蔵では、毎日タンク1本の酒を仕込んで、順番に出来上がるのが理想的なんだけど、半仕舞いはそれを2日に1本で仕込むんだ。半仕舞はモロミの添・仲・留の仕事にじっくり時間をかけるので、そうなるの。とっても効率が悪いんだけど、丁寧に手造りする小さな蔵元には欠かせない方法だよ」
剣の健気な話しぶりに平は深く頷き、龍二が目尻をほころばせた。そのようすを真剣な表情で見入っていた伊衛門が、ひと言、つぶやいた。
「よかった。これで、安心して終われるべ」
その余韻の中で、伊衛門が酒株を剣の手に握らせた。剣はポカンと口を空け、平と龍二も沈黙した。
太郎は、あすかに察していた表情の翳りを伊衛門の言葉に確信した。
「近々、父は酒造免許の取り消しを申請します。それで、十代続いた高野酒造もお終いです」
どことなく震えているあすかの声音に、全員が高野酒造の復活はなくなったことを理解した。
「ようやく日本酒が海外に広がり始め、日本料理も世界遺産に認められたというのに……慙愧の念に耐えません。しかし、今も国内需要は減っていて、これからもさまざまな蔵元が窮地に陥る気がします。少子化、酒を飲まない若者、愛飲者の高齢化、前途多難ですが、ポンバル太郎さんのような酒場があれば、光明が見える。それに、あなたには剣君がいらっしゃる」
伊衛門は太郎の肩に手を置きながら、あきらめとも納得ともつかいない笑みをシミの多い頬に浮かべた。
太郎は、高野酒造がここ三代は女系一家で男児が生まれず、伊衛門もその父も養子縁組とあすかから聞いたのを思い出した。
あの大震災さえなければ、伊衛門はあすかに養子を迎え、蔵娘の再生を考えていたのではと太郎は斟酌した。
顔を曇らせる面々の中で、剣だけはもらった酒株に嬉々とした表情でガッツポーズを見せた。その姿にあすかが目頭を濡らすと、機転を利かせた龍二が口を開いた。
「あすかさん! いっそ、剣君のお嫁さんに立候補すればどう? 将来のポンバル太郎の女将だよ」
「はっ!? 龍二君、私いくつだと思ってんのよ! もう三十前よ!」
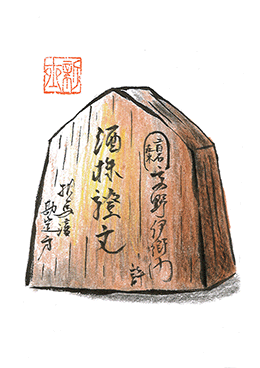
あすかの素っ頓狂な声音に、重苦しい空気が壊れた。苦笑する太郎や平の前で、剣が声を高めて、あすかの肩にもたれかかった。
「僕が年頃になるまで、待っててよ。あすかさんはお酒と一緒で、新酒よりちょっと熟した方が美味しいかも」
あすかを赤面させる剣の大人びた演技に
「さすが、太郎さんの息子だねぇ!」
と平や龍二が腹を抱えながら、盃を飲み干した。
「こっ、この野郎! 増せガキになりやがって!」
太郎がカウンター越しに怒鳴りつけると、剣は舌を出してあすかの背中に隠れた。
「やりますなぁ! こりゃまさに、お株を奪われましたな」
古めかしい酒株が若い剣の手の中で、ポンバル太郎に響く笑い声を聞いているようだった。
