「ハッピー ニュー イヤー! 太郎さん、おめでとうございます!」
ようやくアメリカから戻って来た雑誌記者のジョージが勢いよく扉を開けると、ポンバル太郎の壁に飾ってあるイワシと柊の魔よけを不思議そうに見つめた。
「このスットコどっこい! ジョージ、今日はもう節分だよ!」
聞き覚えのある声に、恵方巻きを齧っていた火野銀平は振り向きざまに叫んだが、ジョージの後ろについて来ている男を酔った目元で見るなり、語尾が尻すぼみになった。
オールバックの髪型に鋭い目つきの男は革のコート姿で、杉板張りの店内をしげしげと観察し、カウンターの隅に腰かけた。白人ではなく、典型的なアジア系の顔つきだった。
ジョージは男と流暢な英語を交わすと、太郎へ旬の煮物とそれに合う日本酒をみつくろって欲しいと頼んだ。ジョージらしくない大まかな注文に、太郎は男がこちらを試していると悟った。
男は視線を冷蔵ケースの酒に止めたまま、口元を動かしていた。酒のレッテルの銘柄をそらんじているようだった。
目が合ったジョージを銀平は首を小さく動かし、呼びつけた。
「お、おい。お前、アメリカから鬼を連れて来たんじゃねえだろうな?」
「ふふ、そうかも知れませんねぇ。でも、ちょっとオモシロイ人ですよ」
小鉢にイワシの梅煮、小皿にその骨せんべいを盛り付けた太郎は
「おめでとう、故郷のニューイヤーを楽しんで来たかい?」
とジョージに声をかけながら、男の冷酒グラスに和歌山の純米酒を注いで「どうぞ」と手を添えた。男の素性を確かめるような太郎の目を、銀平は察した。
男は大粒の梅を箸で裂くと、イワシと一緒につまみながら酒を口にした。
「南高梅か、懐かしいね。うむ……ダシの煮きりにも、この梅と純米酒を使っていて素晴らしい。ジョージ、これこそが日本のBARにあるべきロハスな肴なんだよ」
太郎が日本語を話す男に挨拶しかけると、赤ら顔の銀平が口を挟んだ。
「BARって、あんた。ここは日本酒のバル。つまり、居酒屋だよ。洋酒を並べてるBARと一緒にされちゃ、ちょいと困るなぁ」
怪訝な顔で男を一瞥していたテーブル席の客たちも、銀平の言葉に頷いていた。
すると、扉の鳴子の音とともにしゃがれた声が聞こえた。
「いや、銀平ちゃん。それは間違いやで。高森さんが言うてるのは、日本のBARには日本酒がなさすぎる。それに合う肴も、少ないっちゅうこっちゃ。その理由を、彼は誰よりも知ってるで」
突然、背後から聞こえた中之島 哲男の声に銀平とジョージが肩をビクつかせたが、太郎は男の豹変ぶりに驚かされた。
「おおっ、こ、これは中之島さん! どうして、ここにいてはりますの?」
突如、男が口走る大阪弁に店内の全員があんぐりとしていた。
「いやぁ、奇遇やな! お久しぶりでんなぁ。この与和瀬 太郎ちゃんは、私の親友でしてな。いわば、高森さんと同じ日本酒を愛する酒のプロでもありますわ。太郎ちゃん、こちらは伝説的バーテンダーで、肴や料理も達人の高森さん。今はニューヨークで日本食のレストランBARをやってて、今も大阪では業界人に親方と呼ばれてる人や」
紹介された高森はこわもての顔つきを崩して、照れ臭そうに太郎たちへ頭を下げた。はにかむような横顔に銀平がつぶやいた。
「な、なんでぇ。ジョージ、意外と素直な男じゃねえか。それにしても中之島の師匠が一目置くたぁ、どんな奴なんだよ?」
「だったら、本人から聞いてみませんか。そのつもりで、私はニューヨークからお連れしたのです」
ジョージの答えに、今度は太郎が口を差し込んだ。
「俺もぜひ、お願いしたいですね」
そして中之島が高森に小さく頷くと、テーブル席の客たちも口をつぐみ、聞き耳を立てた。
「私が渡米した20年前、アメリカにはいわゆる本物のバーテンダーがいなかった。つまり、イギリスの正統派BARやパブのような、カクテルのレシピやしつらえ、店の雰囲気にこだわるBARが少なかったのです。だから、本物志向の人たちは私の揃えた日本酒や日本らしいカクテル、和食をアレンジしたつまみを絶賛してくれました。でも反面、いつも聞かされたのは、日本国内を訪れても、日本酒を置くBARがないのはおかしいじゃないかという苦言でした」
高森は常連客のホームパーティにも招待されるほど有名になり、隣町からも彼のBARへセレブが殺到した。おかげで、彼がアメリカで経営するBARチェーンは成功したが、今も“世界から見た日本国内のBARの在り方”がずっと胸の中でくすぶり続けていると語った。
「わしも日本のBARは、変わらなんあかんと思う。日本料理が世界遺産に認定されたからってわけやない。そもそも日本酒と日本の肴は、世界から評価される繊細で丁寧な味を持ってる。だからこそ、BARには日本酒があるべきや」
中之島の言葉にジョージやテーブル席の客たちは感心して声を洩らし、あらためて高森の姿に魅入っていた。しかし、腕組みをしたままの銀平が口を開きかけた時、太郎がその肩に手を置いて、高森へ訊ねた。
「高森さん、アメリカのセレブが通うBARなら、日本酒や日本の肴は贅沢な嗜好品でしょう。だけど、日本人の酒と肴の文化には“始末”が付き物です。もったいない精神です。じゃあ、日本のBARで、あなたはどんな肴を用意しますか?」
水を撒いたように店内が静まると、中之島がつぶやいた。
「そう来ると、思うてたわ。太郎ちゃん、高森さんに厨房を使わせてもええか?」
「もちろん。そのつもりで訊きましたから。どうぞ、材料もお好きに使ってください」
太郎の誘いに口元をほころばせた高森は、駆け引きを楽しむかのようにコートとジャケットを脱いだ。そしてYシャツの腕を捲り上げると、厨房を物色し、さばいたばかりのタコの足の薄皮を手に取った。
「そりゃあ、捨てる物だぜ。もっとも、うちの火野屋から入れた極上の明石ダコだけどよ」
銀平はそう言って鼻で笑ったが、太郎は高森の目の付け所に口元を引きしめた。そのようすに、中之島が嬉しげな笑みを浮かべている。
「捨てる物? それは、私のレシピにはありません」
答えた高森は薄皮をまな板に広げるや、日本酒で洗い、柳刃で丁寧に削ぎ切りにした。そして、もみじおろしとアサツキを刻むと黄金色の酒粕酢で合え、鉢に盛り付けたタコの薄皮にまんべんなくふりかけた。
「下ごしらえで捨てる部位でも、こうすれば逸品の肴にできる。野菜のヘタもそうだが、世界が称賛する日本食の知恵と文化です。太郎さん、あなたのイワシの骨せんべいもそうだけど、私はそれが本当の“ロハス”だと考えます。うわべだけの自然食やレシピじゃなくて、もったいない精神こそが日本のロハス。これなら日本のBARにだって通用する、日本酒の肴じゃないでしょうか」
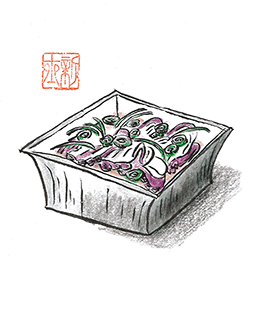
ぐうの音も出ない銀平の横で、太郎がため息混じりに答えた。
「まだまだ、俺は甘いですね。日本人ですら、タコの美味しさを忘れていた珍味だ。さしずめ、うちでは“ロ和ス”ってメニューにしましょうか」
「ありがとう、いい響きですね。太郎さん、近いうちにニューヨークの店に遊びに来ませんか?」
高森が声をかけると、太郎は首を横にふった。
「いや、“ロ和ス”のレシピは僕なりに考えてみたいので時間がかかりそうです。でも、いつか高森さんが開くだろう日本のBARで、一緒に日本酒を傾けたいですね」
太郎の断りに隠された敬意に高森がほほ笑むと、中之島が言った。
「親方、また一人、ええ弟子がでけましたな」
すると、いつの間にかタコの薄皮を食べているジョージが感動して叫んだ。
「これはうまい! やっぱり、ハッピーニューイヤーです!」
「だから、節分だって言ってんだろ!」
銀平のツッコミに、店内の誰もが笑い声を上げていた。
