ポンバル太郎の新酒メニューに無濾過生の純米大吟醸や大吟醸がひしめく頃になり、客たちの間では、気の早いことに全国新酒鑑評会の受賞蔵が予想されていた。
太郎はそんな連中に意中の蔵元を訊かれると、きまって答えをはぐらかした。
今夜もテーブル席では日本酒ツウらしきサラリーマンの上司が、今時分に搾った最高の大吟醸をそのまましばらく寝かせて、五月に出品するのだと部下に吹聴している。でも、そのままではなく、いくつかのタンクの酒をブレンドするのだと右近龍二はカウンター席の隅でほくそ笑んでいる。
「そろそろ新酒の仕込みシーズンは、峠を越えましたねぇ。蔵元さんも鑑評会の出品酒ができれば、胸を撫で下ろすことでしょう」
テーブル席の賑わいに目をやる平 仁兵衛が冷酒グラスを傾けながら、隣の龍二に問わず語った。その酒は、昨年初めて飲んで大いに気に入った広島の小さな蔵元の中汲み純米大吟醸で、上槽を待ち焦がれていた平は上機嫌である。
ただ、銘柄の「貴志子(きしこ)」の意味は、平だけでなく、太郎も解せないままでいた。
「平先生、確かに出品酒が完成すれば杜氏の肩の荷は下りますけど、蔵人がほっとするのは甑倒しを済ませてからですよ」
なにげなく答えた龍二に、一瞬、平は髭を舐めながら目を泳がせた。それは酔った平が困った時に見せるしぐさだった。
「あの、龍二さん。甑倒しってのは何ですか?」
「えっ、先生ご存知なかったんですか。これは失礼しました。まぁ、専門的な用語ですし、知らなくってもしかたないですよ。甑ってのは米を蒸す杉の桶っていうか、最近はアルミニウム製が主流ですが、つまり蒸籠みたいな物で……」
しかし甑の文字をカウンターに指先で書いてみせる龍二にしても、簡潔な説明は難しいのか言いよどんだ。すると甑倒しの言葉に、カウンター席の真ん中で生もと純米酒のお銚子を傾けていた二人の男が同時に頭をもたげた。
どちらも初めての客らしく、一人は細面の華奢な若者で聡明そうな面差しだった。その左側に座るのは、がっちりした体躯の四十がらみの男だった。二人はとってつけたような揃いの紺白の背広姿で、平と視線を合わせるとおっとりした訛り言葉をしゃべった。
「甑倒しは、今年の酒の仕込みが無事に、首尾よく終わったことを感謝する神事じゃけぇ。酒米を蒸す甑を釜からはずして、横に倒すっちゅう意味です」
「つまり、蒸し米の仕事納めちゅうことです。最終の麹米と掛け米ですけぇ、後はモロミが発酵したら搾るだけ。じゃけん、俺たちの肝心な仕事が、ほぼ終わったっちゅうお祝い事です」
その口調だけでなく、目鼻立ちが瓜ふたつの二人に、龍二と平はキョトンとしている。お国自慢のテレビ番組で耳にしたことのある訛り言葉に厨房から出てきた太郎が気づいた途端、玄関から声が飛んで来た。
「あんたたち、広島の人だろ。うちが牡蠣を仕入れている、広島の漁師にそっくりだぜ。それに、今の甑倒しの話しからすると、二人とも蔵人じゃねえの?」
唐突にかけられた銀平の声に二人はどぎまぎしつつも、すぐさま明るい表情で答えた。
「はい、安芸津(あきつ)の者ですけぇ。東京におもしろい日本酒のバルがあるっちゅうて、中之島さんから聞いて来ました。私は、そっちのお客さんが飲んでいる貴志子を造った杜氏で、岡野 光ちゅう者です」
年配の男が平に向かってはにかみながら会釈すると、若い男も遠慮気味に挨拶を続けた。
「俺は、麹担当の岡野 香です。俺も兄貴も同じ蔵で働いてますが、いつか金賞が獲りたくて……じゃったら、その前にここへ来て、ツウのお客さんが望んでいるのは何なのかを勉強しろと、中之島のオヤッさんにハッパをかけられました。どうぞよろしゅう、お願いします」
貴志子の造り手との偶然の出会いに顔を見合わせる平と太郎へ、岡野兄弟は広島酒の展示会に参加するため、ここ数日間上京していると言った。
垢抜けない雰囲気の二人だったが、職人然とした人となりに銀平はまんざらでもない表情で頷き、太郎に視線を向けた。
「さすが、中之島の師匠は顔が広いねぇ。それに、光さんと香さんって名前も吟醸酒みたいで、いいじゃねえか。太郎さん、さっきの甑の話し。龍二もいいかげんだったし、岡野さんたちにあらためて教えてもらおうじゃないの」
「なるほど、それは妙案です。しかし甑は珍しい字ですね。今はほとんど使わないし、見かけもしませんが、そもそもはどんな語源があるのですかな?」
平の声に、テーブル席の顔見知りの日本酒ツウたちも頷いていた。
「なるほど、中之島さんがおもしろい店っちゅうのは、こういうことか。こりゃ、ワクワクしてきたのう」
兄の光はそう答えながら弟の香に目配せをして、返事を譲った。それを待っていたかのように香が立ち上がった。
「甑は何の変哲もない杉桶に見えるけど、遥かな時代の先人の知恵の結晶ですけん。古代の日本人は、野生の米を生で食べてました。つまり、強飯(こわいい)です。そして稲作が広がった弥生時代には、それを土器で蒸して食べることに気づいた。土器の底に湯気を通す小さい穴をぎょうさん開けて、鉄の釜の上に置いたんです。これが、今の甑の原型です」
香は、米にまんべんなく蒸気が行きわたらなければ味にムラができることを古代人は知っていたと述べ、それは自分たちが造る麹米にも欠かせない技術で、バラつきのない蒸し上りが麹米の品質を高めるのだと説いた。
「つまり麹の菌が、均等に米粒へ破精(はぜ)込むわけだ。結果的に、上質の酒ができる確率は上がる」
太郎がニンマリとして言葉を付け加えると、光も拍手をして立ち上がった。そして平の席に歩み寄ると、カウンターに置かれた貴志子の一升瓶を手に取った。
「平さん、でしたのう。この酒の名前、さかさまから呼んじゃってつかあさい」
「ふむ……こ・し・き。おおっ、そうだったか! いやぁ、上から読むことにこだわりすぎて、ちっとも気づかなかった」
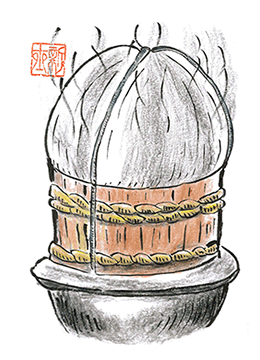
手を打って平が喜ぶと、龍二と銀平が苦笑いを浮かべながら声を揃えた。
「それならそうと、レッテルに意図を書けよ~」
「いえ、意味不明なこの銘柄の由来を飲んでくだすったお客さんが謎解きしてくれることも、俺たちの幸せじゃけぇ。それに、いわくありげな女性のようで、必ず記憶に残ると思うんじゃ」
光はこの名前を発想したのは自分で、甑から生まれる上質の蒸し米は美酒の子どもなのだと言った。
「貴い志の子どもか……あんたら兄弟の日本酒への思い、しっかりと味わせてもらうよ」
太郎が冷酒グラスをおもむろに差し出すと、光が嬉しげに一升瓶を傾けた。
「これも、もう一つの甑倒しですねぇ」
平の言葉に、岡野兄弟の話しに聞き入っていたツウの客たちが「うまい!」と声を揃えた。
