先週末に新酒の搾りが完了する“皆造(かいぞう)”を終えたばかりの蔵元を見学した火野銀平が、土産に買って帰った限定販売の純米吟醸をカウンター席の面々へ自慢げにふるまっている。
そのグラスを口に含んだ平 仁兵衛が隣に座る能登杜氏の矢口と満足げに頷き合い、高野あすかと右近龍二は搾り立ての炭酸ガスが残る酒と、太郎が自家燻製したカマンヴェールチーズを肴にまったりと寛いでいる。
ポンバル太郎の常連たちの間でも知る人ぞ知る蔵元の酒だけに、テーブル席の一見客たちが物欲しげな視線を向けていた。
「ところで、この蔵元ってどれくらいの規模なんですか? 名前は聞いてますけど、僕はまだ行ったことがないんですよ」
裏レッテルの精米歩合や日本酒度を確かめる右近龍二が、目を細めながら銀平に訊ねた。
「へぇ、珍しいじゃねえか。龍二のこったから、もう見学してると思ってたぜ。蔵元に聞いたところじゃ、ほんの五百石。だから、家内工業だな。実際、社長の長男が杜氏で、次男が営業部長だったよ。経理や店頭の販売は奥さんと息子の嫁たちが受け持ってて、家族総出の蔵元だよ」
と悦に入って答えた銀平が、一瞬、語末を呑み込んであすかの顔色を窺った。平成25年から完全に廃業したあすかの実家のことをおもんぱかってかと太郎が目元をやわらげると、同じように平や矢口も口元に微笑を浮かべていた。
だが、あすかはそんな気遣いなど知らぬそぶりで
「そうなんだ。じゃあ、かつての私の実家と同じぐらいかなぁ。ねえ、銀平さん? スマホで蔵の写真とか、撮った?」
と一升瓶を傾ける銀平の脇腹を肘で小突いた。
「わっ、わわ! バカ野郎、こぼしちまうじゃねえか。ちょっ、ちょっと待てよ」
一升瓶を太郎に預けてあすかの隣に座った銀平は、意外と素直にスマートフォンを取り出した。いつにない二人のそんな間合いを龍二が茶化そうとしたとたん、あすかが声を上げた。
「あっ、懐かしい! これ、あみだ車じゃない。うちにも、昔あったんだよ~。小さい頃、職人さんが私を籠に入れて、蔵の二階と一階を上げ下げして遊んでくれたの」
「うへ~! おっかねえ遊びをしてやがる。やっぱり相馬生まれだけに、お前、じゃじゃ馬娘かよ」
嬉々として画面を覗き込むあすかに銀平があきれると、あみだ車の言葉を耳にした矢口が席から立ち上がり、二人の後ろからスマートフォンを覗き込んだ。画面には、飴色をした酒蔵の太い梁にぶら下がる、木製の八角形をした滑車があった。
「これは、よく手入れしてますねぇ。ほら、木目に柿渋を塗って磨き込んでいるから、こんな色になるんですよ。柿渋には、防腐効果がありますからね。でも、今は実際に使ってるんじゃなくて、見学に来たお客さんたちに雰囲気を楽しんでもらうため残しているのでしょう」
「さすが、矢口杜氏。その通りですよ。実際、大勢の見学者が来る時はロープをかけて、使っていた当時を再現するってわけ。この蔵も昔は、仕込みの段取りによって二十石の木桶を引っ張り上げたり、下ろしたりしてたらしいですよ」
唾を飛ばして語る銀平の横で、あすかは飽きもせずあみだ車を凝視している。そのようすがちょっとばかり引っかかる龍二の耳に、テーブル席の客たちの声が聞こえた。
「二十石ってことは、一升瓶だと200本分かよ! つまり360リットル入りの桶か!? す、すげえ」
「あのう……このあみだ車って、いつ頃まで使われてたんですか?」
矢口を蔵人と見て取った若い男が、スマートフォンを手にして訊ねた。あみだ車の画像をwebで検索していたようだった。すると、太郎から二杯目の酒を注がれた平が口を開いた。
「それは私も今、ふと思ったのですよ。おそらく、ほとんどの蔵元では昭和の戦後まで使われてたのではないですか。戦中には軍需用に金属が没収されましたから、鉄製の滑車やチェーンなんて一番最初に無くなったはずですよ」
「そうです。でも、平先生。能登のような地方の小さな蔵元には、昭和30年代になってもなかなか新しい設備や道具は普及しなかったのです。すでに引退した私の師匠は、今年88歳。戦後の酒造りに頑張った能登杜氏ですが、当時はまだ琺瑯タンクも無くて、杉の木桶で仕込んでいたそうです。むろん、あみだ車も使っていました」
平と矢口の問答に聞き入る銀平が頷きながら指を鳴らすと、質問した男と連れの客たちも長い鼻息をもらして感心した。
なぜか口を挟まないあすかを龍二だけでなく太郎も気になり、なにげない口調で話をふった。
「あすかの家は、どうだったんだよ? お前が小さい頃ってぇと昭和時代の終わりだろうから、さすがに、あみだ車はもう使ってなかっただろ」
「ええ……酒造りにはね。でも、皆造を迎えるこの時期になると職人が蔵の二階に暖気樽とかの道具をかたづけるんだけど、階段を使って運ぶのは大変だったから、やっぱりあみだ車で引っ張り上げてた。うちには、大型の電動ウインチやリフトなんて無かったから。この写真を見てると、あの頃うちに出稼ぎで来ていた蔵人や杜氏の姿をおぼろげながら思い出すなぁ……みんな腕っぷしが太くて、肩の筋肉も凄かったの」
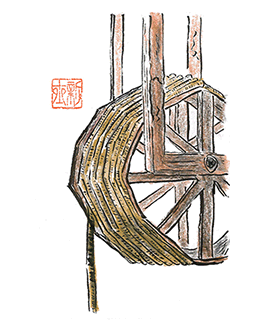
ようやく表情をほころばせたあすかに、矢口がほほえみながらつぶやいた。
「あみだ車を、毎日引っ張るからねぇ。それに比べると、ウインチに頼ってる私たちはひ弱だな」
あすかは矢口の言葉だけでなく、太郎や平、龍二が送るおだやかなまなざしに小さくおじぎを返した。
しんみりとなったカウンター席に、銀平の声が響いた。
「てやんでぃ! 俺の腕っぷしほどじゃねえだろ。この銀平様は、毎日、トロ箱を百箱以上かついでんだからよ。どうだ! 今度、静岡にあるこの蔵元へ一緒に行って、俺があみだ車を回して桶を引っ張り上げるのを見たくねぇか? きっと、見直すぜ!」
銀平は大袈裟に火野屋のトレーナーを腕まくりすると、見事な力こぶをあすかに見せつけた。
「はいはい、素敵な筋肉ねぇ。銀平さんが回すのって、あみだ車じゃなくて、口ぐるまじゃないの? まったく単純なんだから。ひょっとして頭の中も、筋肉でできてんじゃない?」
笑いをこらえていた太郎や客たちの大声が、カラカラとあみだ車のように回った。
