昼休みに皇居の外周を走るランナーたちが、Tシャツにたっぷり汗を染ませている。
新緑の訪れを愛でる暇もないほど都内の気温は急上昇し、渋谷や原宿は半袖姿の若者たちで賑わっているとニュースも報道していた。
その夜も気温は25℃に上がり、純白のスプリングコートを脱ぎながらポンバル太郎の扉を開け放った高野あすかに、菱田祥一が「うおっ!」と声にならない驚きを発すると、男客たちもいっせいに注目した。
温かくなったとはいえ、臙脂色のノースリーブのワンピースは予想だにしない服装だった。しかも大胆なレース模様の裾から覗く太ももに、カウンター席の平 仁兵衛は息を止めたかのように、盃を手にして固まっている。
手洗いから出て来た火野銀平は出会い頭にあすかと対面し、鳩が豆鉄砲を食らったような顔になった。しかし面食らったり、目のやり場に困っている大人たちをよそに、剣があすかの体のシルエットに瞳を凝らしながら訊ねた。
「あすかさん。それって、ひょっとして柿渋で染めてない?」
「当たり! さっすが剣君だね。これ、うちの実家に残っていた酒袋をほどいて、ワンピースに仕上げたの。色合いもレトロ調で、素敵でしょ?」
あすかがクルリとターンするとレースのフリルがめくれて、テーブル席の男たちをどぎまぎとさせた。そして、いつもならとがめるはずの銀平も、純米吟醸のグラスを持ったままあすかのワンピースに目を細めた。
「よくそれだけの数の酒袋が残ってたなぁ。柿渋の酒袋ってハンドバッグとか小物入れは見たことあるけど、ワンピースってのは初めてだぜ。こりゃ、酒蔵の娘にしか考えつかねえな」
銀平がカウンターの奥で同感している太郎に笑みを投げると、隣席の菱田が誰とはなしに訊ねた。
「でもさ、柿渋って肌に悪くないの? 渋柿を食うと歯がキシキシするじゃないか」
単純ながらも的を得た質問にその場が静かになった時、燗酒に上気した平が首を横に振りながら口を開いた。
「いやいや、柿渋は万能薬なのですよ。私も輪島で育った頃、母親がよく作ってました。渋柿をすり鉢に入れておろし、水を加えて発酵させるのです。そのうわずみ水が柿渋です。私の父親は血圧が高かったのですが、これを毎日少しずつ飲んでいたおかげで健康でした。私は、すり傷や切り傷にも塗ってましたよ。柿は日本を代表する伝統的な果実です。例えば、平安朝の延喜式の記録文書には、干し柿子が載っていてこれを料理の甘味料に用いたそうです。干し柿を保存する専用の陶器があったぐらいですからね」
「なるほど、それは解かるなぁ。江戸時代の砂糖は琉球や薩摩からしか手に入らない高価な品だったからな」
つぶやく菱田のそばにあすかが腰を下ろして、言葉をつないだ。
「それに、干し柿は二日酔いを防ぐ薬でもあったの。私が小さい頃、うちの蔵人たちは前掛けのポケットに干し柿を忍ばせてた。二日酔いを早く治したいから、かじりながら仕事をしていたのを憶えてるわ」
それを聞いたテーブル席の客の一人が
「柿って、海の牡蠣のまちがいじゃないのか? 酔い止めのドリンクに牡蠣エキスってあるじゃん」
と仲間たちに問いかけていた。
そのようすに頷きながら、太郎もあすかに付け加えた。
「確か、こんな江戸時代の逸話もあるな。武士が酒の宴席に呼ばれた時は、宿酔しないために懐紙に干し柿を包んで出かけるのがマナーだったそうだ」
「なるほど、だから今でも柿を食うと酔い止めになるってわけか……酒袋といい、日本酒と柿の縁ってけっこう深いんだな」
菱田が並び座るあすかのワンピースをしげしげと見つめると、剣がそばに寄って膝元のレースのフリルに触った。途端に、菱田は冷酒をのどに詰まらせ、銀平が声を上ずらせた。
「こ、この野郎、大胆なことをしやがって。太郎さん、家庭教育がなってねえんじゃねえか」
しかし、剣はそんな声には耳をかさずワンピースの生地目をいじり、あすかは嬉しいような困ったような表情で裾を押さえながら赤面していた。
「柿渋って、長持ちするんだね。これって、かなり年代物の酒袋でしょ? それとさ、酒を搾る槽(ふね)や桶にも柿渋を塗り込んでいたんでしょ?」
「ええ、そうよ。それは、火落ち菌を防ぐためね。日本酒を腐らせてしまう火落ち菌は頑固で、なかなか蔵から消せないの。出来上がったお酒は一度70℃ぐらいに温めて滅菌するんだけど、火落ち菌は完全には消えない。だから、その繁殖力を弱めるために、酒造りの道具や桶や樽のほとんどに柿渋を塗って使ったの。最近の酒袋は化繊で造られていて防止力があるけど、このワンピースのような木綿の袋だと火落ち菌が繁殖しやすかったのね。実は柿渋を使う防止方法って、今も使われてるのよ」
あすかの話しを伝票の裏に走り書きする剣に、平が満足げな顔で言った。
「日本人の知恵は、本当にすばらしいですねえ。その服は、あすかさんをいつまでもキレイにしてくれそうですねぇ。それに柿渋は虫除けにも使われてましたから、あなたに変なムシがつかなくって、いいね」
「まぁ、先生! 嬉しいお言葉ですわ。一杯、お注ぎしますね」
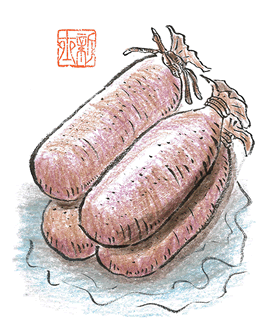
席を立ったあすかは、平の隣にいる銀平を腰で押しのけるようにして座った。
「こ、この野郎! どいて欲しいのなら、ちゃんと頼めよ」
「なによ。悪い虫がいるから、柿渋の服でどかしてるんじゃないの。あっ、そうそう柿渋石鹸もあって体臭予防にいいから、銀平さんの加齢臭に効くんじゃない」
「ぐっ、くっそう。今夜は褒めてやろうと思ったのに、へらず口ばっか叩きやがって」
あすかに鼻息を荒げながらも、ほろ酔いの銀平は気になるげに自分の胸元の匂いを嗅いだ。
「あ~あ、銀平さんって子どもってか、解りやすい男だね。ちょっと干し柿みたいに枯れた方が、人間味が旨くなっていいんじゃないの」
たしなめる剣の大人びた言葉に、笑いをこらえていた客たちが思わず吹き出した。
