神宮の森の新緑が萌え、数日、都内は初夏のような陽射しが夕暮れまで続いている。
その中を額に汗する火野銀平が、くたびれた足取りで通りを歩いて来た。相当疲れているのか、後ろから近づく高野あすかの気配にまったく気づいていない。
ここ半月ほど、銀平は築地市場の記録的な初カツオの入荷に忙殺されていた。太郎が仕入れるカツオも去年より幾分安くなっているのはその証拠だった。
ただ、銀平は入札で二番手ばかりを食らい、一番カツオを落とせないと愚痴っていた。
そんな忙しさのせいでポンバル太郎に顔を見せない銀平の噂を聞いていた高野あすかが、手にぶら提げる紙袋で銀平の尻を軽く叩いた。
「お疲れねぇ! 火野屋の初カツオと山田錦の純米大吟醸で、一杯やらない!?」
「うん? 何だ、あすかか……山田錦って、珍しくもなんともねえじゃねえか。どうせなら亀の尾とか、変わった酒造好適米の酒を持って来な。俺は、ここんところ一杯も日本酒を口にしてねえんだからよ!」
虫の居所が悪いのか、銀平はうとましげに袋の中の四合瓶を一瞥した。どうやら、太郎から聞かされた二番カツオの競り落としを、まだ引きずっているようだった。
あすかは覇気のない銀平を内心気遣いながらも、いつものようにいじくった。
「あら、ご挨拶ね。せっかく元気づけようと思ったのに。いいわよ、じゃあ、あげない。山田錦は山田錦でも、特Aランクなんだから」
「……な、何だよ、その特Aてのはよ」
あすかが銀平の質問に答えず、ポンバル太郎の扉を開けると、待ち構えていたかのように平と龍二がふり向いた。
「来た来た! 特Aの優等生君の登場だ」
「うむ。待ってましたよ、あすかさん。兵庫県産山田錦の真骨頂とやらを、とくと味わせてもらいましょうかねぇ」
平の声に、テーブル席に座る顔見知りの客たちもお裾分けを欲しげに、あすかへ愛想笑いを投げた。カウンターの向こうの太郎も、利き猪口を用意して手ぐすねを引いている。
そのようすに、ただならぬ雰囲気を感じた銀平は態度を変えてあすかにおもねった。
「よう、俺にも飲ませろよ。せっかく持って来たんだから、利いてみてやるよ」
あすかは背中を向けたまま、聞こえない素振りだった。だが、平や龍二は、あすかにしたり顔を見せた。テーブル席の客たちは、どことなく平たちが何かを仕組んでいることに気づいた。
「利くってか? お前に、特Aの山田錦の味が判るのか? じゃあその前に、この酒を飲んで俺の質問に答えられたら、特Aを飲ませてやるよ」
銀平に鼻白む太郎が冷蔵ケースから取り出したのは、新潟県の純米吟醸だった。無濾過生原酒のラベルの上に、「新潟県産 越淡麗 使用」と添え書きがあった。
「越淡麗は、山田錦と新潟県の五百万石をかけ合わせて開発された米だ。すっきりとしたキレのいい五百万石の良さと、香りと旨味が絶妙に調和する山田錦を交配させることでさらに味わいが良くなるけど、もう一つ、五百万石の欠点を無くそうとした。さて、それは何だ?」
太郎の問いかけに、じれったそうに特A山田錦の酒を待っていたテーブル席の男たちが、思わず下を向いた。それに気づいた銀平が、聞こえよがしに声を高くした。
「へっ、五百万石は、精米歩合が高くなると米が割れやすいんだ。だから、精米しやすい山田錦の特性を生かして、大吟醸向けに開発したのが越淡麗だよ。その程度は、俺だって知ってるんだ。ただ、一等米とか二等米ってランク付けは聞いたことがあるけど、特Aってのは知らねえよ」
腕組みする銀平に、あすかがこらえきれずに吹き出した。
「な、何でぇ、何がおかしいんだよ?」
「ううん、そうじゃないの。くっくく……まったくもう、単純なんだから」
小声でつぶやくあすかに、平も特Aの山田錦を待っている空っぽの盃を震わせながら、
「心配するだけ、野暮ですね。あすかさん、取り越し苦労でしたねぇ」
と笑みをもらした。
その時、テーブル席の客の一人が銀平に訊ねた。
「あの、ちょっと訊きたいんですけど、酒造好適米って、どれくらいあるんですか?」
「ううんっと……おい、龍二! お前、答えろ!」
無茶ぶりをする銀平だったが、龍二は嬉しげに返事をした。いつもの銀平らしい態度に、平とあすかも視線を合わせて頷いた。
「あっ、はい。そうですね、僕が過去に調べてみた時は、昭和の戦後からだと200種類は超えてるんですよ。ただ、人気がなくて廃止された品種もあります。それでも、最近は各県の農業試験場で地産池消をテーマにした酒造好適米が開発されて、味の個性化だけでなく、原料として安く調達できるようになりましたから、それで造る酒は価格も手頃ですよね」
「えっ、そんなにあるのかよ? じゃあ、俺の知ってる雄町とか美山錦とかって、基本中の基本なのかよ」
「まぁ、そう言うことですなぁ。ちなみにその越淡麗、飲んでみて、どう感じますかな?」
銀平のグラスに太郎が注ぐ越淡麗の純米吟醸を見つめながら、平が訊ねた。
香りをかぎ、ひと口啜った銀平は、満悦の表情で答えた。久しぶりの日本酒だけに、口元が潤うようだった。
「うむ、いいんじゃねえの。太郎さん、これスッキリとして、まさに初カツオにバッチリだぜ!」
「その越淡麗は、二等米だよ。だけど、うめえだろ? そう感じたなら、お前に元気が戻った証拠だ。特Aだろうが、二等だろうが、日本酒が本当に美味しいと感じる時が、一番幸せなんだよ。お前が落とし損ねた一番カツオだって、二番カツオよりは美味しいだろうが、今年初めてカツオを食う人にとっちゃ、うまいってことだ。いつまでも、失敗を引きずってんじゃねえと、この特A山田錦はあすかちゃんがお前を元気にしようと思って用意したんだけどよ。どうやら、もう立ち直ったし、必要ねえな」
涼しい顔の太郎が、カウンターに用意した特A山田錦のグラスを取り上げた。
「おっ、おいおい、太郎さん。そりゃ、ねえよ。だってよ、特Aの山田錦って、どんなのかも、まだ教えてもらってねえじゃん」
「それを自分で勉強する努力が、いつまで経っても、お前には足りねえんだよ。ほらな、あすかちゃん。やっぱり心配するだけ無駄だったろ?」
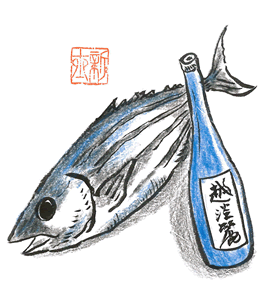
すると、あすかだけでなく平や龍二も、あきらめとも安堵ともつかないため息をもらして笑った。
「いいじゃないですか。やっと、いつもの銀平さんらしくなったし」
と龍二がグラスをかざすと
「そろそろ、泣き言でシメますかねぇ」
と平が笑い
「まっ、この特A山田錦の純米大吟醸は、お勉強ができるまでお預けね」
とあすかがグラスを飲み干した。
三人が立て続けるハッパに、銀平の口から「そりゃ、ねえよぉ」といつものセリフが飛び出した。
