富士山が霞んでいる西の空からようやく入道雲が去り、彼岸の夕風はうろこ雲を連れて来ていた。雲間からこぼれる茜色の光が、ポンバル太郎の玄関に立つ男の横顔に射した。
右手に大きめのトランクを引いていた。緊張している中年男の気持ちが、固まった拳に見え隠れした。御仕着せのような背広姿の男は長い息を吐くと、腹を決めたように扉を開けた。
「こんばんは……与和瀬さん、いらっしゃいますかぁ」
言葉には、強い訛りがあった。山出しの語尾に、カウンター席でひやおろしを飲んでいた高野あすかが反射的に振り向いた。驚きよりも懐かしさが、あすかの表情にはこぼれている。
「太郎さんなら、裏口からお酒の空瓶を出してます。あの、失礼ですけど、ご出身は東北じゃないですか?」
不躾な問いかけに野暮ったい風体の男は赤面し、口ごもった。途端にあすかも我に返って、頬を赤くした。
「いやだ、ご、ごめんなさい! どうしたんだろう。失礼なこと、訊いちゃった」
お互い気まずげに口ごもると、客のいない店内がなおさら陰気になった。男はうつむきかげんで、唇を噛みしめたまま上気している。だが、腹を立てているふうではない。
「さすが、津軽の人は我慢強いですね……待ってましたよ、千堂 健さんですね。真知子さんから聞いています。それで、持って来ましたか?」
太郎の単刀直入な言葉が沈黙を破ると、あすかは男が居酒屋マチコの女将から紹介されて太郎を訪ねて来たことを察した。素朴な顔立ちや容姿は、職人か料理人にも見えなくはない。しかし、田舎っぽさは露呈している。
「はい! よ、よろしくお願いしまっすぅ。これが、うちのサバ節ですぅ」
弘前市の海産物卸会社に勤めている千堂は、この春から東京営業所に赴任していた。かつてマチコの常連客だった亡き辻野という男の親戚で、縁つながりでポンバル太郎を紹介してもらったと語った。
千堂は緊張を解くどころか、トランクを開けるなりビニール袋に詰めていたサバ節を床にばら撒いた。サバ節ならではの濃厚な風味が、店内に広がった。
「あらぁ、大変だぁ! でも、私の大好きな匂いだわぁ」
とっさにサバ節を拾い上げるあすかの言葉も、いつの間にやら訛っていた。せっせとサバ節を集める二人の姿を、太郎はしばらく見つめていた。そして、足元に転がっているサバ節のかけらを拾うと、半分に割って口へ入れた。
?みながら舌の上で転がす太郎に、千堂が斟酌するように言った。
「す、すみません。手造りのサバ節ですから、臭みも強くってぇ……やっぱり、ダメでしょうか」
太郎は、サバ節の色艶と身の締まり具合を確かめながら答えた。
「千堂さん、俺たちはまだ何も、話し合っちゃいねえぜ。それに俺よか、そこにいる女性は福島県の相馬出身だから、サバ節には詳しいはずだ。あすかちゃん、どうだよ?」
ビニール袋にサバ節を戻し終えたあすかが、表情を硬くしたままの千堂へ親指を立てた。
「食べなくたって、匂いと指ざわりで納得しちゃった。うちのお祖母ちゃんが使ってたのと、そっくり!」
満悦するあすかから袋を渡された千堂は、大げさに胸を撫で下ろした。見せかけではなく、彼の人となりから出たしぐさに、太郎は素のままの笑顔で言った。
「安いサバ節みてえに、あんたのその控えめで、内向きなところも真知子さんは気がかりみてぇだな。はっきり言って、サバ節を使う料理はうちには少ない。だけど煮炊き物の味をととのえたり、スープの隠し味には欠かせねえ。おっと! このサバ節の良し悪しを目利きできる奴が、そろそろ現れる頃だ」
すると、その言葉へ相槌を打つかのように、玄関の鳴子が音を立てた。あすかと太郎のサバ節の吟味に気をゆるめた千堂だったが、響いた鳴子にまた頬をこわばらせた。
「お待たせ! あれ? あすかも……そうか、おめえの地元もサバ節でダシを取るな。あんたが千堂さんかい? 火野屋の銀平だ、よろしく頼むぜ」
千堂を歳下と踏んだ銀平は、鷹揚な口ぶりで自己紹介するとカウンター席に千堂を誘った。
「チンタラやってちゃ、客がやって来て太郎さんに迷惑をかけちまわぁ。あんたの造ったサバ節、味見させてくれねえか。火野屋で扱うかどうかは、ささっとこの場で決めちまうぜ」
江戸っ子かたぎの巻き舌に気おされた千堂は、せわしなくサバ節を取り出すと、くたびれた背広のいずまいを正して黙り込んだ。
銀平はそれを一瞥して太郎に笑みを投げると、サバ節を噛みしめた。
固唾を飲んだままの千堂に、銀平が口を開いた
「こいつは、ちゃんと天日干しをしてるな。サバの身独特の脂と強い香りが残っている。だからカツオ節よりも甘めの、コクのあるダシを取ることができる。課題は、こいつの風味をどんな酒の肴に生かせるかだ……だけどよ。あんたも、てめぇんちの商品なんだから、ちったぁ、俺にアピールしてみな。朴念仁みてぇに、ただ黙ってんじゃねえよ」
銀平のいつになく裏返った声に、あすかはわざと語気を強めていると気づいた。銀平と太郎は、明らかに前もって何かを企んでいると思った。
「はぁ、誠に申し訳ねぇっす……そこが三十にもなって、私のダメなところですてぇ」
白髪のまじった坊主頭を掻く千堂の前に、太郎が小さな瓶を置いた。300ml入りの酒瓶の中に、焦げ茶色の液体が詰まっている。瓶からは、強い香りが洩れていた。
「こっ、これはもしや“サバの煎じ”では、ないですかぁ?」
瞳を凝らす千堂に、太郎が安心したように頷いた。
「判ったかい。この煮汁はサバから出た鉄分やミネラルもたっぷりで、旨味調味料よりも濃厚だ。うちでは、湯豆腐のダシやシメの蕎麦つゆに入れる。ラーメン店では、スープの隠し味に使ってる店もある。俺は、これを真知子さんに教えてもらったんだよ。でもよ、真知子さんもある人に頂くまで、この存在も使い方も知らなかったそうだ」
謎かけする太郎に続いて、銀平があすかに訊いた。
「あすかも、サバの煎じを知ってるだろ? サバ節を造る前に、内臓を取ったサバをじっくり煮た後の残り汁だ」
「ええ、うちにもあったわ。ねっとりした水飴みたいなんだけど、なめると旨味がたっぷりなの……あの味つけに合う日本酒となれば、どれかなぁ」
銀平の思惑を読んだあすかは冷蔵ケースを探ると、津軽の濃醇な純米酒を取り出した。その「津軽恋」の一升瓶を選んだあすかに銀平が感心すると、太郎が千堂に言った。
「ある人が、サバの煎じに合うと真知子さんに薦めたのも、その酒だったそうだ」
はっとした顔で、千堂がつぶやいた。
「ひょっとして、辻野の親爺さんですかぁ……いやぁ、そうにちげぇね」
千堂は津軽恋のレッテルを指で触れながら、辻野がその酒を晩酌にしていたこと、可愛がられた幼少の頃の思い出、少年時代に聞かされた東京のようすや苦労話を語った。
「夢みたいな町だけど、おっかねえ場所だとも思いました。だから、津軽を離れることなく、地元に就職したんだども……因果だなぁ」
太郎はしょげる千堂が、カツオ節に比べて売り押しの弱いサバ節のように思えた。真知子が自分に千堂の話しを持ちかけた理由は、サバ節うんぬんよりも、人となりの相談だったにちがいないと確信した。
「いい歳をしてヘコんでても、しかたねえだろ。あんたの業績が伸びないのを、真知子さんは心配してるぜ。上京した当時の辻野さんも当初は引っ込み思案で、控えめな自分が嫌になったらしい。業界はあんたとちがうけど、津軽らしい味のサバ節やサバの煎じをアピールし、津軽の地酒と合うことをしゃべってるうちに、周囲の人たちと打ち解けたそうだ」
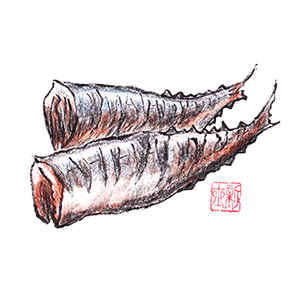
太郎はサバの煎じが入った小瓶を数本冷蔵庫から取り出し、千堂の前に置いた。
それでも気後れしている千堂の背中を、しびれを切らした銀平が一発張り上げた。
「おう! まずは、あんたもそこからだ。火野屋は明日からでも、そのサバ節は仕入れてやらぁ。ただし、今から俺と一緒に同行営業するんだ。うちが納めてる料理店に、さばの煎じと津軽愛をあんたの口から自慢してみな。それができねぇなら、取引はお断りだ!」
その音を合図にしたかのように、数人の客が扉からなだれ込み、対峙している銀平と千堂を傍観した。
千堂は周囲の視線にたじろぎつつも、銀平に深々と頭を下げて
「よ、よろしく、お願ぇしまっす!」
と恥じることなく津軽弁を言い放った。
鼻で笑う客たちを睨みつけたあすかが、千堂にグラスを手渡し、津軽愛の一升瓶を傾けた。
「千堂さん、頑張って。きっと辻野さん、空から見てるわ。サバ節と津軽愛で、一杯やりながら」
すると、今しがたの客の一人が嬉しげに言った。
「俺、サバ節大好きなんだぁ。その酒、故郷の地酒ですぅ」
しばらくすると、千堂の門出に景気をつける東北訛りの乾杯が、ポンバル太郎に響いていた。
