重陽の節句が過ぎたものの32℃を超える残暑のぶり返しに、長そでシャツへ衣替えしたサラリーマンたちが辟易しながら歩いている。シーズン終了を前にした都内のビヤガーデンは、にわかに活況するほどだった。
火野銀平が一瞥する通りの居酒屋や立ち飲み店でも、生ビールの注文が盛り返している。
「ちくしょう。俺も早く、冷酒が飲みてぇ!」
冷えた大吟醸と冷や奴が目の前にちらつく銀平は、思わずポンバル太郎の玄関先でつんのめった。
ここ数日は東京湾が荒れて、火野屋が得意とする活け魚が減っていた。どうにかして活きたままでと注文されても、しけのせいで弱った魚介類は長くもたない。それを活かす工夫を思いつかない銀平は、ふがいなさに気持ちが落ち込んでいた。
意地っ張りの江戸っ子だけに、まわりの競合店に相談を持ちかけない性格が仇になっていた。
「おいおい、銀平ちゃんともあろうもんが夏バテかいな。ちょうどええわ。旬の明石だこ料理の名人を大阪から呼んでるさかい、今晩は“たこしゃぶ”を食わしたるで!」
肩越しの関西弁に中之島哲男と判ったが、立ちくらみを起こした銀平は、とっさに振り向けなかった。
「たっ、たこしゃぶって……あったけぇ鍋の、しゃぶしゃぶ? 師匠、そりゃ拷問だぁ。勘弁してくださいよ」
ふらつく銀平がのどを鳴らしながら扉を開けると、あろうことか、カウンター席から湯気が立ち昇っていた。小さな素焼きの七輪の上には銅鍋が乗っかり、高野あすかが具材を盛った皿を前にしている。テーブル席にも、同じ小鍋をつつく客たちがいた。
「あっ! 中之島さん。グッド、タイミング! 今から、たこしゃぶを頂くところなの。明石だこって、今が最後の旬なのね。」
問わず語るあすかに、中之島は嬉しげに隣へ座ると、明石だこの薄い切り身に目を細めた。
「台風の後は、兵庫の山に降った雨水が栄養分をぎょうさん含んで、植物性プランクトンといっしょに明石の海へ運ぶわけや。これが“鹿の背”と呼ばれる浅瀬に溜まると、それを食べる動物性プランクトンや小型の魚介類が集まって、明石だこの餌になるんや。ましてや、明石海峡は潮の流れが速いよって、それにもまれるたこの生命力も強い。“明石のたこは、立って歩く”ちゅうからな」
テーブル席の客たちが、中之島の含蓄に感心した。
その声を聞く銀平はクーラーの下で頭を冷やしながら、うつろな視線をカウンターに向けた。柳葉包丁の冴えもさることながら、半透明の身はまだ活きているせいか、小刻みに動いている。
「この明石だこの生命力が、元気をくれるのかしら。たこしゃぶって、タウリンって栄養がダシに出て、夏バテ回復にいいんでしょう?」
煮立ってきた昆布ダシに待ちきれないようすのあすかが、誰とはなしに投げかけた。
厨房から出た太郎が、花びらのような明石だこの切り身を箸でつまみながら、だしに通した。
「たこしゃぶは、食い倒れの大阪で生まれた究極のたこ料理だ。それを考え出したのが、中之島師匠の親友の箱田さんだ。酒匠としても、素晴らしい方だぜ」
太郎の声に厨房の奥から現れたのは、白い割烹着がはち切れんばかりの体格をした六十がらみの男だった。薄く剃った頭や面差しが、誰かに似ていた。
「あっ、銀平さんと似てる! 親子みたい」
クーラーに冷えた銀平も、夏バテ回復の言葉と箱田の顔立ちに惹かれてカウンター席へ腰を下ろした。
疲れた顔の銀平の前に、箱田が小皿を置いた。
「まずは、これと明石の純米酒をやってみなはれ。明日の朝は、体が復活してまっせ」
隣のあすかがほくそ笑んだ。先に銀平は、その料理に度肝を抜かれていた。
「ぎゃっ! まだ、動いてっじゃねえかよ!」
皿の中では、切った明石だこの足や吸盤がのたうっている。明石だこの「踊り食い」である。同じ皿を出された中之島は、くねっている足を口に放り込むと、しばらく舌の上に吸いつく感触を楽しんでから酒を流し込んだ。
椅子から腰を浮かせる銀平に、中之島とあすかが大声で笑った。
「なんやねん、銀平ちゃんは毎日活きた魚をさばいてんのに、活けだこは苦手かいな」
「だって、銀平さんの親戚みたいだもんねぇ」
銀平は冷や汗を拭きながら、箱田へ申し訳なさげに答えた。
「俺は、売るのと食うのじゃ別なんで……まして、活きたままのたこってなぁ、魚屋泣かせなんですよ」
銀平は、東京湾で獲れる真だこは築地や深川の料亭に人気で、活けだこを欲しがる得意先もある。だが他の魚を傷つけるから、同じトロ箱では運べない。たこ専門の卸業なら方法はあるんだがと答えながら、昨日断った活けだこの注文を思い出した。
その曇りがちな横顔を、中之島が見つめていた。
「その通りですなぁ。私も昔、なかなか活けの明石だこが手に入らんもんで、苦労しました。そやから、あんさんと同じように一時はたこを嫌いになりました。けど、私の求める究極の明石だこ料理は、活きてないとあかんのです」
箱田は、活きた明石だこを魚と一緒に運ぶと、からみついて傷をつける。スミを吐くと、魚が汚れる。水槽に入れると、吸い付いて取り離しづらい。だから漁師や仲買人だけでなく、料理人も扱うのを嫌がったと話しを続けた。
「それでも箱田はんは、あきらめへんかった。食い意地が張った大阪人の知恵を見せよった。明石だこを活きたまま運ぶ方法を、自分で考えたんや。ワゴン車の後ろにバケツを並べて、エアーを送る装置を取り付け、大阪から毎日往復や。あの頃はわしも手伝いで、明石の漁協まで通ったもんや」
中之島は懐かしげに語ると、銀平に冷酒グラスをわたして純米酒を注いだ。その酒と、たこしゃぶを口にした銀平の顔に精気が戻った。
「けどよ、それじゃあ、経費も時間も馬鹿にならないじゃねえですか」
銀平の問いにあすかも頷きながら「今も、そうしてるのですか?」と箱田に訊いた。
すると、おもむろに箱田が右手で赤い塊りを持ち上げた。それは、みかんを詰めて売る際の、ビニールの赤い網だった。
「偶然の産物ですが、私にとっては、まさに神様のお恵みでしたわ。淡路島の漁師が地元名産のタマネギを入れる網に、活けだこを入れるアイデアを発見したんです。こないしたら、ほかの魚にからむことなく一緒に水槽で運べるし、たこにストレスがかからず、元気なまま手に入るんです。今では全国の活けだこ業者が、この方法を使うてますわ」
箱田の言葉が終わると、中之島が銀平の顔を覗き込み意味ありげに笑った。
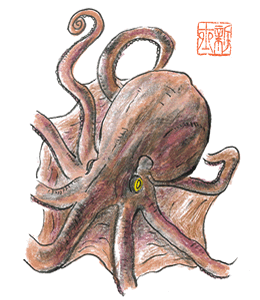
「そっ、そうか……これと、さっきの空気を送るブクブク装置を使えば、どうにかなるじゃねか!」
口走った銀平が血相を変えて立ち上がると、太郎が言った。
「おい、踊り食いも食ったら、今夜はとっとと帰るんだぞ。お前、明日の活け物を届ける算段をしなきゃなんねえだろ」
すべてお見通しの太郎に、中之島とあすかもたこしゃぶを食べながら、うんうんと頷いた。
そのようすに、箱田が笑みを浮かべながら口を開いた。
「たこと付き合ってると、たこの性格や癖も気づくんですよ。そやから、銀平さんのお人柄、私にはようと分かりまっせぇ」
「へいっ! たこ田師匠、今後とも、よろしくお願ぇいたしやす!」
箱田をたこ田といじくる銀平のように、しゃぶしゃぶ鍋の明石だこもほんのりと赤くなっていた。
