ちゃんこ鍋や寄せ鍋の幟が繁華街の店頭に並び、客引きの店員たちの吐く息はうっすらと白くなっていた。
ポンバル太郎の通りでも午後7時を回ると、冷えた夜気が吹き抜ける。先週に街路樹の茂みで寝ていた野良猫は、いつの間にやら姿を消していた。
今しがたやって来た火野銀平の手にするスポーツ新聞は、「今年も紅葉の季節は短く、師走は都内で大雪のもよう」と報じている。
「この前まで猛暑日の連続記録だ、なんだと、騒いでたのによ。もう雪の心配をしなきゃなんねえのか。こう冷えてくると、やっぱり、おでんと熱燗はありがてえぜ」
カウンターの向こうで煮立っているおでんの銅鍋に銀平は目尻をほころばせ、お燗酒のチロリを持つ太郎に盃を差し出した。銀平が好きな秋田の辛口純米酒である。体を早く温めるにはもってこいの、濃厚な味わいだった。
「そういや、今夜は久しぶりに中之島の師匠がやって来るぞ。なんでも、珍しいおでんダネを持って来てくれるそうだ」
太郎は盃を満たすと、菜箸でおでんをつつきながら、銀平が頼んだ厚揚げと大根を皿に盛った。よくダシのしみた褐色の大根に、テーブル席の客が「うほ! うまそうだ」とつぶやいた。
「へぇ。おでんダネね。関西じゃ、おでんを関東煮(かんとうだき)ってんだろ? 聞くところじゃ、ちくわぶやハンペンが入ってねえらしいな」
「ああ、大阪じゃ、牛のすじ肉やくじらの脂身を入れる。ダシも関西風で、少しうす味だな。東京人には、物足りねえらしい」
銀平の前に置かれた皿が、醤油ダシの香りと湯気を立ち昇らせた。鼻先をひくつかせると、カウンター席の隅で独酌する中年の男が口を開いた。
「あのう……おでんにひら天ば、ありますか?」
どことなく、九州地方の訛りがある声だった。男の浅黒い顔に彫りの深い目元も印象的で、
ポンバル太郎では珍しい長崎県の本醸造を飲んでいた。
「ええ、ありますよ。お一つでいいですか?」
太郎が答えながらひら天を箸で引き上げると、一瞬、男は顔を曇らせて
「あっ、や、やっぱりけっこうです……じゃあ、大根とつみれば、お願いします」
と注文を変えた。
男の視線からすると、どうやら、ひら天が気に入らなかったようだった。すると、今度は銀平が眉をしかめて言った。
「そのひら天、ダシがしみて、柔らかくてうめえよ。築地で魚屋やってるうちがすり身から作ってんだから、まちげえねえ。ひょっとして、お客さんは関西の人かい?」
「このタコ! 押し売りするんじゃねえよ。お客さん、気を悪くしないでくださいね」
太郎が銀平を叱りつけると、男は気まずげにうつむいた。
頭を掻きながら「すみません」と詫びる銀平に、男は「あっ、いや、そんな……」とつぶやいた。
男のしぐさに太郎が素朴な人柄を感じた時、玄関の扉が鳴子を響かせた。
「おでんのタコもうまいやろうけど、こいつは、もっとうまいでぇ…うん? なんやタコはタコでも、銀平ダコかいな」
途端にテーブル席から爆笑が起こり、その場の空気が一気に変わった。苦笑いするしかない銀平に、男もこわばっていた表情をゆるめた。
「ところで師匠、珍しいおでんダネって、何ですか?」
機を見るに敏な太郎が、話題をすり替えた。
「おう、忘れとった! これやがな」
中之島は手提げ袋から油紙でくるんだ四角い塊りを取り出した。そこから出てきたのは、大判の厚揚げのような物だったが、灰色がかった肌にきめ細かな黒点が散らばっている。
「な、なんでぇ、こいつは? まるで、厚揚げのお化けじゃねえすか?」
銀平が目を白黒させ、匂いをかごうと鼻先を近づけると、カウンターの隅から声が飛んだ。
「じゃ、じゃこ天。五島のじゃこ天!」
寡黙だった男が、豹変したかのように立ち上がって叫んだ。銀平と太郎が呆気に取られる前で、中之島は感心した面持ちで男の訛った言葉に頷いた。
「さよう。これは、九州の五島列島のじゃこ天や。一般的には、静岡の焼津や四国の宇和島のじゃこ天が有名やけど、こいつは分厚くて、旨味と歯ごたえがまったくちがう。これをおでんに入れたら、最高にうまいんや! なぁ、お客さん」
「そうですたい! ありがとうございます!」
じゃこ天に太鼓判を押す中之島の恰幅の酔い着物姿に、男は感服したようすで深いおじぎをした。男の謝辞には、はっきりと五島訛りが現れていた。
「ところで、あんさんのお名前は?」
「あっ、はい! 私、松浦と申します。五島では、ありふれた名前ばってん……」
すると、中之島が嬉しげに両手を叩いた。
「あんさん、松浦党の血筋やろ。どえらい強かった、海賊の子孫やおまへんか。ちゅうことは、じゃこ天に縁が深い人やな」
「か、海賊ぅ? しかも、じゃこ天に縁がある? 中之島の師匠、どういうこと?」
じゃこ天から顔を上げた銀平が訊くと、中之島が、それは松浦に答えてもらおうと柔和な目元をカウンターの隅に向けた。
松浦は本醸造のグラスをひと口なめ、喉を湿した。
「私の先祖は、確かに海賊や水軍やったとです。しかし、江戸時代以後は戦う一族ではなくなり、漁をやりながら海産物の加工も手がけんと、生きちょれません。そこで、昔から水軍の兵糧だった海賊天(かいぞくてん)を商品にしたとです」
よく知られている宇和島のじゃこ天は、ほたるじゃこという小魚を骨や皮ごとすりつぶして、手のひらほどの大きさだが、五島のじゃこてんはアジやトビウオの幼魚を使い、両手でも足りない大きさ。ただ、宇和島にしても伊予水軍の河野氏の根城で、やはり五島と同じく海賊が作った食料だった。かつて海賊たちは戦さの船上でじゃこ天をかじりながら、甕酒を飲んでいた。その酒の名残りが、自分の飲んでいる長崎の本醸造なのだ。しかし、近代になって海産物の加工業も年々さびれ、秋冬には東京へ出稼ぎに来ているのだと語った。
「この酒ば飲むんも、久しぶりですたい。東京では、めったに飲めまっせん。じゃどん、今日は五島のじゃこ天にもお目にかかれっとは……誠に、ありがとうございます」
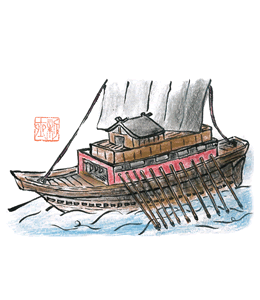
松浦の律儀な態度に店内の客たちが一様に感心すると、中之島が声をかけた。
「海賊の血筋やのに、粗忽さはみじんもおまへんなぁ。誰かさんとは、できがちがうで」
中之島の流し目に銀平が恥ずかしげに赤面すると、太郎がじゃこ天を受け取りながら言った。
「松浦さん、礼を言うにはまだ早いですよ。じゃこ天を、うまいおでんで食ってからにしませんか。それに海賊ばなし、もっと聴かせてもらえませんか」
ためらう松浦の横に、ふいに椅子から立ち上がった銀平が近づいた。
「俺からもお願いします。それで、うちでも、このじゃこ天を、海賊天って名で売らせてもらいてえ!」
松浦が半分飲んだ本醸造のグラスを、銀平に手渡した。
「松浦の海賊は、仲間と同じ盃を飲み回すもんたい」
二人を見つめる客たちの向こうで、海賊天のおでんが心地よい音を立てていた。
