隅田川を抜ける冷たい風に、両国橋を渡って行く人波が肩をすくめている。
新年早々、国技場で催されている大相撲初場所は連日の大入りとなり、界隈の商店街が鏡開きを威勢よく行なっていた。
ポンバル太郎でも、ここ数日、神棚やカウンターに飾っていた鏡餅を御下がりにして、酒粕入りのぜんざいが客たちにふるまわれている。客の中には鏡開きを知らない若者がいて、今夜も高野あすかは出版社の女性スタッフたちを連れて来るなり、テーブル席でぜんざいを勧めている。
「あすかの連れは、甘いのも辛いのも両刀使いかよ。太郎さん、あんなに食わせてっと、餅が足りなくなっちまうじゃねえか」
カウンター席の火野銀平が、純米吟醸の新酒をなめながら愚痴った。
隣で千枚漬けを肴に錫のチロリを傾けている平 仁兵衛は、それとはちがう意味で、ため息をついた。
「それにしても、鏡開きを知らない若者がいるのは寂しいですねぇ。昔ほど、ぜんざいも食べないみたいですし、日本人から正月が遠のいていますなぁ」
声音の弱さに餅を炙る太郎が厨房から覗き見ると、平はずいぶん白髪が薄くなったようだった。そういえば、この1月末に六十六歳を迎える。
控え目な平だけに、誕生日は太郎にしか教えず、常連たちは平の寄る年波に気づいていない。太郎は、この一年でめっきり老けこんだ気がしていた。
「緑寿の祝いか……元気になる贈り物を考えなきゃ、いけねえな」
太郎がつぶやいた時、玄関の鳴子が響いて右近龍二が入って来た。
ここ二週間ほど顔を見せなかったのは出張続きのせいで、龍二はついでに各地の蔵元へも立ち寄ると意気込んでいた。その土産話が、太郎は何よりも平の薬になる気がした。
「おう、龍二! 蔵元はどうだった。東北はドカ雪で、酒の仕込みが大変じゃねえのか?」
ほろ酔いの銀平は、龍二が右手に提げる紙袋を気にしながら訊いた。物欲しげな目元に、龍二が苦笑しながら答えた。
「蔵人の皆さん、麹造りに寝ずの番をしながらも、お元気でしたよ。“室の花”杜氏の西嶋 佳代さん、能登の矢口さん、秋田の神崎さんに、それとあすかさんの従兄の高野武志さんにも、お目にかかりました。しばれる寒さの中で、頑張っておられました」
すると、従兄の名を耳にしたあすかが龍二に近寄って、袋の中身を覗き込んだ。
「お土産は鏡餅?……あっ! これ、ひねり餅でしょ?」
思わずビニール袋に顔を突っ込みそうなあすかを、銀平が叱りつけた。
「おい、あすか! いくら餅入りのぜんざいが好きだからって、いじきたねえことをするんじゃねえ! ところでよ、龍二。ひねり餅って、そんなにうまいのかよ?」
素のままの顔で訊ねる銀平に、龍二と太郎が顔を見合わせた。平も盃を持つ手を止めて、銀平の顔をしみじみと覗いた。
「な、なんでぇ……俺、おかしなこと訊いたかよ」
鼻白む面々に銀平がたじろぐと、あすかはここぞとばかりに皮肉った。
「年初めから出たわねぇ、銀平さんの大ボケ。ひねり餅って、杜氏が酒の蒸し米の状態を見るために作るのよ。だから、売られてるお菓子じゃないの! あいかわらず、不勉強だよねぇ」
頭を剃ったこわもての銀平に対して口さがないあすかに、酒粕ぜんざいを啜る編集者たちは餅を喉につまらせた。
「くくっ、ちくしょう!……ああ、そうかよ。だったら、餅米じゃねえってこったろ。前に酒米の握り飯を食った時、さほどうまくなかったし、俺は餅米のぜんさいを頼むぜ」
八つ当たりしてグラスを飲み干す銀平に、あすかと女性たちが飽きれた。
その時、カウンターを龍二の右手が叩いた。思わず腰を浮かせた銀平は、平へ寄りかかった。平はそれでも、疲れた表情のままだった。
いつもなら銀平の暴言に愛想笑いを浮かべる龍二が、厳しい目つきで見返した。
「銀平さん。うまい、まずいって価値の餅じゃないんですよ。これ、現役に復活した矢口杜氏のひねり餅です。ぜひ、平先生に食べさせてあげてと頼まれたんですよ」
「えっ、矢口杜氏って、本格的に復活したのかよ……俺ぁ、聞いてねえぜ」
銀平が丸くした目を太郎に向けると、あすかも知らないらしく視線を重ねた。
頷いた太郎は、言い訳のないしっかりした口調で答えた。
「去年まで矢口さんが若手の監修をしながら酒造りを続けていたことは、みんな知っての通りだ。それは七十歳を越えてから、両手の動きが鈍くなっちまったせいだった。だけど、この冬の仕込みから恩人の蔵元に招かれた。三顧の礼で頼まれたが、納得のいく酒に仕上がるかどうか自信がないと言ってたんだ。その新酒は、そろそろ届く頃だがな。だから、蔵元を見学する龍ちゃん以外には、まだ伝えてなかったのさ……でも、このひねり餅を渡されたってことは、いい酒ができる証しだろ。まずそれを、平先生に伝えたかったんだ」
太郎の声は銀平じゃなく、いつになくしゃべらない平へ向けられていた。
その場の空気を読んだあすかと編集者たちも、口を結んだままだった。
「そうですか……矢口さんはもうすぐ緑寿になる私を励ましそうと、このひねり餅をくれたのでしょうねぇ。まだまだ現役で頑張ろうって先輩がいるのに、私は情けない男だ。太郎さん、このひねり餅のぜんざいをもらえませんか」
平の緑寿を知ったあすかと龍二が畏まった時、厨房の裏戸が開いて出入りの酒屋が現れた。手にしているのは、銘柄に「矢口」と揮毫された純米吟醸だった。
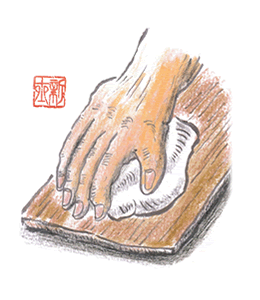
一升瓶を目にした銀平が、すっとんきょうな声を上げた。
「へっ!? 平先生、六十六になるのかよ。気づかねえなんて、俺はトンマな野郎だぁ。太郎さん、ちょいとひとっ走り火野屋に戻って、御祝いに生簀の活け鯛をもってくらぁ!」
言うが早いか、銀平は革ジャンのフードを頭にかぶった。
平はそれを止めようとしたが、太郎が酒の栓を開けながら制した。そして、銀平の背中へ嬉しそうに叫んだ。
「お前、そんな元気があるならよ、ちったあ日本酒の勉強をしろ!」
玄関を飛び出す銀平が、振り向きざまに笑った。
「俺、頭の中だけは粘りがねえんだよ。その内、矢口杜氏に脳みそをひねってもらうかぁ」
龍二とあすかが顔を見合わせて吹き出すと、平がひねり餅を手にしてつぶやいた。
「今年もいい人たちに囲まれて、ありがたいです……私も、ひとひねり、ふたひねり、まだまだ頑張りますよぅ」
矢口が造った酒の前で、丸々としたひねり餅が真っ白に光っていた。
