暴風雪が日本海側に吹き荒れ、その余波の運んだ冷気は皇居の御堀を丸一日凍らせていた。夕刻のポンバル太郎の通りも、3℃まで下がっている。
東北や北陸の蔵元は尋常ではない大雪に酒のモロミが冷えすぎ、造りに難儀しているのではないかと天然ブリの身を切り分けながら太郎は思った。
ポンバル太郎では、寒さに震える客たちがあったかいブリ大根を立て続けに頼んだ。カウンター席に並んだ火野銀平と右近龍二は四人前をたいらげ、太郎は追加で仕込まなければならなかった。
おまけに熱燗の純米酒の注文も殺到し、お燗番に剣を二階から呼び出している。
「おい、こっちの酒はまだかよ。子どもになんて手伝わせっから、遅くなっちまうんだよ」
カウンターの隅に座る五分刈り頭の男がしびれを切らせると、火野銀平と右近龍二が表情をこわばらせた。
途端に、隣りの老人が三十歳そこそこに見える男の頭を小突いた。老人は髪と眉が白く、拳を握る手が皺深かった。年輪を重ねた職人の手だと、龍二は見て取った。
「よさねえかい、三郎。その堪え性のなさが、俺には心配なんでぇ」
男の苦情に燗どうこから銚子を取り出した剣が頭を下げると、老人は気にするなとばかりに何度も頷いた。七十歳過ぎとおぼしき老人の目尻は、孫を見つめるようにほころんでいた。
龍二がほっとした笑みを銀平に向けると、細くなった目が老人を凝視していた。
三郎と呼ばれた若者は、老人に酌をしながらおもねった。
「すみません、万治の親方……ところで、かぶら寿司の仕込み方をそろそろ教えて欲しいんです。俺が必ず、あの味を引き継いでみせますから」
かぶら寿司と聞いて、龍二は金沢名物のなれ寿司と気づいた。冬の日本海で獲れる脂ののったブリを加賀野菜の蕪にはさんだ郷土料理で、ポンバル太郎でも、年末年始の裏メニューになっている。
「ダメだ。まだ、お前には無理だ」
万治が三郎の注いだ純米酒に口をつけた時、太郎がブリ大根の器を置いて詫びを言った。
「お待たせしました。申し訳ないですが、急仕込みの品で、いつもの半日寝かせたブリ大根より旨味が控え目です」
太郎の物腰に、龍二と銀平も万治が腕のいい料理人らしきことを感じ取った。
湯気の中に天然ブリの風味とやわらかな柚子の香りがあいまって、万治の顔が器に向いた。そして箸でブリの身をほぐし、口にすると、ほぅと感心しながら三郎の前に器を押し出した。
「三郎、このブリ大根には隠し味がある。それが何か当ててみろ。できりゃ、かぶら寿司を教えてやってもいい」
万治の言葉に、三郎は真顔になって器とにらみ合った。自分とさして歳の変わらないちっぽけな居酒屋の主人が、師匠の万治を驚かせた? 三郎はそんな戸惑いを浮かべながらブリの身を噛むと、思わず舌を巻いた。
「ここ数日、富山の氷見あたりじゃ海がシケて、漁もできてねえ。なのに、こんな極上のブリが用意できるのは、よっぽどいい魚屋と付き合ってるんでしょう。ただ、短時間でこの旨味とコクを引きだすのに何を使ったのか……分かりやせん」
口惜しげな三郎が万治に上目遣いした時、銀平の口から声が飛び出た。
「思い出したぁ! あんた、深川にあった割烹『加賀』の大将だ! うちの祖父さんが可愛がってた能見万治さんでしょ?」
テーブル席の客たちが、驚いて振り向いた。
三郎のふがいなさに肩を落としかけていた万治は、突然の問いかけに目をしばたたき、銀平が着ている黒いジャンパーのロゴマークに瞳を凝らした。
「あんたの祖父さん? うん? 火野屋……おおっ! 銀次郎さんの孫か!? あの小さかった坊主が、こんなになったのかい。もう、三十年になるかな」
興奮した万治がよろけながら立ち上がると、太郎と龍二は顔を見合わせ、剣も燗した銚子をどうこの中に落としかけた。
三郎が万治の背中を支えながら、銀平と太郎に会釈した。
「こりゃ、失礼しやした。築地の火野屋さんってことは、このブリもそちらから仕入れた上物ってわけですかい?」
火野屋の名に気づいた三郎は割烹『加賀』の板前だろうと、太郎は察した。
銀平の記憶によれば、万治がようやく独立して深川に割烹を開店したのは、昭和57年(1982)だった。当時、五歳だった銀平は、祖父の銀次郎行きつけの『加賀』へ、頻繁に連れ出された。いずれは火野屋を背負う孫をカウンターに座らせ、上物の魚をさばく料理人の腕前を目に焼き付けた。
「そうかい。火野屋が卸してるなら、ポンバル太郎さんの魚は何を食ってもうめえはずだな。このブリの旨味は、麹で引き出している。それも塩麹じゃなく、米麹だ。つまり三郎、かぶら寿司のように米麹へブリの身を漬け込んでるんだ。だから短い時間でも、旨味のある柔らかいブリ大根になった。お前のように米麹を表面だけで見てると、この裏技は分からねえ」
腑に落ちた顔で告げる万治に、三郎は「くっ!」と声を洩らして赤面した。
太郎は冷蔵庫からバットを取り出すと、米麹に漬けているブリの身を万治たちに披露した。ふくらんだ身が、脂につや光っていた。
「恐れ入りました、図星です。米麹に、急いで漬けました。ひょっとして、万治さんも時間がねえ時はこのやり方をなさいますか?」
「そうだ。あんたが使っているのは、総破精(そうはぜ)の米麹だろ。だから発酵力が旺盛で、少しの時間で食材の旨味をたっぷり引き出せる。わしにそれを教えてくれたのは、銀次郎さんだった」
バットの中で溶けている大きな米粒を万治が懐かしげに見つめると、また銀平が驚いた。
「へっ!? うちの祖父さんに、そんな知恵があったんすか?」
「ああ、かぶら寿司の仕込み方の応用だ。銀次郎さんは俺が割烹をオープンした冬、俺の故郷・金沢のかぶら寿司を店の看板商品にしろって言った。そして、脂ののった寒ブリをじっくり発酵させるなら突き破精(つきはぜ)、手早くやるなら総破精の米麹を使えって教えてくれたのよ」
しかもかぶら寿司にはブリだけでなく、サバや鮭も使えるから、米麹を上手く使い分けろと教えてくれたと万治は語った。
感心する龍二の表情に、銀平はその理屈が眉唾じゃないと分かり、気分よさげに熱燗の盃を飲み干した。
「それじゃあ、このかぶら寿司はいかがでしょう」
太郎が、もう一つのバットを冷蔵庫から取り出した。そこにはニンジンや細切り昆布の入ったかぶら寿司が仕込まれ、米麹のふくよかな香りをかいだ剣は唾をわかせた。
ブリの淡い赤身と白い蕪のなれ具合を目にした万治は、味見もせずに言った。
「うむ、上出来だ。仕上げにひと工夫すると、さらにうまくなるな。三郎、お前が頂いてみろ。このかぶら寿司を、より美味しくするにはどうすればいいか、考えてみろ」
万治が命じると、三郎は目を皿にしてかぶら寿司のバットを見つめた。白いつけ汁がプクプクと泡を立てて、おだやかに発酵していた。
かぶら寿司をつまんだ三郎はその美味しさに脱帽し、「う、うまい」とつぶやいて黙り込んだ。答えを待つカウンターの面々に、三郎の声は聞こえなかった。
「……やはり、まだお前にゃ、うちのかぶら寿司は継がせねえな」
万治が白い眉をゆがめてくさした時、龍二が立ち上がり、日本酒の冷蔵ケースから純米酒を取り出した。そして盃一杯の酒を、バットの中に垂らした。
その動きに太郎と剣が満足げに頷くと、万治は瞠目していた。むろん、三郎は声をなくしている。
「三郎さん、このかぶら寿司は発酵が強くて、少し酸味が高まっていたでしょう。でも、水で薄めちゃダメです。酒で酸味をおさえ、旨味も調えるんですよ。米麹にしてみれば、酒とは親子関係ですからね……万治さん。生意気なようですが、もったいぶらずに教えるべきです。あなたも若い頃、銀次郎さんに教わらなきゃ分からなかったんじゃないですか?」
龍二は毅然とした態度で万治に対すると、三郎の横に腰かけ、酒と米麹を使った旨味の引き出し方を教え始めた。
ふうっと長いため息を吐く万治の横に、銀平が腰を下ろした。そして、熱燗の酒を盃に注ぎながら笑った。
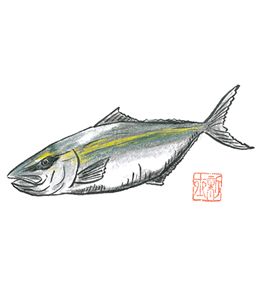 「へっ、三郎さんって、若い頃の万治さんと似てるじゃねえすか。あんたも俺の祖父さんに、よく説教されてた。でも、それは教わるチャンスでもあった。この店には教えてくれる客がいっぱいだ……気心から人生観までもね」
「へっ、三郎さんって、若い頃の万治さんと似てるじゃねえすか。あんたも俺の祖父さんに、よく説教されてた。でも、それは教わるチャンスでもあった。この店には教えてくれる客がいっぱいだ……気心から人生観までもね」
万治が盃を干すと、二人の前に太郎の手が伸びて「みんな、仲間ですから」と酌をした。
「そうみてぇだな。三郎にとっちゃ、あんたたちは、あの頃の俺にとっての銀次郎さんみてえなもんか……よろしく頼むぜ。かぶら寿司みてえに、あいつをうまく発酵させてくれねえか」
「がってんでぇ! 任せてくんなよ」
万治の横顔に祖父を懐かしむ銀平は、思わず力こぶを見せて叫んだ。
かぶら寿司を皿に取り分ける剣が、銀平を冷やかした。
「でも、頭の古い銀平さんは、すぐに酸っぱくなるけどねぇ」
銀平を見知ったテーブル席の客たちが、笑いながらかぶら寿司を頼んだ。
