
津軽の酒造りに生きがいを見つけた、自然大好き派の道産子杜氏
津軽の寡黙な頑固親父をイメージさせる、辛口の“じょっぱり”。その美酒を醸し出す中心人物は、杜氏としては弱冠34歳の河合 貴弘(かわい たかひろ)氏です。
訥々と語る表情に、津軽人らしい素朴な人柄が見え隠れします。ところがインタビューを始めるやいなや、河合 杜氏の口から意外な言葉が飛び出しました。
「私は北海道の岩見沢出身で、実は7年前まで東京でコンピュータのシステムエンジニアをしていました」
しばし、唖然とする筆者!河合 杜氏の津軽訛りからは、大都会で最先端ビジネスをこなしている姿など想像できません。
「北海道のコンピュータ専門学校を卒業して、20歳で上京したのですが、体に染み付いた自然派人間の血が都会には合わなかったようです。7年間、深夜まで仕事に没頭してコンピュータとにらめっこしているうちに、何でこんなことをしてるんだろうと悩むようになりました」
憧れと期待を抱いて上京した河合氏でしたが、現実は過酷でした。広大な北海道で自由闊達に育った彼にしてみれば、雑踏とコンクリートの世界は無機質な空間だったようです。 昼夜なく激務をこなす河合氏は、人生の方途を悩み始めます。
そんな折、青森県出身の女性と出逢い、田舎暮らしについて意気投合。心の拠りどころとなった彼女が実は現在の河合夫人であり、ここから第二の人生が始まったそうです。
「元々、日本酒が大好きでした。東京時代から酒蔵に興味がありまして、いつか働いてみたいなと思い、あれこれと調べていたのです。ところが家内と知り合って、彼女の父親の縁で当時の六花酒造の佐藤 晃司 社長(現・会長)へお話ししてみたところ、二つ返事で引き受けて下さったのです」
青天の霹靂とは言えトントン拍子に事が運び、平成9年(1997)1月、河合氏は六花酒造へ入社。弘前市に一家で暮らすこととなったのです。



7年目ながら、すでに杜氏として製造責任を預かる河合氏。入社4年目には異例の大抜擢で、職人の頭(かしら)を任ぜられています。
しかし、六花酒造の現場は、現在でも季節労働の蔵人によって支えられています。その理由には、津軽らしさを大切にするポリシーが存在していますが、新参者の河合氏にしてみれば、物心両面で相当に気苦労があったことでしょう。
「杜氏が新しい方に変わり、それと同時に頭を命じられました。とにかく、この体制でやるんだと、社長が現場の全員の前で宣言されました。目から鱗、寝耳に水でしたね。3年経ってようやく麹造り助手という半人前だったので、知らないことだらけ。まずは徹底的に訊くこと、体で覚えることを繰り返しました。もちろん、今も同じ気持ちです」
の時のことを昨日のように思い出しますと、顔を赤らめる河合杜氏。
20人もの古株の蔵人や先輩社員たちを飛び越しての重責に、誰とて辟易するのが当然ですが、河合氏を見込んだのは、北村社長でした。


さて、河合杜氏は、南部出身の阿部 隆男(あべ たかお)総杜氏の指導を仰ぎながら、次代の総杜氏としての道を歩んでいます。
そんな河合杜氏に、六花酒造の酒造りとはいかなるものかを訊ねてみました。
「いつ飲んでも飲み飽きしない、家でも料理店でも晩酌として楽しめる素直な酒ですね。その秘訣は、季節職人の方たちと社員が一体となって、昔ながらの津軽らしさ、人間味を大切にしているからだと思います」
近代の津軽の酒造りは、地元のリンゴ農家の人々によって支えられてきたと、河合杜氏は解説します。事実、今回の取材はリンゴの最盛期だったため、まだ酒造り(蔵入り)は始まっておらず、収穫シーズンの終わる11月半ばからのスタートになるそうです。
「リンゴや米を扱う農家の方は、生き物と暮らしているわけです。したがって、我々とは違った視点で毎年の酒造りの課題を見つめていますし、問題点に対応する独自の工夫や知恵を持っています。酒米の良し悪し、精米具合や浸漬の判断にしても、マニュアルとは違う機転が働きますよね。
当社の製造量は吟醸酒・普通酒を合わせて昨年度実績6,000石ですが、そのすべてが季節職人も含めた手造りなのです」特定名称酒以上を手造りにし、上撰クラス以下を機械製造することはいずこの蔵元にも共通していますが、河合杜氏はその全量が手造りであると胸を張ります。
六花酒造の現場では、年間雇用の正社員は河合杜氏を含めて4名。以外の10名は、地元農家出身の熟練した蔵人で構成されているのです。



それでは、麹造り、酵母のこだわりを教えてもらいましょう。
六花酒造では、吟醸酒の場合は総米600kgを基本としています。出麹、切り返し、仲仕事などはもちろん麹蓋による繊細な作業の連続で、76歳の阿部 総 杜氏を筆頭に河合杜氏、職人・社員合わせて8名でこなします。
そして、これにレギュラー酒の仕込みも重なるわけで、広い工場の中で全員が息つく暇なく八面六臂の活躍をしなければなりません。つまり、少数精鋭主義でのコストパフォーマンスも、六花酒造のポリシーなのです。
「出麹までの間は、泊り込みで出来具合を観察しています。やはり、この期間が勝負の分かれ目ですね。一瞬一瞬が緊張の連続ですが、気持ちはとても充実しています。これらの人の経験値と機械設備による分析値を照らし合わせて、初めて納得のいく酒質が完成しますね」
キツイ毎日ですが、東京での暮らしを思い出せばいかに幸せかと、河合杜氏は語ります。麹造りが始まれば、河合杜氏は弘前市内の家には帰らず、阿部 総 杜氏とともに社内へ泊り込むのです。
「早朝の麹のチェックも、結局は二人一緒に起床して行きます。阿部の親爺さんとあ・うんの呼吸、指呼の間でいられることで、自分の技量が着実に向上できていると思います」
また、酵母についても、六花酒造は青森県産に執着を持っています。 「最近、力を入れているのは青森県酵母のイ号、ロ号などの吟醸系酵母ですね。イ号は香り立ちの良い酵母で、新商品の“純米大吟醸じょっぱり華想い”に使っています。ほのかな香りと繊細な味を醸しますね。ロ号は純米酒向きで、幅広い味を醸す旨口タイプに適しています」
酵母の選択についても、河合杜氏と阿部 総杜氏は忌憚なく意見を交換し、決定しているそうです。
孫と祖父のような年齢差の二人ですが、泊まり込みの期間、河合杜氏の“男の手料理”を肴に酌み交わし、尽きることのない酒談義を楽しんでいるそうです。
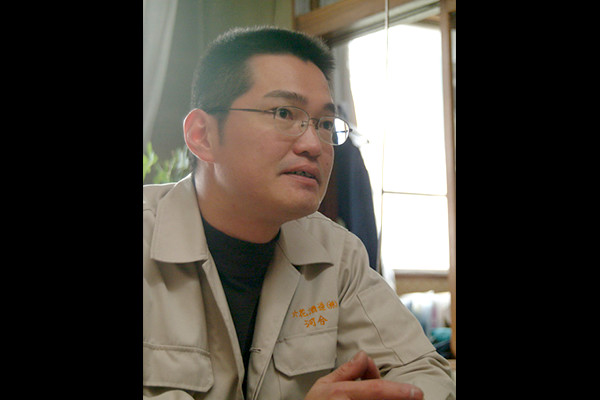



北村 社長の計画にもありましたが、いずれ白神山麓に移転した暁には、六花酒造は清冽無比なる天然水を満々と得ることになるでしょう。
現在のところは、酒質に応じて工場敷地内の地下水を汲み上げ、また白神山系の湧き水を搬入しています。
水質は、みちのく特有の軟水。これが辛口と言えども、硬水系の灘、北陸の辛口酒とは異なる繊細な“じょっぱり”のキレを生み出しているのです。
そして、この地元の水で醗酵させる酒米・陸奥誉(むつほまれ)、華吹雪(はなふぶき)を河合杜氏は痛く気に入っているそうです。
「例えば、全国新酒鑑評会は山田錦の大吟醸のオンパレードなのですが、それは普段飲める酒ではないでしょう。たとえ消費者の口に入るとしても、価格は高騰します。それに、一種の金看板のようなセレモニーになって、ちょっとマンネリ化していますね。もし、全国の地元県産米で造る酒の品評会があれば、イベントとしては目新しく、出品する製品価格も現実的です。今や、何が何でも山田錦の時代ではないと思うのです」
自分自身が愛飲家で、酒の肴も調理するという河合杜氏。日々の晩酌を大切にする彼は「適正価格と上質の味わいこそが、これからは評価される時代」と投げかけてくれました。




それでは最後に、新しいじょっぱりファンを獲得するための抱負とチャレンジを述べてもらいましょう。
「5年後、10年後のファンを掴むためには、今の若い人たちにどんな酒を、どのように飲んでもらうかがポイントです。そのためには、従来の清酒の枠を出た発想が必要ですね。その鍵は女性ユーザーが握っていると思いますが、だからと言って、ウケ狙いのような価値観の見えない製品はダメでしょう。あくまで日本酒として筋が一本通っていながら、そこに現代的なセンスがきちんと現れている製品。上手くは言えませんが、硬くなく柔らか過ぎず、それでいて洗練された味わいの日本酒を造ってみたいですね」
インタビューが進むにつれ硬い表情は消え、河合杜氏は少年のような笑顔を見せてくれました。
「自分が飲んで美味しいと感じる酒を、若い人に飲んでもらえるよう頑張ります」
そう約束してくれた彼にもまた、じょっぱりスピリッツを感じる筆者でした。






