
新生 越の誉を掲げ、”幸せを呼ぶ酒造り”をひたむきに研鑽する!
七代目蔵元の原 吉隆 社長にとって、幼い頃、酒蔵の中は遊び場でした。
麹や酒母の匂いが、体に染み込むほど慣れ親しんだ世界。その歴史ある蔵が瓦礫の山と化した中越沖地震の直後は、筆舌に尽くしがたい心中であったことでしょう。
「無事だった鉄筋社屋から敷地を見渡しましたが、その悲惨な光景に、夢を見ているのではないのかと思いました。と同時に、怒りとも悲しみともつかない感情が押し寄せてきましてね。頭の中はカッカと燃えてくるのですが、胸の内はやけに冷静でした。そして、『こんなことに、負けてたまるか!』という胆力と申しますか、絶対に復活してやるんだと覚悟を決めました」
筆者は、平成19年(2007)7月16日に発生した地震の翌日、報道ニュースで無残な姿を横たえている原酒造の蔵を愕然として見つめていましたが、原社長のみならず社員や蔵人たちにとっても、身を切るより辛い体験だったことでしょう。
それでも原社長は打ちひしがれることなく自らを奮い立たせ、来る日も来る日も社員とともに夥しい瓦礫を撤去し、この年の冬の仕込みに向けて、一心不乱に再生への道を歩みました。「胆斗のごとし」とは、まさにそんな心境を言うのでしょう。
おりしも真夏日のことで、炎天下の作業は過酷を極め、一画の日陰さえ確保できない日々でしたが、ベテラン杜氏から若い社員たちまでが一丸となって励まし合い、汗と涙をぬぐいながら復活の日を目指したのです。
「そのせいでしょうか。今ではスーツよりも、動きやすい制服が板に付いてしまいました(笑)」と、原社長は震災の陰など微塵も感じさせない笑顔を見せます。
奇跡的に助かったタンクの酒は高品質を保ったままで、瓶詰めラインも手を加えれば稼動できる状態。一刻も早く業務を再開することで社員の士気を高め、さらには声援・支援を贈って下さった全国の皆様に応えたかったと、原社長は力を込めて語ってくれます。
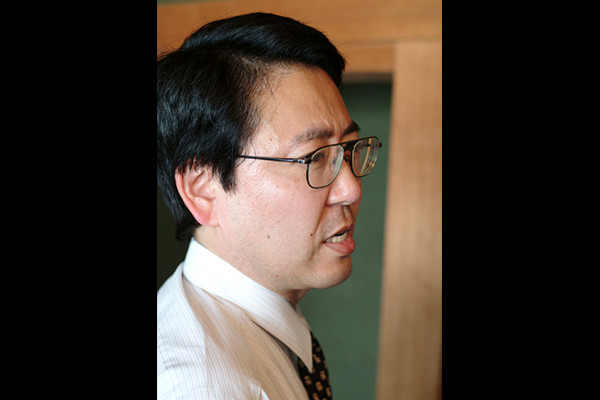


「そして不幸中の幸いだったのは、月曜日にも関わらず、社員の事故が皆無だったことです。本来なら営業日ですし、発生した10時13分は誰かが蔵の中にいてもおかしくない時間帯です。偶然にも、当社はその日を“ハッピーマンデー”という休業日にしていたのですよ。しかし、それでも誰か出勤してたのではないかと気が騒ぎ、まずは人命第一と、私と執行部のメンバーで手分けして崩れかけている蔵の中を見て回りました。不気味な余震が続いて冷や汗物でしたが、人身事故は一切なく、胸を撫で下ろしたのです」
原社長が次々と閲覧してくれる記録写真……地震の凄まじさを物語るカットに、しばし筆者は呆然と固まってしまいます。
この状況から、よくぞ年内の醸造に挑戦されたものと訊ねてみると、原社長は笑顔をほころばせて答えてくれました。
「まず精米機が壊れていなかったことに、感謝しましたね。若干の調整で、正常に動きました。そして、生産管理システムの心臓部であるIT機器やデータも、無事でした。麹室は本来3つの品質に分けて配備していたのですが、これが被害を受けました。ただ、冬までには時間があるので臨時の室を設置することは可能でした。最も心配したのは、水です。やはり原料処理ができなければ、酒造りは始まりません。地震後はもちろん水道も寸断されてましたし、復旧の目途は立っていなかったのですが、これも幸運なことに、10日ほどで当社には水が通じたのです。柏崎市内は意外に早い復旧でした」
現在、壊れた瓦礫は撤去され、敷地内には仮設プレハブの貯蔵庫や倉庫が立ち並んでいます。そして、無事だった鉄筋社屋の一室には、原社長から若手社員までが一つになって勤しんでいます。
「私の社長室も、キレイさっぱり無くなりました(笑)。でも、このファミリーなムードが、なかなか新鮮でしてね。社員同士、さらに気持ちが通じ合うようになっています」
“災い転じて福となる”、そんな諺にふさわしい明るい雰囲気が、これからの原酒造の未来を物語っているようです。


さて、震災の話題はそろそろ置き、原社長の経営哲学についてインタビューしましょう。
今、清酒業界は停滞気味だが、飲食の嗜好性がますます多様化してきたことで、幅広く料理に合う日本酒が見直されつつあると原社長は言います。その洞察も含め、現在の業界の課題と原酒造の方針を訊いてみました。
「年々、廃業・倒産などで蔵元が減少していますが、ある程度の淘汰はやむを得ないと思います。生き残りたい酒造会社は、流れに従うのでなく、自らさまざまな手を尽くして勝たねばならない時代です。つまり、フォロワーではいけない。チャレンジャーかニッチャーを目指すべきでしょう。これだけニーズが多様化し、アルコール商品があふれますと、昔のような右肩上がりの景気任せ、ルートセールス一筋の時代はもう帰ってきません」
例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで売りのステージがさらに広がって、日本酒は食品の一部になったと原 社長は指摘します。だから、酒質や価格が細かく差別化され、それぞれの蔵元がより主張を持った製品を造ることができると提言します。
「そのためには、まず製造部門をしっかりと固め、メーカーとして磐石な力を持つことです。まずは、高い品質と正確な技術の確保ですね。自らもお客様も『うん! これが越の誉だ』と賞賛できる商品を造り続ける力。つまり、完成度の徹底的な追求ですね。それが、当社の理念である“幸せを呼ぶ酒造り”につながるのです」

ところで、越の誉の酒は淡麗な味わいが基本です。スッキリとした中にも、ふくらみのある味わい。それを生かしつつ、さまざまなバリエーションの製品を醸していると、原 社長は5品の酒を試飲させてくれました。
芳醇な熟成酒タイプの純米大吟醸「もろはく」、旨味があって食中酒にピッタリの「特別純米酒」、女性をターゲットにした低たんぱく米のヘルシーな純米酒「初摘み春陽」など、どれを味見しても、丁寧な造りと繊細な喉ごしを感じました。
「私は、商品開発こそが蔵元の使命だと思っています。当社は早い時期から失敗を繰り返しながら、新しい製品を開発してきました。とにかくやってみる、チャレンジすることを、父や祖父もモットーにしていました。半世紀前からの研鑽の積み重ねが、これらの個性的な商品として現れているのです」
原 社長は「もろはく」を手に取り、その開発について解説します。
「もろはくは昭和52年(1977)に発売した、常温8年貯蔵の純米大吟醸です。当時は地酒ブームの走りでしたが、こんな酒は極めてマニアックで、特定の方に好まれてもヒット商品にはならない時代でした。しかし、このような取り組みが、現在の商品開発力の礎になっているのです。父の寛は『酒の熟成を徹底的に研究しろ。そのためならタンク1本、2本の酒が無駄になっても構わん』と現場に指示しました。熟成酒は難しく、現場の努力も徒労に終わる日々が続きました。しかし、このあくなき挑戦によって“もろはく”が誕生したのですが、それは必然の結果であったと私は思います」


それでは、多様化するアルコール需要を考える上で、今“日本酒離れ”と言われている若い世代のニーズを、原酒造はどのように捉えるのでしょうか。
「まずは、各蔵元が個性化に進んで取り組むことですね。個性化するということは、それだけ他社との違いをアピールする必要があります。そうすることで、ニーズやブームの先にあることを考えたり、創ったりしますね。これが、従来の蔵元に足りない商品開発力。つまりはマーケティング力です。そして、業界を挙げて若い方への情報発信を行なうべきですね。中央の組織やアソシーエーションが中心となることで、“日本酒のかっこ良さ”なんかも創り出せると思うのです。また、最近の海外での日本食と清酒のブームも、若い方には魅力となるはず。輸出も当社は早くから手がけており、現在は台湾・中国が好調。アメリカも上向いています。きっかけとなるのは、やはり食とのマッチングですね。寿司文化は若干アレンジされましたが、みごとにアメリカに定着しましたから、日本酒にもチャンスは十分あると思っています」
日本酒の海外輸出は、業界全体としてようやくビジネス的に取り組めるようになってきたところと、原 社長は読んでいます。
ちなみに、越の誉は全日空国際線のファーストクラス機内食に使用され、外国人ゲストにも好評です。以前、同じく扱われる数社の蔵元と全日空社員とのパーティーが催され、その席上、越の誉が一番人気であったことから、原 社長にスピーチ役が回ってきたそうです。

最後に、自身へのスローガンを一言とお願いすれば「再生ではなく、新生した“越の誉”ですから、一歩一歩しっかりとチャレンジしていきたいですね。いつも丁寧に、ひたむきに」と原社長は胸を張って締め括ってくれました。
メーカーとしての誇りをかけた、たゆみなき技術研鑽と商品開発。震災という苦難を乗り越え、今一度、その哲理を追求して行く。そこに原酒造のモットーである“幸せを呼ぶ酒造り”が、再び誕生する。
「今回ほど、当社の社員を誇りに思い、惚れ直したことはありません。ですから、私も彼らに応えるべく、まだまだ、これからが勝負です」
ほがらかな笑顔を絶やさない原社長は、さらに美味しい越の誉を求めてやまないようです。






