8月に入ったとたん、真夏日を待ちわびていたかのように、公園では蝉の大合唱が始まった。
あまりにぐずついて、気象庁もあたふたとした今年の梅雨明けだったが、マチコの通りはようやく夏の風景に彩られている。
八百屋の店先にはいつもの年と同じように濡れ縁が置かれ、夕涼みのご隠居さんたちがチラホラと集まっていた。
「あ~! もう、こんな時間。お店開けなきゃ」
5時10分前を指す柱時計に、カウンター席で遅ればせながら暑中見舞いを書いているマチコは焦った。
「あ~あ、さっさと出さなきゃ残暑見舞いになっちゃうよ。暖簾と提灯は俺がやっとくから、書いちまいなよ」
半分開いた格子戸から、額に汗した澤井が覗きこんでいた。
「打ち水は、僕がやるから」と、擦りガラス越しに松村が手を振った。
「そう! じゃあ、お言葉に甘えさせてもらうね」
残り数枚のハガキに、真知子は筆ペンを走らせた。
段取りを終えた澤井と松村が席に着くと時計の鐘は5時を叩き、それと同時に一人の若い男が入って来た。20歳半ばらしき男は、野暮ったいTシャツとGパン姿だった。
初顔の客に真知子はそのまま書いているわけにもいかず、「いらっしゃい」と席を立ち、おしぼりを出した。
松村から一席置いて座った男は「酒をぬる燗で。それとメザシ」と注文すると、ペットボトルを手元に置いた。
見たところ何の変哲もない、水が入ったボトルのようだった。
「こう暑いと、水分補給は大事ですね~」
よそよそしいのも妙なので、松村は男に愛想言葉を投げてみた。
しかし、男は松村を見返しもせず「ただの癖です」とぶっきらぼうに答えた。
「な、何でぇ……」
松村はおもしろくなさげにつぶやくと、席を立って、もう乾いてしまった玄関先に水を撒きに行こうとした。
「今頃から打ち水するなんて、もったいない。もっと陽が落ちて、風が出てからですよ」
男の声に、柄杓とバケツを持ちかけた松村の手が止まった。
松村は若僧に冷や水を浴びせられたような気分になり、振り向いた顔にはありありと怒りが込み上げていた。
「あのな! 俺は、この店の常連なんだよ。あんたみたいな新参者にとやかく言われる筋合いはねえの。分かったら、黙ってろ! こちとら、毎日暑くって虫の居所が悪いんだ!」
いつにない松村の剣幕に、澤井が目を丸くして言った。
「おいおい! 落ち着けよ。お客さんも、たかが打ち水じゃないすか」
すると今度は、客の男が澤井の言葉に強く反応した。
「たかが!? たかがじゃないですよ。水は大切な資源でしょう。そんなことを言ってる連中が多いから、環境破壊が進んじゃうんですよ」
「連中? 連中たぁ、誰のこと言ってんだよ!」と澤井が顔色を変えた。
こうなると、もはや水掛け論で、お互いを非難する声が飛び交ってしまう。
そのようすに腕組んでいた真知子が、ついに鶴の一声を上げた。
「いいかげんにしなよ! 男三人がちっちゃなことで、暑苦しいったらありゃしないわ。みんな、おもてのバケツの水で頭冷やしといで! あんた、それすらもったいないって言うのなら、とっとと帰ってちょうだい。御代はいらないよ!」
店内が、水を撒いたように静まりかえった。
松村と澤井は「す、すみません」としおらしく詫びたが、若い男はうつむいたままだった。
真知子は、口をつぐむ男にぬる燗のお銚子を傾けた。
「……確かに、あなたの言うことは正しいわよ。だけど、もう少し、言い方ってもんがあるんじゃないの?」
男は盃に手を出しかけて、引っ込めた。
「す、すみません。そう言う性分なもんで。僕、昔から人と話すのが苦手で、ヘンコツ者って言われました。そんなつもりはないのに、いざ口を開くと、人を怒らせたり、神経を逆なでするような口調になるんです。気がつくと、そう言ってしまっている。元々、不器用なもので……」
盃を持つべきか、持つまいか、まだ指先をおずおずとさせている男に真知子はクスッとほほ笑んだ。
「あなた、生真面目なのね。お名前は?」
「……水守です」
聞き取りにくい小声で答えた男に、松村が眉をしかめてつぶやいた。
「へっ、水漏れ?」
「ちっ、ちがいます! 水守ですよ! あっ……すみません。また、やっちゃった」
松村が呆れ顔でため息をつくと、横に座る澤井が「まあまあ、力を抜いて」と水守の肩を揉んでやった。
「そのお名前、この水と関係ありそうね」
真知子が、水守のペットボトルを見つめた。
「……僕は、熊本の小さな町の出身で、今は都内の機械メーカーで働いてます。田舎は東京都と正反対で、自然がいっぱい。湧き水が豊かな町で、それしか観光資源はないんです。僕の家は、代々、その町の水守りを司っていました。今も実家には古い井戸があって、ほとんど使ってはいませんが、大事に守り続けています。でも最近、心無い旅行者たちが町の川や泉を汚してばかりいるらしくて……この水は、町の泉の水なんです。毎週、おふくろに頼んで送ってもらってるんです。水のありがたみを、忘れないためにも」
「水守君。あなた、ちゃんと素敵な話しができるじゃないの。人の体って7割が水分だから、そんな良い水の話は誰にだって伝わるんじゃないかしら」
「えっ……そうですね、ほんとだ。今までこんなこと、会社の人間にも話したことなかったです」
澤井がふ~んと感心し、ペットボトルを手にして言った。
「俺もけっこう知ってるんだぜ、水のこと。水はちゃんと命を持ってるんだって。それでね、きれいな言葉や音楽を聞かせてあげると、もっと美味しくって清らかな水になるそうだよ。酒蔵もそれをやってる所があるんだぜ」
「えっ! そうなんですか!」と水守がうれしげに目を丸めると、松村も口を開いて、ひとしきり水談義が続いていった。
「ねえ……その水。今度来る時に、ごちそうしてくれないかな」
真知子が透き通ったペットボトルを、店の灯りにかざして言った。
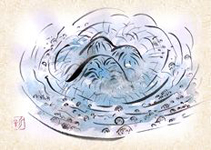 「もちろん! 女将さん、もっとキレイになりますよ」
「もちろん! 女将さん、もっとキレイになりますよ」
「おっと~♪ いきなり口がうまくなり過ぎじゃねえか」
澤井のツッコミに水守は頬を赤らめつつ、満面に喜びを浮かべていた。
「あのさ、俺にも1本もらえっかな。今日のことは水に流してさ! ね!」
松村が手をすりすりして水守に頼むと、真知子がひと言、水を差した。
「和也君は、なかなか流れないわよ。都会暮らしで、よどんでるからねえ~」
ペットボトルの水は、4人の笑い声にひときわ澄んでいるようだった。
