強い北風が、マチコの通りに初雪を散らせていた。玄関先には、小さな白い粒が吹き溜まっている。
マフラーやコートの襟に首をうずめる男たちが、格子戸を開け閉めするたび、その雪粒が店内にコロコロと転がっては消えた。
カウンターやテーブル席には燗した徳利が並んで、ほとんど満席だった。
夕刻、ふと東京タワーに昇ってみたと言う澤井が「灰色に吹雪く町を見ててさ。あの夏の猛暑をすっかり忘れてんだよね。働きづめで季節感もない暮らしって、何だか切ないねえ」と、カウンター席でブルッと背中を震わせた。
「それって、単に歳のせいじゃない? 澤井さん、寒いならステテコ履いた方がいいよ」
燗酒で頬を赤らめている隣の松村が、ニンマリとして皮肉った。
「うるせ~な。俺がボケてるって言いたいのか。お前こそいい歳して、いつまでもダテの薄着してんじゃねえよ。去年のクリスマス、泥酔してカミさんに放り出されて、大熱出したの、どこの誰だっけ?」
澤井の切り返しに、カウンターの端に座る青年がクスクス笑うと、今度はまともに赤面した松村が叫んだ。
「大きなお世話だよ、ほっといてくれよ! 広告マンにはトレンドさが必要なんだよ」
今にも言い合いの始まりそうな2人の前に、「ストップ! どっちにしても、若い人から見れば、身も心も寒いオジサンたちなんだからね。まずは、これを食べる!」と、真知子がグツグツと煮える土鍋を置いた。
鶏だんごや蟹の入った美味しそうな鍋に、澤井と松村は鼻息をゆるめ、しぶしぶ箸を持った。薬味はマチコ自家製の柚子胡椒で、何とも言えない爽やかな香りがしていた。
「おほう~! こりゃ、うまそうだねえ。真知子さん、私にも一つお願いしますよ」
その鍋の湯気越しに、宮部の笑顔が見えた。
「あら宮さん、いらっしゃい。じゃあ、3人分にすればよかったわ。あいにく、大きい土鍋しかなくて……」
真知子が申し訳なさそうに答えた途端、「わしも追加や! ほんならイケるやろ」と津田の鬚面がにゅっと現れた。
宮部の登場でカウンターは満員だったが、タイミング良く「女将さん、ごちそうさまでした!」と隅にいた青年が席を立った。
「あら、料理もお酒も残して。気を遣わなくてもいいのよ。少しずつ詰めれば、大丈夫なんだから」
真知子の声に、宮部が「そうそう。あっ、良かったらいっしょに鍋食べませんか?」と誘い、津田もニッコリとして同意を示した。
「あっ、ありがとうございます。でも、せっかくなんですが、ちょっと帰ってやらなきゃなんないことがあるのです。ご好意だけ頂いて、また今度ゆっくりとご相伴にあずかります」
清廉潔白そうな雰囲気の青年は、少し訛りのある言葉で答えた。キラキラとした目が、津田の顔をじっと凝視していた。
彼の丁寧なおじぎに、津田が「うむ」と感心したような顔で頷いた。
青年が勘定をして出て行くと「今時の若いもんにしては、えらい律儀というか、ようでけとるなあ。久々に気持ちのええ子や」と、津田が心地良さそうに盃を飲み干した。
「彼って、新顔だね。初めて?」
澤井がハフハフと鶏だんごを頬ばりながら、真知子に訊いた。
「ええ、小1時間前に来てね。日本酒は初心者ですとか言って、芋焼酎を最初に飲んでたの。たぶん……」
「たぶん、何なのさ?」
憶測している真知子に、松村が訊ねた。
「あの訛り……鹿児島か宮崎だと思うの。私の上京した頃と似てるもの」
ちょっとうれしげな表情の真知子に「ふ~ん」と松村と澤井が口を揃えた時、「これ、何だろ?」と宮部がカウンターの隅にあった小さな箱を手にした。
古めいた色使いの箱には、ミカンのような絵と大きなカタカナが書かれてあった。
「鹿児島名物のボンタン飴やないか。懐かしいなあ」
室温でくもった眼鏡をハンカチで拭きながら、津田がつぶやいた。
「となると、真知子さんの推察からして、さっきの彼の忘れ物だな」
宮部はそう言って、ボンタン飴の箱を手の中で転がした。すると、箱とセロファン袋の間に、紙切れが挟まれていた。
宮部と津田は顔を見合わせ、その紙を取り出した。
それは、小さく折りたたまれた1枚の便箋だった。
耕治へ
正月には、帰っておいで。
あんたが東京へ行って、もう3年になる。最初は父ちゃん「あのバカタレは、もう、ワシの子やなか」と言うちょったが、先月、あんたが毎月、私に送っちょった手紙を読んで、涙ぐんでたよ。
4年前、母ちゃんが亡くなってから、父ちゃんは家事を背負うた私にすまんと思うちょった。だから耕治には、私を支えてほしかったんじゃね。
けどね。父ちゃん、あんたの手紙を読んで、わがままで出て行ったのやなしに、自分の夢を叶えようとしてることや、私にいつも申し訳ないと思うちょることを知った。
こいは……このボンタン飴は、父ちゃんからの手紙じゃ。
あんた、昔、いつも父ちゃんに甘えて、買うてもろうてたね。
きっと照れ臭いんじゃね、あんたに手紙を書くのが。
じゃから耕治。父ちゃんに、返事をあげてちょうだい。
そして、きっと帰って来なさいね。
たった一人の姉 由美子より
小声で読んでいた宮部の指が震え、津田はふうっと深いため息を吐いた。
真知子は前掛けで目頭を押さえ、澤井はうつむき、カウンター席の客たちもしんと静まっていた。
「……彼、手紙を書きに帰ったんやろな。もうその事だけで、胸がいっぱいだったやろう」
津田の声が、しんみりと響いた。
「そう……そして、津田さんに、お父さんの姿を想ったんだよ。だから、あんなに見つめてたんだ」
目を真っ赤にする澤井が、鼻声で言った。
その時、顔を腕でぬぐった松村が宮部から手紙とボンタン飴を奪い、「必ず、見つけるよ!」と叫んで、飛び出して行った。
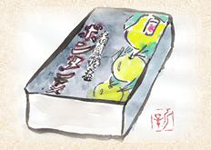 何が起こったのかとテーブル席の客が茫然とする中、澤井が松村の出て行った格子戸を見つめ、顔をクシャクシャにして言った。
何が起こったのかとテーブル席の客が茫然とする中、澤井が松村の出て行った格子戸を見つめ、顔をクシャクシャにして言った。
「あいつ……薄着のまま行きやがって。また風邪引いちまうぞ……やっぱり、根はバカ正直な関西人だよ」
「まあ、ええやないか……関西には、アンポンタンちゅうのがおってな」
タバコに火を点け、うまそうに吸いこむ津田の眼鏡に、マチコの泣き笑い顔が揺れていた。
