おでんや鍋焼きうどんの幟が新橋の繁華街にはためくようになり、外国人観光客が殺到しているとスポーツ新聞が報じていた。欧米で注目されているカツオや昆布の旨味ダシを、彼らは欲しがった。
それはポンバル太郎でも同じで、おぼつかない箸使いでアラ鍋をつつく外国人がテーブル席に座っていた。夫婦とおぼしきカップルは日本酒ファンらしく、冷蔵ケースに並ぶレッテルを目にした途端、興奮を隠せないようすで太郎に5種類の銘柄を注文した。
冷酒グラスを舐めながらプリップリのアラの白身へ驚く夫婦に、九州出身の手越マリがぶつ切りの英単語をつなげている。
天然物のアラを納めたカウンター席の日野銀平は、まんざらでもない顔で純米酒のぬる燗を傾けていたが、マリのお節介へよせばいいのにと言いたげなしかめっ面を見せた。
隣の平 仁兵衛は、マリの身振り手振りの英語に目尻をほころばせている。
「銀平、アラは英語ではどげん言うとね?」
「アラは、クエだろ……ちがった。そりゃ、日本語だ。ええい、俺にめんどくせえことを訊くんじゃねえよ」
マリの問いかけをはぐらかす銀平の後ろから、たどたどしい日本語が飛んで来た。
「銀平さん、ハタはグルーパー。ニューヨークでは、イタリア系の人たちがバターソティとか、オリーブオイルでフライにして食べます」
外の寒風に首をすくめて登場したジョージは、夫婦へアラ鍋の解説を英語で始めた。短髪ブロンドの中年男性は、ジョージに根掘り葉掘り問いかけ、鍋ダシやアラの身を何度も確かめるように口にした。
太郎は男の風貌に、料理人の雰囲気を感じた。
博多のアラ鍋は相撲レスラーの好物と伝えるジョージに、平が嬉しげに「上手い表現ですねぇ」とつぶやいた。
カツオの本枯れ節と利尻昆布を使った鍋ダシの匂いに、マリの腹の虫が鳴った。
「なるほどねぇ、国が変われば食べ方もちがって、おもしろかねぇ。ばってん、九州育ちの私はアラに飽き飽きしとるけん。太郎ちゃん、うまか鍋ば、他になかとね?」
高級魚のアラに飽きたと見栄を張るマリに、銀平が舌打ちした。
「けっ! アラはアラでも、骨ばっかりのアラの方じゃねえのか?」
「なんば、言いよっとね! そっちのアラは、魚屋のあんたが得意じゃなかね!」
売り言葉に買い言葉の二人に、ジョージと夫婦があんぐりとした時、玄関の鳴子が音を立てた。雪駄の尻金の音が、チャリンと店内に響いた。
「太郎ちゃん、お約束の物を持って来たでぇ。ああ、この御仁はわしの先輩で、多門三郎はんや」
和装の中之島哲男が、皺だらけの顔をした老人を連れていた。地味なジャンパーとジーンズ姿のしょぼくれた多門は、恰幅のいい中之島の着物姿と対照的だった。
中之島がビニール袋をカウンターに置くと、中から白い物がふわりと宙に浮いた。それはゆっくりと、言い争うマリと銀平の間へ舞い落ちた。
「あら、この羽根は……雉じゃなかね」
「その通り! 昨日、木曽福島の森で捕れた野生の雉や。こいつで、うまい雉鍋を太郎ちゃんに作ってもらおうっちゅうわけや」
藍染めの和服をまとった中之島に、夫婦の妻が一緒に写真を撮りたいとジョージにせがんだ。
それを察した中之島が、破顔一笑して「オーケー! オーケー!」と連発すると、連れの多門は静かにカウンター席へ座った。
「あ~あ、マリさんと五十歩百歩な英語だぜ。けどよう、その雉鍋はご相伴に与りてぇなぁ」
銀平は中之島を茶化しながらも、雉鍋と聞いて舌なめずりをした。
「あんた、調子が良すぎるばい。そもそも、鍋を頼んだのは私たい。あんたには、やらんけんね」
またぞろ始まりかけた悶着に、太郎が「よさねえか!」と声を上げた時、夫婦の主人が青い目で訝しげに中之島を見つめた。そして、ジョージから野生の雉肉を持って来たことを聞くと、両手を広げ、うんざり顔で英語を捲し立てた。
キョトンとしている常連たちに、ジョージが気まずげに通訳をした。
「彼は、ロンドンでレストランのシェフをしている、マイク・レスターさん。でも、雉肉は信用できないそうです。イギリスでは養殖した雉を建物の上から投げ、それを猟銃で撃って、狩猟された野生の雉に見せかける業者が多いそうです」
マイクは、ひたすら撃って落とした大量の養殖雉が、野生と偽って何倍もの値段で売られていると苦い顔をした。
黙って聞いていた多門の指が、ピクリと動いた。やけに太い指先が、太郎は気になった。
「おいおい、そりゃ失礼だろ! 中之島の師匠が、偽物の雉を持って来るわきゃねえ。ジョージ、そこん所をキッチリ伝えろい!」
酔った勢いで口を尖らせる銀平にマイクの妻が早口な英語で言い返すと、マリも「あんた、黙りんしゃい!」と、今しがた世話を焼いた時とは表情を一変させた。
不穏な動きのカウンター席へ奥テーブルの客が眉をしかめると、中之島の野太い声が響いた。
「ジョージ、かめへん。マイクはんにも、雉鍋をふるもうてあげようやないか。そしたらこの雉がどんな代物が、シェフなら判るはずや」
自信ありげな中之島が目顔で雉をさばくように伝えると、太郎は袋から肉の塊を取り出した。大きく開いた太郎の目に、一発の弾痕すらない雉肉が映った。
もう一度、多門の指先へ釘づけになる太郎に、中之島はしたり顔をほころばせた。
つかの間、鍋の煮える音が聞こえ、湯気の中に味噌ダシと雉特有の脂っこい匂いが漂った。マイクの鼻先がひくついて、疑念を浮かべていた顔つきが引き締まった。
鍋ダシの黄色い脂は天然物の雉肉の証しで、中之島はすかさず冷蔵庫から木曽福島の純米酒を取り出した。
「うへぇ! こりゃ、たまんねえコンビだぜ」
「私も子どもの頃、熊本の山で捕れた雉ば食べたばい。あの時と同じ、いい匂いがしとると」
二人の言葉に頷く平は、待ちきれずに、もうレンゲでダシを啜っている。
恐る恐る鍋を見つめていたマイクは、銀平とマリが大ぶりに切った雉肉を口にすると、「オウ! ビ ケァフル!」と叫んだ。しかし、気を付けるどころか、常連たちは黙々と雉肉を食らい、ダシを飲んでいる。
茫然としているマイクの前に、中之島が純米酒の一升瓶を置いた。
「イッツ ノット ビ ショット。あんさんが心配してるような散弾銃では、打ってないで。雉肉の中に、鉛玉は残ってへんのや」
ジョージへ中之島が顎を振って、通訳しろと命じた。それを伝えるジョージも、撃たれていない理由に首を傾げた。すると、太郎がマイクたちの前に冷酒グラスを置きながら、口を開いた
「これは、トラップ ハンティング。日本の猟師は、昔から罠を仕掛けるのが得意だった。できるだけ獲物の肉を傷つけずに捕まえたんだ。銃で撃つと弾の当たった部分から血が広がって、肉が臭くてまずくなるのを知っていた。それに赤ワインのように酸味が強い酒は、血が混じった肉に負けないが、日本酒は血の臭いに負けてしまう」
ジョージの英訳を聞いているマイクが何度も頷くと、中之島はグラスへ純米酒を注いだ。
「これは、かなりボディが効いてるゴツイ味の山国の純米酒や。そやから、野生の鳥や獣の肉にも合わせられる」
マイクは中之島を振り返ると、「ゴメンナサイ」と自分の思い込みと非礼を詫びた。そしてジョージに、通訳してくれと長い言葉を続けた。
ひとしきりしゃべったマイクに、笑顔のジョージが親指を立てた。
「中之島さん。マイクさんはこの雉の猟師を、ぜひ紹介して欲しいそうです。そして、どうにかして、冷凍でロンドンまで送れないだろうかと訊いています」
「さぁて、どうしたもんでっしゃろ、多門はん。ぎょうさん雉を捕るとなれば、罠の仕掛けは心配ないとしても、血抜きと肉を洗うのんが多門はん一人ではしんどいですな」
腕ぐむ中之島が、多門の隣へ座った。
あんぐりとしている銀平とマリの横で、平が赤らんだ表情を崩した。
「やはり、そうでしたか。多門さんの発しているオーラ、只者ではないと思ったんですよ。ねぇ、太郎さん」
太郎は頷きながら、マイクへ言った。
「この年配の方が、猟師さんですよ。罠を仕掛ける太い指先、見せてもらえばいい。日本の猟師のスゴさが判るはずです」
太郎の視線を追ったマイク夫婦が太い指先に驚きと尊敬のまなざしを送ると、はにかむ多門は白髪頭を掻いてつぶやいた。
「50年間、罠を作り続けてきました。カズラやツタを使う罠は、年寄りでも仕掛けられるんです。それは、老いて一人になっても食っていけるように考えた山の民の知恵なんですよ……こんな老いぼれの仕事が役に立つのなら、村の若い者にも手伝わせますよ。ただし、その雉鍋とわしの暮らす木曽福島の酒を、マイクさんが好きになってくれたらの話ですがね」
ジョージが訳すると、マイクたちは揃って立ち上がり、多門へ握手を求めた。太い多門の指先に、二人は再び声を上げた。
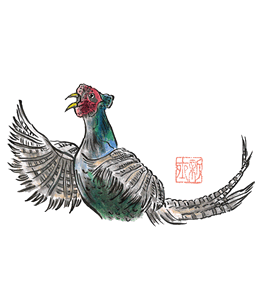
「最後の最後まで多門さんの正体をばらさないなんて、中之島の師匠、憎い仕掛けじゃねえですか」
雉肉の歯ごたえと旨味に目を丸くする銀平が褒めそやすと、中之島も太郎へ鍋を注文した。
「その罠に銀平ちゃんは、まんまと引っかかりよった」
「おめえは単純だから、すぐに騙されるタイプだしな」
中之島と太郎がたしなめる銀平に、マリも追い打ちをかけた。
「だいたい、あんたは憎まれ口ばっかり叩くから、こうしていじめられるとよ。“雉も鳴かずば、撃たれまい”たい」
その諺は英訳するのが難しいとばかり頭を捻るジョージに、銀平が八つ当たりした。
「いつまで、通訳をやってんだよ!」
「オウ! 私の雉鍋ができあがるまでね! それまで、罠にハマりやすい銀平さんの紹介をマイクさんへしますよ」
雉鍋の濃厚な湯気が、客たちの笑い声を包んでいた。
