日本橋や渋谷のデパートでは御歳暮の早割注文が歳末商戦の始まりを告げ、銀座を行き交う人波にコート姿を見かける季節になっていた。
暖冬の予報は、当て外れの感がある。
ポンバル太郎の店内も、ひやおろしの燗酒に温もった客たちの笑顔が揺れている。2時間前から飲んでいる平 仁兵衛の鼻っ柱は、すでに真っ赤である。
今年のひやおろしはそろそろ品切れで、テーブル席から新酒はまだかと気の早い声も聞こえた。
そんな客たちと同様に、火野銀平がカウンターの中央に置かれた物に視線を止めた。
「太郎さん、麹米かよ? これ、どうしたの?」
茶色い木箱へ山盛りになっているのは、酒を仕込む麹米である。白くふくらんだ米粒からは、ほのかに甘い香りが漂っていた。
「ちょっとした座興にって、岐阜県の蔵元さんが送ってくれたんだよ。この麹蓋ごとな」
平成27byの酒造りが始まったばかりの蔵元は、ちょうど麹米や酒母の仕込みの時期で、お待たせしている得意先にこの粋な計らいをしているらしいと、太郎は麹米を手で握った。
麹蓋に落ちる米粒の音に、カウンターの隅に座る白髪交じりの男がほうば味噌の田楽をつまむ箸を止め、目を鋭くした。そのようすに平が気づいた時、玄関の鳴子に混じって声が聞こえた。
「それって、面白いですね。いろんな種類の酒造好適米の麹米を揃えてお客さんにひと口食べてもらうってのも、いいかも知れませんよ」
テーブル席の客たちがふり向くと、現れた右近龍二は脇目もふらず麹蓋へまっすぐ歩み寄った。まるで蔵元見学へ行ったかのように、興奮している。
そして、しげしげと麹蓋を見つめて「年季の入ったヘギですね」と太郎へつぶやいた。
聞き慣れない“ヘギ”に客たちは小首をかしげ、銀平も「ヘギってのは、何でぇ?」と問いかけた。
あいかわらず不勉強な銀平に太郎が飽きれ顔で答えようとした時、カウンターの隅から芯の通った声がした。
「へぎは、杉の幹を一枚一枚、手でへぐ、つまり剥いだ板です。ノコギリやカンナが生まれる前からあった、原始的な木工技術なんですよ」
六十路半ばと見える男の目尻が、麹蓋を愛しむようにほころんでいた。声の張りとは対照的に皺深い右手が、奥飛騨の地酒の盃をあおった。
太郎はうつむき気味だった男の面ざしに、はっと表情を変えた。手のひらからこぼれた麹米が、カウンターでパラパラと跳ねた。
「あなたは……現代の名工の高山真吾さん。日本で二人しか残っていない、へぎ職人ですよね。飛騨の蔵元に飾っている写真で、以前、拝見しました」
珍しく動揺を隠せない太郎に、龍二や銀平だけでなく、他の客たちも男の顔を背伸びして見つめた。
つかの間、高山は曇った表情で口を結んでいたが、麹蓋に手を伸ばすと杉板の柾目を食い入るように見つめ、問わず語った。
「大した者じゃありません。一介の木地師ですよ。そろそろ手先も目もおぼつかなくなってきました。でも元気な内に、へぎのことを皆さんに知っておいて頂ければ幸いです」
へぎは、麹蓋だけではなく、家具や卓、大きな物では天井板にも使われた。木を割くことは、原木を加工する一番シンプルな技で、落雷が樹木を裂いた跡に人は学んだそうである。木の繊維を壊さず、道具で切ったり削ったりしないで、厚さ1ミリ以下まで均等に薄い板に裂くのだと、高山は両手で幹を剥ぐ仕草を見せた。
真剣なまなざしで聞く客たちに高山は幾分やわらいだ表情だったが、ひとしきり話すと肩を落とした。
「しかし、木曽でも天然木が少なくなりヘギ板に適した木を入手するのが、難しくなっています。今の材料は“ネズコ”。別名、黒部(くろべ)とも言います、昔は天然杉を使いましたが、適した木がなくなって代用に黒部を使うようになりました。だから、黒部杉と呼ぶ人もいます。しかし、ネズコはあくまで代替品。やはり天然杉がいいんです。特に、日本酒の麹米を振る蓋には、なぜか杉がいい。そもそも酒の桶や道具に杉が使われていたのも、相性がいいからでしょうね……残念ですが、天然杉のヘギも麹蓋も、私と同じで、消えていく身です」
客たちの口から、ため息とも諦めともつかない音が洩れた。誰も言葉を発しない中、平は高山の隣へ席を移すと、麹蓋をクルリと回した。
何事かと顔を見合わせた龍二と銀平が、「おお!」と叫ぶ高山へ振り向いた。
麹蓋の横っ腹に、古めかしい“焼き印が刻まれていた。片側だけの焼き印は、高山からは見えなかった。
「確か、高山さんの雅号は“杉人(すぎと)”でしたね。この意匠、あなたの物でしょう」
震える高山の指先が、焼き印に重なった。見えにくいが、焦げた杉と人の字が木目に浮いている。
「まさか、再会できるとは。この麹蓋は、私が初めて拵えたへぎ作品です。ほら、この焼き印の下に、“四五たかやま”と刻んでます。私が中学を卒業して、修行3年目に作った昭和45年当時の物……であれば、この飛騨酒の蔵元の注文で拵えた麹蓋ですね」
「ええ、まさに今、高山さんが召し上がっている酒の蔵元から頂戴しました。蔵元は、私におっしゃいましたよ。麹蓋一つで、酒の味は変わる。機械で杉を切るのではなく、人の手で裂くへぎ板には杉の命が宿るんだと。それが麹米の命と結びついて、素晴らしい味の日本酒が生まれるってね」
高山は山出しの男らしく、素直にウンウンと頷きながら目頭を赤くした。
平がジャケットの内ポケットへ手を忍ばせた。ハンカチを取り出して高山に渡すのだろうと銀平は察したが、現れたのは折り畳まれた小さな布だった。
「高山さん、これ、私のお守りなんですけどねぇ。今じゃ使われなくなった、陶器を作る杉ベラなんですよ。これも、へぎを張り合わせて作っている物です……でも私は、またいつか、これが必要になると思っています。いくら技術や設備が発達しても、複製するだけの進化はいけない。神様が宿るあなたの麹蓋は、その真逆にあるということです」
平の杉ベラに瞳を潤ませる高山の前に、太郎の手が伸びた。
「あっ!」と声を上げる龍二と銀平の目で、麹蓋の焼き印部分を剥がす太郎の指先が動いた。それは、みごとな一枚の薄い板となって剥がれた。
「どうぞ、高山さん。これを御守りに」
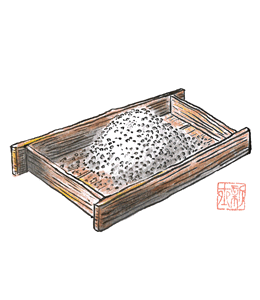
両の手のひらで太郎から受け取る高山に、客たちも自然に頷いていた。
「さすが、太郎さん。粋なふるまいです。ついでに、残っているいくつかの麹蓋に蕎麦をのっけて、“へぎ蕎麦”といきませんか。ねえ皆さん! 注文しますよね」
聞こえよがしな龍二の声に、客たちはいっせいに手を挙げた。
「おう! 俺も頼むぜぇ! なんたって、神様が付いてくる蕎麦だろ。もちろん、ワサビをがっつり効かせてくれよ!」
腕まくりする銀平を、太郎の声がいなした。
「いやぁ、悪いけどよ。銀平の分まで、蕎麦の在庫がねえや。まあ、おめえは酒の勉強もしねえし、もはや神様に見放されちまってるから食っても無駄だ」
「そ、そんなぁ!」
ガックリとうなだれる銀平に、どっと客たちの笑い声が巻き起こった。
麹蓋の山からこぼれた麹米が、銀平の前で嬉しそうに弾んだ。
