忘年会の賑わいもひと区切りついたせいか、師走半ばのポンバル太郎はまばらな客足だった。余裕のある店内に、カウンター席へ向かう平 仁兵衛が厚手のコートを脱ぎながら嬉しげに口を開いた。
「太郎さん、私も今夜はハタハタ鍋を頼みます」
ヘリンボーン柄のマフラーを外す平の視線の先には、黒革のブルゾンを着た高野あすかが腹から朱色の卵が弾けているはたはたの鍋を前に置き、隣席の着物姿の女性に錫のチロリを傾けている。
盃に添える指先をじっと見つめる平の視線に、妙齢とおぼしき女性は透き通るような肌の口元をほころばせた。いつになく平が赤面すると、あすかは大袈裟に声を発した。
「あ~、平先生。私なんて見向きもしないくせに、佳代さんにたじろいじゃって。やっぱり、秋田美人は得だよねぇ」
あすかの声に、スッピン顔で色白な女性をチラ見していたテーブル席の男たちが納得したように頷いた。
すると、カウンターの向こう側の太郎が平へ聞こえよがしに訊ねた。
「あなた、西嶋 佳代さんでしょう? あすかの書いた記事に紹介されてた、秋田の女性杜氏さんですね。その酒、あなたが造った純米酒なんでしょ?」
燗したその純米酒はあすかが先週、太郎へ入荷を頼んだ品物だった。太郎も酒屋に無理強いして仕入れ、初めて利いてみたが、あすかのテイスティングどおり味が濃く、はたはた鍋のしょっつるダシにもってこいの燗上がりする旨さを持っていた。
太郎は、今夜やって来るあすかにこの酒を選んだ理由を訊ねてみようと思ったが、同席した佳代が秋田弁まじりでハタハタ鍋を注文した途端、それを造った本人と読んだ。
「はい、私の仕込んだお酒です。米は秋田県の美山錦で、仕込み水は鳥海山系の軟水です。なるべく香りの立たない酵母を使っていますから、常温か燗にするのがオススメです」
素のままの美しさで生真面目に語る佳代を、あすかは近いうちに必ず脚光を浴びる人物と、酒に酔ったのか饒舌になった。そして15年前に酒蔵のアルバイト主婦だった佳代が今年杜氏になるまでの道のりを紹介すると、店内の客たちも聞き耳を立てた。
その頃、男社会の酒造現場では当然ながら女性の勤務に難色を示していた。女人禁制を頑として譲らない杜氏は、佳代に瓶詰めと甑(こしき)や道具の水洗いしか任せなかった。ところがある日、扉の開いている麹室(こうじむろ)が乱雑に放置されているのを見かね、つい佳代は室の掃除を内緒で手がけてしまった。すっきりと整頓されている室に、鷹揚な蔵人たちは誰がやったのか気にもかけなかった。彼らの仕事が終わるたび、佳代は幾度となく整理を続けた。
「でも、ついには杜氏に見つかっちゃって、大問題になった。“好事、魔多し”ってヤツね。だけど、蔵元は『女性だからこそ、できたのだ。男所帯は、ともすれば現場整理が杜撰になる。これは革新的な出来事だ』って、殊勝にも考え方を変えたの。そこから佳代さんは、女性蔵人としての一歩を踏み出した」
あすかが溜飲を下げるような面持ちで披露すると、間髪をいれず、しゃがれた声が聞こえた。
「なるほど。ほんなら、わしも一本、そのお燗をつけてもらおうか。ハタハタの鍋は、平さんと一緒につついてもかまへんやろ?」
後ろから飛んで来た関西弁に、佳代がほんのりと色づいた頬で振り返った。
「あ~あ、また佳代さんにまいっちゃいそうなオジサマが来ちゃった」
背中の響きで中之島哲男と判り、苦笑するあすかだったが、次の瞬間、佳代が身じろぎ一つせず目をみはっているようすに首を傾げた。
「な、中之島さん……ども、ご無沙汰していまっす。おっ、驚きましたぁ! まさか、ここでお逢いするなんてぇ」
動揺する佳代の声は完璧に訛っていて、清楚な容姿とあまりに不釣合いだった。
声を失くしているあすかに代わって、太郎が口を開いた。
「中之島の親爺さんの知り合いでしたか。なるほど、いい蔵人になるわけだ」
しかし、その声に中之島は相貌を崩すことなく、佳代をまっすぐ見つめていた。二人の間の空気は、やけに緊張していた。
「……いえ、私はまだまだです。15年前の中之島さんの宿題、まだ、できていません」
「15年前って、ひょっとして佳代さん、蔵人になる時に中之島さんと会ってたの? それって、私は聞いてないよ」
あすかのぼやきに、佳代は罰が悪そうに答えた。
「あの頃……蔵元の親友だった中之島さんが見学にいらしたのです。そして麹室に入られた後で、私に小声で囁いた。『室の整理や掃除は余熱で汗もかくし、大変やねぇ。けど、あんたの使ってるシャンプーの微かな匂いが漂ってる。それは吟醸酒造りに良くないから、室の隅っこにリンゴを置いてみなはれ』と教えてくださったんです。体臭だけで、私が室へ入っているのを見抜かれた時、正直、怖ろしかった」
佳代の話しによると、当時、蔵元は地元向けの普通酒が主流で、特定名称酒はほとんど手がけておらず、今後の吟醸造りのご意見番として中之島を招いたのだった。中之島は、実のところ女性の整理整頓の能力だけでなく、デリケートな感覚は、麹やモロミの温度管理など微妙な酒造りの仕事に適していると解説した。
「中之島さんは蔵元や杜氏に、女性は酒造りの諸訳に通じるのが早いと説得してくださいました。あの後押しがなければ、禁令を破った私は辞めさせられていたと思います。吟醸造りを始めた室にリンゴを置くことが、私の新しい役目になりました。そして、中之島さんが帰られる日、これを頂いたのです」
佳代は、鹿の子折りの巾着袋からお守り袋らしき物を取り出すと、口紐をゆるめて一片の紙切れを取り出した。
そこには、骨太い筆致で“室の花”と揮毫してあった。
「ふむ、見覚えのある筆づかいですねぇ。中之島さんのに似てますが、若干、勢いがありますな」
平が、太郎の用意した中之島のマイ盃に焼かれている字と見比べながらつぶやいた。確かに盃の「哲男」の筆致に似ているが、太郎にも、止めやはらいが力強く思えた。
「わしの字ですわ。まだまだ元気やった頃でっから、文字もヤンチャですなぁ……そやけど、佳代さんも、その紙切れをよう大事に持ってはったなぁ。まあ、捨ててへんちゅうことは、“室の花”になる日を目指して頑張ったっちゅうとこか」
中之島がようやく目尻をほころばせると、佳代は目頭をおさえながら細い声をもらした。
「はい……はい、ありがとうございます」
その横で、ハンカチを取り出したあすかが佳代に手渡しながら、紙切れを見つめて言った。
「中之島さん。“室の花”って、どういう意味ですか?」
「俳句の季語でな。昔は春が来るのを待ち焦がれて、盆栽や切り枝を家の室の囲炉裏や炉火で暖めて、早咲きさせたんや。それにあやかって、麹を造るあったかい室で佳代ちゃんが花開いて、はよう杜氏になれるようにっちゅう、おまじないや。女性にとって酒造りの現場はいろんな意味で厳しいことがあるが、冬を耐えて、杜氏として咲いて欲しかったんや」
中之島の言葉に、店の客たちからも感嘆するような、ため息がもれた。
記者癖で室の花の意味をメモするあすかに感心しつつ、平が言った。
「なるほど、ロマンですねえ。でも願いは叶ったじゃないですか。佳代さんは、今年から杜氏になったわけですから」
「それは……中之島さんが、このお酒をどう思われるかです」
ためらいがちな佳代の返事をさえぎるかのように、太郎の手がカウンター席に座る中之島の前へ純米酒の盃を置いた。
中之島は無言で、純米酒を利いた。
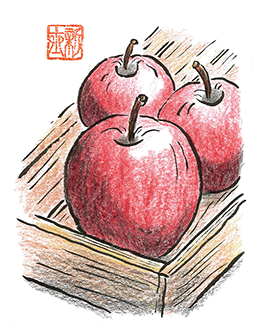
シュルシュルと酒を啜る音が水を撒いたような店内に響き、あすかや客たちは固唾を飲んで中之島の答えを待った。
「太郎ちゃん、和紙と筆ペンをもらえんか」
肩透かしを食らったあすかが
「ちょ、ちょっと、中之島さん。評価はどうなのよ?」
とじれったそうに問い詰めた。
中之島は黙ったまま、太郎が持って来た和紙と筆ペンを佳代の前に置いた。
「ようやく、宿題が終わったな。秋田の女性らしさのある、たおやかな旨味の純米酒や。佳代さん、ここへ“室の花”と書きなはれ。わしから蔵元に、この銘柄を提案するよってな」
佳代は感動のあまり、顔を両手で覆ってしまった。その背中を、あすかがさすりながら励ました。
「素敵な銘柄ね。佳代さん、ずっとずっと咲いてね!」
いつの間にか、太郎が客たちに純米酒の盃を配っていた。
中之島が客席に向かって盃をかざすと、全員が立ち上がり、佳代への乾杯を贈った。
