年の瀬も押し迫り、仕事納めまで数日を残す男たちの人いきれがポンバル太郎に充満していた。テーブル席では彼らの今年最後らしき酒宴が盛り上がり、冬休みに入って店を手伝う剣は新酒の瓶を抱えて、忙しげに立ち回っている。
太郎の指図をすぐに理解する剣の機敏な動きに、カウンター席の右近龍二が頬杖をつきながら目を細めていた。
純米酒の盃をなめる平 仁兵衛が目尻の皴をほころばせ、つぶやいた。
「龍二君もあんなふうに、利発な子だったんじゃないですか?」
「いいえ、僕なんて盆百なハナタレ小僧でした。気が利かなくて、いつも親父の説教をくらってましたよ」
「ほう、あなたのお父さんは土佐のいごっそうだから、おっかなかったでしょうねぇ」
照れくさげに相槌を打つ龍二は空いた冷酒グラスに酒を注ごうと、カウンターに置いた緑色の一升瓶に手を伸ばした。すると、剣がその瓶を奪って
「龍二さん、ちょっと借りるよ。は~い! お待ちどうさま~。松田さんの高知県へのご栄転、おめでとうございます!」
とテーブル席に陣取るスーツ姿の男たちに、土佐の純米吟醸を注いで回った。それも、太郎からの予めの指示だった。
「おい、坊や! 土佐の酒らしく、豪快に注いでくれよ!」
「でも、この高知の酒って、意外に軽い味じゃん。これなら日本酒に弱い松田でも、向こうへ行って接待や付き合い酒ぐらいはできるな。大して、辛口でもないしな」
同僚らしき二人のサラリーマンが、ほろ酔い口調で、真ん中に挟んでいる細身の男を肩で小突いた。二人は、濃厚な生原酒をずいぶん飲んでいる。
その声が耳に入っている龍二に向かって、剣が口パクで「なめたら、いかんぜよ」と顔をしかめて見せた。しかし龍二は歯牙にもかけない顔で、さっさと瓶を戻せと黙って手を振った。
「うむ、まっこと、土佐の酒など怖るるに足らずぜよ。な~んちゃって! おっほん、松田君。君には期待してるんだから、もっと明るい顔で飲め! 年明け早々の異動で大変だろうが、高知営業所を立て直す気概で頑張ってくれよ。がっははは!」
テーブル席の真ん中に座る上司らしき男が呂律をからめて、松田の目の前に冷酒グラスをかざした。その座の全員が異口同音に「乾杯!」と叫んだが、どこか皮肉めいた笑みや厄介払いができたかのような表情を覗かせていた。
「はっ、はい! ありがとうございます……頂きます」
カウンターからそのようすを見つめる太郎に酒を注がれる平も、声音が尻すぼみになる松田の気持ちが逡巡してることを感じた。
「まあ……上司に都合のいい、左遷ですか。でも、どうせ土佐に行くなら、とことん日本酒にひたってもらいたいですねぇ」
平の感想に、太郎が頷きながら龍二を一瞥した時、上司が剣に向かって声を上げた。
「おい、チビ! この店で一番強い、土佐の酒ってないのか!? 松田君、まずは鍛えておこうじゃないか」
横柄な物言いに太郎が口を出そうとした途端、龍二が無言で立ち上がり、店内の冷蔵ケースから黒い一升瓶を取り出した。そして太郎に目で詫びると、松田のテーブル席に近づいた。
「失礼します。私はこの店の常連で、右近と申します。これ、土佐っぽの僕がオススメする大辛口生原酒です。アルコール度数は21度ありますが、よろしければ土佐流で飲んでみませんか?」
「おう、それはありがたいですな。松田君、土佐の流儀を教えてもらおうじゃないか」
上司の男は、唐突ながら律儀な態度の龍二にまんざらでもないといった口調で答えた。
「はっ、はぁ……俺、大丈夫かなぁ」
おじけづく松田に、龍二は笑みを返すと
「じゃあ、接待のプロである上司の方から参りましょう。まずは一献!」
龍二は豪快に一升瓶の底を片手でつかむと、グラスになみなみと生原酒を注いだ。それが上司に拒むひまを与えないパフォーマンスと太郎はほくそ笑んでいた。
「プハー、これは凄い! ガツンとくるね~。ゆっくりといこうか」
ふた口ほど飲んだグラスを置こうとする上司を、龍二が即座にとがめた。
「それ、ダメです。土佐では注がれた盃を飲み干すまで、卓に置いちゃいけません。さらに自分が飲み干した盃を相手に渡して、酒を注ぐ。相手も飲み干して、また盃を返され、注がれた酒を飲み干す。これが、土佐の“献盃返盃(けんぱいへんぱい)”です」まばたきもせず語気を強める龍二に、二人を見つめるテーブル席の客たちが口をつぐんだ。
「ちょっと待て。私は飲むのに、時間がかかるんだよ。おい、主役はお前だ! 松田、お前が飲み干せ!」
松田はあわてて上司からグラスを受け取り、あおったが、それを飲み干すことはできなかった。
傲岸な態度で松田にグラスを差し出した上司を、太郎の脇に立っている剣が鼻で笑った。
龍二は彼らしからぬ、怜悧な笑いを浮かべて上司に語った。
「失礼ながら、あなたは土佐じゃ出世できません。高知県には“飲み上がり”の文化がありましてね。昔は献盃返盃ができなきゃ、都会から高知へ赴任しても出世できませんでした。ようは、酒豪じゃないと男として認められないことが多かった。土佐の酒自体がどうこうじゃなくて、今も酒文化は強烈なのです」
上司はこめかみに浮かぶ血管をひくつかせたが、グラスを卓におけないままの松田だけでなく同僚たちも龍二の話しに耳を傾け始めた。
龍二はおもむろに手提げバッグを開くと、小さな盃を布包みを取り出して松田の前に置いた。
「その文化の一つが……これです。開いてみれば、いいですよ」
龍二が松田の手から冷酒グラスを取ると、動かしようのなかった同僚たちは胸を撫でおろした。しかし、松田が包みを開けるとなにやら得体の知れない盃が転がり、またもや表情を曇らせた。
底が尖った駒のような形の盃に、怪訝な顔をしていた松田がつぶやいた。
「べく盃だ……僕、本物を見たのは初めてです」
卓の上でゆっくりと動く盃に、上司が瞳を凝らした。
「べ、べく? ってなんだね? どんな字を書くんだ? それに、これは立たないじゃないか?」
「可盃と書きます。漢文で可の字は返り点みたいに句の上にあって、下には置きません。そこから引用して、飲み干さなきゃ下に置けない盃ってわけです」
素焼きの盃の底をつまんだ龍二が上司に手渡そうとすると
「じょ、冗談じゃない。そんな盃を持ったら、体がいくつあってももたんよ。もういい! おい、亭主! お勘定だ。おい、みんな次へ行くぞ!」
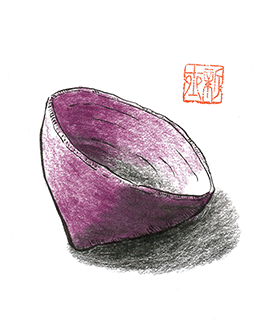
キレた上司の声にうろたえる者や、そそくさと財布を出す男たちの中で、松田はじっとべく盃を見つめていた。
「おい、松ちゃん。次に行くよ! 早くしないと、またパワハラくらっちまうぜ」
「いや、俺はいい。行かないよ。もう、あの人に媚びるのはごめんだ。それに、このべく盃や飲み上がりを知って、来年からは高知で生き方が変わりそうだよ。右近さんでしたね……もう少し、土佐流を教えて頂けませんか」
上司はそんな松田の声を聞くふりもなく、扉を開け放って出て行った。
ようやく止まったべく盃を松田の指がつまむと、剣が土佐の大衆的な本醸造を持って来た。龍二はそれも太郎の指図と解って、カウンターの面々に笑みを返した。
剣が注ぐ酒を緊張した面持ちでべく盃に受ける松田へ、龍二がようやく満面の笑みを見せた。
「坂本龍馬もひ弱な少年でした。酒蔵の息子なのに、若い頃は酒に弱かった。でも、土佐の仲間と献盃返盃を重ね、飲み上がって、大きな男になったんです」
「はい! べく盃を持って、土佐で頑張ります」
二人に酒を注ぎ終えた剣が、上司たちの出て行った先に向かって叫んだ!
「なめたら、いかんぜよ!」
