ヒグラシの声がパッタリと消えた街路樹の根っこから、時折、コオロギの声が聞こえる頃になった。東京湾から吹く冷えた風は昼の熱気を洗い流し、澄んだ夜気の中、秋の色に染まるスカイツリーが満月の明りに映えている。
ポンバル太郎の店内にも、花瓶代わりの青い一升瓶にすすきの穂が飾られていた。
「冷えてきましたねぇ。ようやく秋めいて、お燗が好きな私には、とっても嬉しい季節です」
カウンター席の平 仁兵衛が錫のチロリを独酌しつつ、目尻をほころばせた。白磁の盃の中が琥珀色なのは、山廃純米酒のぬる燗だからである。
あたかも満月を想わせる色合いは、粋人の平を喜ばせた。その面持ちを待っていたかのように、太郎が声をかけた。
「平先生、今夜はちょいと、おもしろい料理を山廃純米酒に合わせてみませんか」
「と言うと、この中のメニューですかな?」
平が手にした本日のおすすめメニューは、松茸や芋煮など秋の味覚を揃えていた。それは店を手伝う剣が先週末に一新していたが、太郎は首を横にふった。
「そこにはない、チーズフォンデュって料理です。山廃や生もと純米酒と、よく合いますよ」
「ほう! チーズですか。ふむ、以前に龍二君から日本酒はチーズを使ったイタリアンにも合うって話を聞いたことがあります。私は初体験ですが……じゃあ、やってもらいましょう」
平は細くなった目を開いて、好奇心を露わにした。
それを耳にしたテーブル席の若い男たちは
「チーズフォンデュって、普通は白ワインで食べるんじゃねえの?」
と疑うように口を揃えた。しかし、太郎は気にかけず、冷蔵庫の中から大きな円柱形の塊を取り出した。ひと抱えほどの平たくて丸いチーズには、英語が焼印されている。
「これは、立派なチーズですなぁ。どこの国のチーズですか?」
「オランダ産のゴーダチーズですよ。本来のフォンデュはスイス料理なので、地元のチーズを使いますけど、このチーズは濃厚でクリーミィ。酸味もあって、山廃や生もとの酒と相性がいいんですよ。これをスライスして鍋にたっぷり溶かし、茄子などの秋野菜や旬の鮭を熱いチーズにつけて食べてもらいます」
平が目の前に転がされたゴーダチーズに見入っている間に、太郎は炭火を熾した小さな七輪に、銅製の丸鍋を乗せた。そして、再びチーズを引き取ると、スライサーで薄く切り取り、鍋で溶かし始めた。
たちまち熱したチーズの濃い匂いがカウンターに満ちて、平が一瞬、眉をしかめた。
「けっこう濃厚ですねぇ。こりゃ、胸やけするかもしれませんなぁ」
「大丈夫ですよ、平先生。ちゃんと和風の隠し味も付けますから。もうすぐ、それを持って来てくれます……おっ、来た来た!」
答える太郎の視線に合わせて、平が玄関を振り返った。扉のガラス越しに見えたのは、手越マリの派手な花柄ブラウスだった。
「太郎ちゃん、お待ちどう。遅うなったばい」
鳴子を響かせて登場したマリはカウンター席に座ると、茶色い塊を置いた。慌ててやって来たのか、香水と汗のまじった匂いがチーズの香りとからまり、客たちの鼻先をいっそう突いた。
しかし、それも気にならないようすの平は、塊に目を凝らしてつぶやいた。
「なるほど、味噌ですか。しかも……甘口の九州味噌だ」
「ええ、長崎の麦味噌です。チーズは麦から作るパンに合います。パンの麦芽の旨味は、麦味噌も同じ。だから、チーズにも合うはずです。山廃や生もとの濃厚な味、辛さや酸味も、濃くて甘いこの味噌に負けないですから」
太郎は袋の味噌を取り出すと、匙で加減しながら溶けたチーズに入れた。
すると強いゴーダチーズの匂いはまろやかに落ち着き、テーブル席まで漂った湯気に不審げだった客たちの表情が変わった。
「あっ、味噌バターラーメンの匂いじゃん! これなら、たぶん日本酒にイケるよ! 太郎さん、俺たちも同じ鍋を頼んでいいすか?」
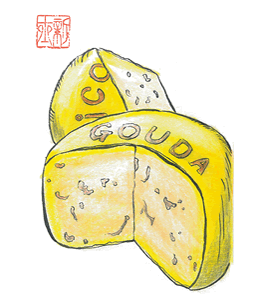
素朴な和食を好む平の思いがけない答えに、マリが串を持ったまま目を丸めた。
鮭のフォンデュを手にする平が、テーブル席の男性客たちに優しい口調で言った。
「皆さんはチーズフォンデュに白ワインとおっしゃいましたが、チーズは冷めると固まります。ですから、冷えたワインだと腹の中で塊になってしまいますよ。それならば、お燗したあったかい日本酒を私はおすすめします」
メニューの白ワインを注文しかけていた若い男が、仲間の顔を見返した。
全員の得心顔に、男は満面の笑みで太郎たちへ答えた。
「じゃあ、僕らはチーズに足す味噌は少な目にして、味のやわらかい特別純米酒を熱燗でお願いします」
鍋に味噌を入れる寸前、太郎が手を止めて答えた。
「うむ、なかなか解ってるね。山廃系が苦手なら、その手もあるなぁ」
すると、マリが豊満な体を揺すって男たちに詰め寄った。
「あんたたち、食わず嫌いたい! そういわず、九州の味噌をたっぷり入れてみるたい!」
尻込みする客たちの苦笑いが、チーズフォンデュの湯気の中に揺れていた。
